南薩の神話もついに最後のエピソードである。
山幸彦は海神の宮で、海神の娘トヨタマ(豊玉)姫と結ばれたのであるが、海幸への仕返しを果たした後にトヨタマ姫がやってきて、「子どもが産まれるのでやってきました」という。彼女は海辺に産屋を作り、鵜の羽で屋根を葺いていたところ急に産気づいた。そして言うには「異郷の人間は、産む時は本当の姿になります。私も本当の姿で産もうと思いますので、お願いですから覗かないように」として産屋に閉じこもった。
山幸彦はその言葉を訝しんで産屋を覗いてしまい、そこに大きなサメがのたうっているのを見て仰天。そのためトヨタマ姫は正体を見られたことを恥じ、産まれた子どもにウガヤフキアエズ(鵜の屋根を葺き終えないうちに、という意味)という不思議な名前を付け、子どもの養育を妹のタマヨリ(玉依)姫に任せて海神の宮に帰ってしまった。
このウガヤフキアエズは、長じて叔母に当たるタマヨリ姫を娶り、4人の子をもうけるが、そのうちの1人が後の神武天皇である。この神武の誕生で記紀神話の幕が閉じることになる。
ところで、タマヨリ姫の正体もまたサメであったとは記紀には書いていないが、姉妹である以上タマヨリ姫もサメと考えるのが自然だ。とすると、神武天皇は母(タマヨリ姫)と祖母(トヨタマ姫)がサメということになり、血統的には3/4がサメということになる。天皇家というのは、祭祀的には稲に関係する農耕的性格が強いが、その起源は多分に海洋的な性格を持っている。サメを祖神とする考え方は南洋に多いと聞くが、ここにも隼人が持ち込んだ海洋性が見えるようである。
さて、サメが正体のトヨタマ姫だが、これを祀っているのが、水車からくりで有名な知覧の豊玉姫神社だ。知覧はトヨタマ姫と縁が深く、その陵(墓)が残っていることを始めとしてその伝説が多く残っている。特に有名なのが「取違伝説」だ。
なんでも、海神からそれぞれ川辺と知覧を治めるように使わされたトヨタマ姫とタマヨリ姫であったが、頴娃から知覧に着いて一泊したところで、犀利なタマヨリ姫は土地の豊かな川辺の方が有利であることに気づき、トヨタマ姫がのんびりしている隙に川辺に行ってそこを治めたということである。本来行くべき所と逆に取り違えて行ったということで、その一泊した場所を取違(とりちがい)というようになり、今でもそこには取違さんという変わった苗字の人が住んでいる。ちなみに川辺側でタマヨリ姫を祀っているのは、かつて川辺の総鎮守であった飯倉神社である。
これは記紀神話にはないエピソードだし、ストーリー的にも記紀神話に接続する箇所もなく、かなりローカル色が濃い。もともとの取違伝説では、取り違える対象が天智天皇の第一皇女と第二皇女だったという話もあり、後世に改編されたものという可能性も大きいが、ともかくトヨタマ姫は知覧の地元の神だという意識があったことを示唆している。南薩における記紀神話は、天孫ニニギがコノハナサクヤ姫と出会ったのが笠沙、海幸と山幸がケンカしたのが笠沙〜枕崎の西南海岸というように巡って、トヨタマ姫の出産で知覧に至って終わるわけである。
このように、南薩は記紀神話の舞台として重要な地域であるにも関わらず、それがあまり認知されていない。その理由としては、このあたりには立派な古社・大社がないことが考えられる。仮に出雲大社のようなモニュメンタルな神社があれば、それが崇敬の対象としてわかりやすいし、なによりそこを中心に観光業が栄えて経済的にも潤う。結果的に神話伝説への関心も増し、対外的なアピールも盛んになる。
しかし、現実の加世田〜知覧の地域には、観光客が大勢訪れるような大規模な神社はなく、いくら神話の舞台とはいえ、そこに広がるのは縹渺とした風景だけだ。それが逆に本物っぽいという通もいるだろうが、一般的には面白味に欠ける。そう考えると、南薩の神話が注目を浴びることは今後もあまりなさそうだが、ここにはかつて阿多隼人たちが山海を舞台に活躍してつくり上げた日本の源流の一つがあると言えるだろう。
【参考文献】
『知覧町郷土誌』1982年、知覧町郷土誌編さん委員会
『古事記』1963年、倉野憲司 校注
2012年12月31日月曜日
2012年12月26日水曜日
隼人の南洋的神話=海幸・山幸——南薩と神話(4)
 |
| 黒瀬海岸(撮影:向江新一さん) |
なんでも、天孫ニニギは高千穂峰に降臨した後、舟で南下し、たどり着いたのがここ黒瀬海岸だということで、うら寂しい漁港に神代聖蹟「瓊瓊杵尊御上陸之地」という仰々しい石碑も建っている。またこの故事に因み、ここは別名「神渡海岸」ともいう。
正統派の記紀神話では舟で南下したというエピソードはないわけで、これはローカルな神話なのだが、だからこそ面白い。というのも、神さまが海の向こうからやってくる、という神話はポリネシアなど南洋の神話に多く、古代の隼人たちの海人的性格を示唆しているように思われるからだ(ちなみに遊牧民系だと、神さまは天から降りてくる場合が多い)。
ニニギの息子たちの海幸彦・山幸彦の神話は、そういう海人たる隼人が記紀へ持ち込んだ神話だろう。話の筋はこうである。山幸は海幸に「仕事道具を交換しよう」と持ちかけ釣針を借りるが、海に釣針を落としてしまう。その弁償に1000個の釣針を新たに作ったが海幸は「元の釣針を返せ」と納得しない。山幸が途方に暮れていると、塩椎神(シオツチのカミ)が来て「この”間なし勝間の小舟”に乗ってワタツミ(海神)の宮へ行きなさい」と言う。その通りにいくと海神の宮に着き、そこで出会った海神の娘、豊玉姫と結ばれ3年を過ごす。
そして山幸はふと海幸とのケンカを思い出し、海神に相談すると、海神はいろいろな魚を集めて釣針の行方を問う。そこで鯛の喉に例の釣針が引っかかっていることが判明。山幸は海神から「塩盈珠(しおみつたま)」「塩乾珠(しおふるたま)」という水を自在に操る宝物をもらい、釣針とともに帰還。この道具を使い海幸を懲らしめ、その結果海幸は山幸に服従を誓って物語が終わる。
この神話は南薩に残る神話でも最も中心的、かつローカル性が確実なものだろう。例えば、金峰町の双子池はコノハナサクヤ姫が海幸たち兄弟を産んだところというし、笠沙町の仁王崎は「二王の崎」の意であって、海幸山幸が兄弟ゲンカをしたところという。また枕崎は山幸が”間なし勝間の小舟”に乗って最初に付いた場所といい、枕崎の旧名「鹿篭(かご)」はこれに由来するという。ついでに、指宿には「指宿のたまて箱」の由来でもある竜宮伝説が伝えられているが、竜宮伝説=浦島太郎物語は海幸・山幸の神話の変形なのだろうと考える人もいる。もちろん海幸・山幸の神話は南薩だけに伝えられているものではなく、安曇氏の海神信仰も混淆しているようだが、物語の原型は隼人たちのものだっただろう。
ところで、海幸山幸の話は神話学的には「釣針喪失譚」と呼ばれ、南洋に多く分布しており、特にミクロネシアのパラオ島、インドネシアのケイ諸島、スラウェシ島にはこれと酷似した神話がある。どうも、隼人族はこうした南洋系の人々と近い関係にあったようだ。
ちなみに、前の記事で紹介した「天皇が短命なのは醜いイワナガ姫を拒否したため」という神話も、類似のそれがインドネシアからニューギニアの南洋に分布しており、中でもスラウェシ島のある部族が伝えている神話とは非常に共通点が多い。
このような事実から推測すると、隼人たちは黒潮に乗って南洋から来たか、あるいは南洋の人々と共通の祖先を持つ人々だったのだろう。事実、金峰町の高橋貝塚からは南洋でしか採れないゴホウラという貝の腕輪の半加工品が日本で唯一発見されているし、吹上浜の伝統的な漁具のカタギテゴという魚籠(びく)は日本では南九州にしか存在しないが、東南アジアには広く分布している。
『ぼくの鹿児島案内。』の著者、岡本 仁さんは「鹿児島は東南アジアの最北端」と言っているが、これは案外的外れではなく、鹿児島は文化的には東南アジアと共通項が多いのである。
それはさておき、神話に話を戻すと、この山幸彦が天皇家の祖先であり、海幸彦が隼人阿多の君の祖先ということになっている。つまり、阿多隼人は天孫から分かれた天皇家の親戚ということになっているのである。記紀神話は各氏族の天皇家との関係を示す寓話という側面があるので、天皇家と親戚ということ自体は特筆大書すべきものではないが、天孫から分かれた子孫という設定は格が高いので、隼人たちの朝廷における重要性を示しているとも考えられる。
ただし、正統派の記紀神話解釈では、この神話は、隼人の祖(海幸)が天皇家(山幸)に服属を誓うということで、隼人族が朝廷に服属すべき由来を説明したものとされている。南薩の神話の中心である海幸・山幸の神話が、朝廷への服属の神話にさせられているというのも、なんとも皮肉なものだ。そもそも、海に生きる海幸彦が、海神を味方につけた山幸彦にやっつけられるという話自体、皮肉な展開なのだけれど。
【参考文献】
『日本神話の源流』1975年、吉田敦彦
『海の古代史 ー東アジア地中海考ー』2002年、千田 稔 編著
『古事記』1963年、倉野憲司 校注
2012年12月24日月曜日
薄倖だった秋かぼちゃ
先々週、初の「加世田かぼちゃ」の収穫・出荷を行った。
その結果は、すでに予見されていた通り、あまり芳しいものではない。約2000粒の種を植えて、出荷できたのがコンテナ約70箱分。小さかったりキズがひどかったりで出荷できなかった規格外品が約20箱分。収量も少ないし、規格外品の割合が非常に高かったのが痛い。
原因としては、(1)定植が若干遅れたこと、(2)定植時に雨が異常に多かったこと、(3)台風が2回来たこと、(4)生長期に逆に日照りが続いたこと、などが挙げられる。天候に翻弄された部分以外の管理は、先輩農家Kさん兄弟の全面的な支援・指導を受けたおかげでそこまで悪くはなかったと思うが、まあはっきり言って結果が伴わなかった…。
「加世田かぼちゃ」として出荷できない小さなかぼちゃは、いつもの「大浦ふるさと館」で売ることにしたが、こちらの売れ行きも正直いまいちである。初夏から続くかぼちゃのシーズンの最後であり、新かぼちゃといっても一般消費者からすると新鮮さが感じられないのだろう。先日は冬至で、「冬至かぼちゃ」の需要があるかと期待したが、売れ行きにはあまり関係なかったようだ…。
とはいっても、一応完熟かぼちゃというだけあって、そこら辺のスーパーで売っている一般的なかぼちゃよりは少し美味しいのではないかと思うし、規格外品とは言え調理を考えると便利なサイズであり、さらにかなり安くお買い得でもある。私は800g〜1kgくらいのやつを150円で売っているが、スーパーのカットかぼちゃの半額程度ではないかと思う。
「大浦ふるさと館」ではポンカンの販売が始まってカンキツの季節も到来したので、お立寄りの際には隅に追いやられている薄倖なかぼちゃコーナーも見てみて欲しい。
その結果は、すでに予見されていた通り、あまり芳しいものではない。約2000粒の種を植えて、出荷できたのがコンテナ約70箱分。小さかったりキズがひどかったりで出荷できなかった規格外品が約20箱分。収量も少ないし、規格外品の割合が非常に高かったのが痛い。
原因としては、(1)定植が若干遅れたこと、(2)定植時に雨が異常に多かったこと、(3)台風が2回来たこと、(4)生長期に逆に日照りが続いたこと、などが挙げられる。天候に翻弄された部分以外の管理は、先輩農家Kさん兄弟の全面的な支援・指導を受けたおかげでそこまで悪くはなかったと思うが、まあはっきり言って結果が伴わなかった…。
「加世田かぼちゃ」として出荷できない小さなかぼちゃは、いつもの「大浦ふるさと館」で売ることにしたが、こちらの売れ行きも正直いまいちである。初夏から続くかぼちゃのシーズンの最後であり、新かぼちゃといっても一般消費者からすると新鮮さが感じられないのだろう。先日は冬至で、「冬至かぼちゃ」の需要があるかと期待したが、売れ行きにはあまり関係なかったようだ…。
とはいっても、一応完熟かぼちゃというだけあって、そこら辺のスーパーで売っている一般的なかぼちゃよりは少し美味しいのではないかと思うし、規格外品とは言え調理を考えると便利なサイズであり、さらにかなり安くお買い得でもある。私は800g〜1kgくらいのやつを150円で売っているが、スーパーのカットかぼちゃの半額程度ではないかと思う。
「大浦ふるさと館」ではポンカンの販売が始まってカンキツの季節も到来したので、お立寄りの際には隅に追いやられている薄倖なかぼちゃコーナーも見てみて欲しい。
2012年12月16日日曜日
嘘みたいな話ですが、SoftBankのアンテナが立ちました
ちょっと書くのが遅くなったが、11月に家の近所にSoftBankの中継基地(電波塔みたいなもの、以下「アンテナ」)ができて、我が家が圏外でなくなった。
以前書いたSoftBankへの悪口(?)が未だに結構アクセスがあるので、公平を期するため今回はSoftBankを褒めておきたい。 というのも、どう考えてもこの過疎地にアンテナを建ててペイできるとは思えないからだ。
事実アンテナが立つまで「もし自分がSoftBankの社長だったら絶対ここにはアンテナは立てないなあ」と思っていた。今後人口が増えることは見込めないから新規加入者の増加はないだろうし、現在の利用者も極めて少ないからサービス向上にもあまり繋がらない。
「極めて少ない」というか、もしかしたらこの付近でSoftBankのユーザーは我が家だけなのかもしれない。このアンテナが立つ前は、我が家を含めて行動範囲のほとんどが圏外だったので、こんなところでSoftBankを使うマヌケが私たち以外にいるとは思えなかった。
だから、ちょっと誇張して言えば、今回新しく立ったアンテナは、ほとんど我が家のために立ててくれたようなものである。有り難く使わせていただく。
ところで、現在SoftBankはLTE(高速データ通信)のエリアを拡大していることをテレビCMで訴えているが、我が家では当然LTEは使えない。というか、WEBサイトで確認してみるとLTEのサービスエリア(とその拡大予定地域)はとても地方まで広がっているとは言えない状況で、CMの中の主張とかなり相違がある。ただ、地方の中でも鹿児島(薩摩半島)はかなりマシな方で、加世田までは来ているので頑張って大浦まで拡大させてほしい。
ともかく、このアンテナ設置が(予想通り)大損だったということになると、SoftBankのサービスは今後の向上が見込めないので、周りに少しでもSoftBankユーザーが増えて欲しいと願っている。少なくとも今回、SoftBankは大損する可能性のあるところまでアンテナを立てる愚直な会社であることが判明したので、悪い会社ではないと思う。というか思いたい。
以前書いたSoftBankへの悪口(?)が未だに結構アクセスがあるので、公平を期するため今回はSoftBankを褒めておきたい。 というのも、どう考えてもこの過疎地にアンテナを建ててペイできるとは思えないからだ。
事実アンテナが立つまで「もし自分がSoftBankの社長だったら絶対ここにはアンテナは立てないなあ」と思っていた。今後人口が増えることは見込めないから新規加入者の増加はないだろうし、現在の利用者も極めて少ないからサービス向上にもあまり繋がらない。
「極めて少ない」というか、もしかしたらこの付近でSoftBankのユーザーは我が家だけなのかもしれない。このアンテナが立つ前は、我が家を含めて行動範囲のほとんどが圏外だったので、こんなところでSoftBankを使うマヌケが私たち以外にいるとは思えなかった。
だから、ちょっと誇張して言えば、今回新しく立ったアンテナは、ほとんど我が家のために立ててくれたようなものである。有り難く使わせていただく。
ところで、現在SoftBankはLTE(高速データ通信)のエリアを拡大していることをテレビCMで訴えているが、我が家では当然LTEは使えない。というか、WEBサイトで確認してみるとLTEのサービスエリア(とその拡大予定地域)はとても地方まで広がっているとは言えない状況で、CMの中の主張とかなり相違がある。ただ、地方の中でも鹿児島(薩摩半島)はかなりマシな方で、加世田までは来ているので頑張って大浦まで拡大させてほしい。
ともかく、このアンテナ設置が(予想通り)大損だったということになると、SoftBankのサービスは今後の向上が見込めないので、周りに少しでもSoftBankユーザーが増えて欲しいと願っている。少なくとも今回、SoftBankは大損する可能性のあるところまでアンテナを立てる愚直な会社であることが判明したので、悪い会社ではないと思う。というか思いたい。
2012年12月14日金曜日
田舎における農産加工へのハードル
鹿児島県立農業大学校が主催する「農産加工基礎研修」という一泊二日の研修を受けた。
内容は、農産加工の入門編の位置づけで、業務用機器の取扱の説明と実習、農産物加工の基礎知識の講義である。雰囲気的には、農産加工グループなどで活動を始めようという女性を対象とした研修で、私以外の受講者は全員女性であった。ただ、最近ではビジネス的に農産加工に参入したいという男性の参加も少なくないのだという。
私は、加世田かぼちゃをつかったジャムを商品化したいと思っているので、農産加工の基礎的知識を学ぶためにこの研修に参加したのだが、実習ではジャム制作の理論的知識を教えてもらい大変参考になった。こういう研修に参加すると、「こうしなくてはいけない」という基礎の部分とともに、「これくらいで大丈夫」という妥協点というか、現実的な落としどころが分かるのもいいことだ。
南薩地域振興局の方からは、「新規就農者が農産物加工に取り組むのは危険。農業でちゃんと成り立ってから手を出すべき」というアドバイスを頂いたけれども、研修を受けてみた感触としては、小さく始めるなら必ずしも時機を待つ必要もない気がする。
ただ、問題は加工施設を一から建設しなければならないことで、ここはもう少し制度的にハードルを低めることが出来ないかと思う。例えば、大浦には「農村婦人の家」という古風な加工施設があるが、これは既存の加工グループ以外は商品販売の目的では使えない。商用利用では、事故(食中毒)等が生じた時の責任問題などがややこしいということかと思うが、一グループのみには特権的に商用目的で使わせているわけで、ここがネックになっているわけではないと思う。こうした施設を一定の基準を設けて商用目的にも使えるようにすれば、産業興しにもなると思うので市役所の方にはぜひご検討願いたい。
というのも、こうした施設が使えなければ、建屋から作らなくてはならないのが田舎のこわいところである。都会なら、適当な物件が見つかれば借りて内装をいじるだけで済むが、田舎には借りられる物件はほとんど皆無なので、ちょっとした加工所でも100万円単位のお金を使って建てなくてはならない。空き屋はたくさんあるのにバカバカしいことだ。
「産業興し」などというと抽象的だが、要は新しい事業に取り組むハードルを下げ、個人のアイデアが具現化しやすい環境をつくっていくことだと思う。それには予算も必要だが、既存の施設を商用利用できるように変えていくだけでも、随分変わってくるのではないだろうか。もちろん、商用利用を可能にするためには、そのための制度や規則、役所側の覚悟も必要になる。人口減で予算も厳しい世の中なので、県、市町村にはそういう手間のかかるややこしい仕事も面倒くさがらずにやってもらいたい。
内容は、農産加工の入門編の位置づけで、業務用機器の取扱の説明と実習、農産物加工の基礎知識の講義である。雰囲気的には、農産加工グループなどで活動を始めようという女性を対象とした研修で、私以外の受講者は全員女性であった。ただ、最近ではビジネス的に農産加工に参入したいという男性の参加も少なくないのだという。
私は、加世田かぼちゃをつかったジャムを商品化したいと思っているので、農産加工の基礎的知識を学ぶためにこの研修に参加したのだが、実習ではジャム制作の理論的知識を教えてもらい大変参考になった。こういう研修に参加すると、「こうしなくてはいけない」という基礎の部分とともに、「これくらいで大丈夫」という妥協点というか、現実的な落としどころが分かるのもいいことだ。
南薩地域振興局の方からは、「新規就農者が農産物加工に取り組むのは危険。農業でちゃんと成り立ってから手を出すべき」というアドバイスを頂いたけれども、研修を受けてみた感触としては、小さく始めるなら必ずしも時機を待つ必要もない気がする。
ただ、問題は加工施設を一から建設しなければならないことで、ここはもう少し制度的にハードルを低めることが出来ないかと思う。例えば、大浦には「農村婦人の家」という古風な加工施設があるが、これは既存の加工グループ以外は商品販売の目的では使えない。商用利用では、事故(食中毒)等が生じた時の責任問題などがややこしいということかと思うが、一グループのみには特権的に商用目的で使わせているわけで、ここがネックになっているわけではないと思う。こうした施設を一定の基準を設けて商用目的にも使えるようにすれば、産業興しにもなると思うので市役所の方にはぜひご検討願いたい。
というのも、こうした施設が使えなければ、建屋から作らなくてはならないのが田舎のこわいところである。都会なら、適当な物件が見つかれば借りて内装をいじるだけで済むが、田舎には借りられる物件はほとんど皆無なので、ちょっとした加工所でも100万円単位のお金を使って建てなくてはならない。空き屋はたくさんあるのにバカバカしいことだ。
「産業興し」などというと抽象的だが、要は新しい事業に取り組むハードルを下げ、個人のアイデアが具現化しやすい環境をつくっていくことだと思う。それには予算も必要だが、既存の施設を商用利用できるように変えていくだけでも、随分変わってくるのではないだろうか。もちろん、商用利用を可能にするためには、そのための制度や規則、役所側の覚悟も必要になる。人口減で予算も厳しい世の中なので、県、市町村にはそういう手間のかかるややこしい仕事も面倒くさがらずにやってもらいたい。
2012年12月11日火曜日
本当は南薩に縁がないかもしれない日本史上初の美人——南薩と神話(3)
 |
| コノハナサクヤの銅像 |
ニニギが笠沙の御崎で出会った「麗しき美人(おとめ)」がカムアタツ姫、又の名をコノハナのサクヤ姫という。古事記ではこれ以前には女性の形容に「美しい」が使われていないということで、コノハナサクヤは神話上での我が国初の美人、ということになっている。ちなみにカムアタツ姫というのは「神阿多都(姫)」と書き、「阿多の姫」という意味である。
ニニギはコノハナサクヤに早速求婚し、父であるオオヤマツミ(大山祇神)によって承認される。だがこの岳父はコノハナだけではなく、その姉イワナガ(石長)姫も添えて二人をニニギの元に送った。しかしイワナガ姫は大変醜かったため、これを厭ったニニギはすぐにイワナガ姫を実家に送り返す。
これを恥じたオオヤマツミが嘆じて言うには、「岩のごとくいつまでも変わらないようにイワナガ姫を、 木花のごとく栄えるようにコノハナサクヤ姫を嫁がせたのに、イワナガ姫を送り返したからには、天孫の子どもたちは木花のようにもろくはかないだろう」と。これは天皇が短命な原因とされ、神話学的にはバナナ型神話の短命起源と分類される。
この神話の背景として、当時は姉妹が同じ男性に嫁ぐ一夫多妻制があった、というまことしやかな解説もあるが、疑問もある。というのも、姉妹が同時に嫁ぐ「姉妹型一夫多妻」というのは、通常は妻方居住、つまり男性が妻の実家に迎え入れられるという風習とセットであり、二人して夫の元に送られるというのは奇妙である。ニニギがたじろいでイワナガ姫を送り返したのも無理はない。
ともあれ、めでたく天孫ニニギは日本史上初の美女コノハナサクヤと結ばれた。そしてコノハナサクヤは一夜にして身籠もり、やがて臨月となる。だがいざ産もうという時に、さすがに一夜の契りでは妊娠しないだろうということでニニギはコノハナサクヤを疑い、「私の子どもではなくて国つ神(地元のやつ)の子どもに違いない」と言う。
ところで、この話の展開を考えると、どうもニニギはコノハナサクヤと一度しか寝ていないようで奇妙だ。別居でもしていたのだろうか。それとも、実際は妻方居住の習慣があったために、イワナガ姫を拒絶したニニギは二度とオオヤマツミの家に入れてもらえなかったのだろうか(※1)。それにしてもニニギというのは、譲られたはずの出雲ではなく日向に来たり、奥さんの姉を見た目重視で拒絶してお義父さんに怒られたり、出産の間際に「俺の子じゃないだろう」などと言ったり、なんだかおっちょこちょいな性格のようである。
ニニギに疑われたことを怒ったコノハナサクヤは、「もし貴方の子どもだったら無事に産まれるでしょう」と言って、大きな家を作り、その中に入って入り口を塞いで火を放った。そして燃えさかる火の中で3柱の神を無事出産して無実の罪を晴らしたのである。この神、美女にしては壮絶な性格だったようだ。ちなみにこういう証明方法を「うけい」という。そしてこの時産まれた3兄弟が、ホデリ、ホスセリ、ホオリであり、このうちホデリ=海幸彦とホオリ=山幸彦が次の神話の主人公になる。
さて、長々とコノハナサクヤの神話を辿ったが、実は通説ではカムアタツ姫とコノハナサクヤ姫は別人で、アタツ姫は阿多の土着の神であるが、コノハナサクヤは宮崎県にいた別の神なんじゃないかと言われている。つまり、カムアタツとコノハナサクヤの話が混じっているらしい。どこからどこまでが宮崎での話なのか、どこが阿多の話なのか今となってはわからない(※2)。
だが、3兄弟出産の伝説は阿多土着のもののようで、これに因む旧跡は南薩に多い。コノハナサクヤが出産したのが加世田の内山田にある竹屋ヶ尾で、ここには3兄弟の臍の緒を切った竹刀に由来する竹林(※3)、彦火火出見(ホオリ)尊誕生碑、竹屋(たかや)神社などがあり(※4)、竹屋ヶ尾自体が昭和15年には「神代聖跡」に指定されている。
だが、これらの旧跡は人気がないのか、あまり注目されることはないし、そもそもアピールもされていない。一方で、本当はあまりゆかりがないのかもしれないコノハナサクヤが「きんぽう木花館」の名前の元になったり、彫刻家の中村晋也氏(「若き薩摩の群像」の方)によりその銅像がつくられたりということで、やはり美人というのはキラーコンテンツなんだなあと思う。
※1 日本書記本文によると、ニニギがコノハナサクヤの方に「幸(め)す」=「行った」ということになっていて、つまり通い婚であったと受け取れる。こちらの方がそれっぽいストーリーである。
※2 宮崎県西都市には、コノハナサクヤを祭る都萬(つま)神社があり、西都原古墳群にはニニギとコノハナサクヤの墓と言われている古墳もある。ついでにオオヤマツミの墓とされる古墳もある。ただ、コノハナサクヤの神話のほとんどは実はカムアタツ姫の神話を元にしたもの、という可能性もあるので、本記事のタイトルに「本当は南薩に縁がないかもしれない」とつけたが、縁がある可能性もあるわけである。
※3 加世田と川辺の堺にある竹山。コノハナサクヤが捨てた竹刀が根付いたのが竹林のいわれというが、一度伐採されており、現在の竹叢は1984年に加世田市によって復活させられたもの。
※4 竹屋神社は今は加世田の宮原にあるが、1161年以前は竹屋ヶ尾にあったらしい。ちなみに、明治以前は鷹屋大明神といったようだ。また、南九州市にも同名で同様の由緒を持つ神社が存在する。
【参考文献】
『古事記』1963年、倉野憲司 校注
『日本書紀 上(日本古典文學大系67)』1967年、坂本太郎、家永三郎、井上光貞、大野 晋 校注
2012年12月4日火曜日
朝日の直刺す国、夕日の日照る国——南薩と神話(2)
南薩は日向(ひむか)神話の舞台となったところだが、日向神話を語る前に、記紀神話(古事記と日本書紀で語られる日本神話)の全体像もわかっていた方がいいかもしれない。
ということで、記紀神話について簡単に紹介する。これは天地ができてから神武天皇が誕生するまでを描いているが、大きく分けると次のような3部構成になっている。
第1部は高天原が舞台。イザナギとイザナミ夫婦が国産みを行い国土が完成、ところが火の神を産む時にイザナミは焼かれて死んだため、イザナギは黄泉の国までイザナミを追いかける。しかしその変わり果てた姿を見て退散。その禊ぎによってアマテラスやスサノオが誕生する。次がアマテラスとスサノオの姉弟ゲンカの話で、ケンカの結果スサノオは高天原から追放、落ちていったところが出雲である。
第2部はその出雲が舞台。高天原は「天界」なのでやや抽象的な話が多いが、出雲神話は地上の話なので具体性とストーリー性が強く、例えばスサノオのヤマタノオロチ退治、因幡の白ウサギなど人気の(?)神話が収録されている。スサノオの娘の旦那であるオオクニヌシの指導の下で国土が発展したのを見て、アマテラス一族はその国を譲ってもらおうと何度か使者を送り交渉した結果、結局オオクニヌシが国を譲ることを決定。
第3部はがらっと場面転換して日向(ひむか)、つまり九州が舞台。出雲を譲ってもらったはずのアマテラスだったが、孫のニニギをなぜか日向に派遣。ニニギは山の神の娘であるコノハナサクヤ姫と結ばれ、海幸彦と山幸彦の兄弟が誕生。山幸は海幸から借りた釣り針をなくしてしまい、海神の宮まで探しに行く。山幸はそこで海神の娘である豊玉姫と結ばれウガヤフキアエズが誕生、さらにその子どもがイワレヒコ=神武天皇であり、ここに記紀神話が終結する。なお、さらに記紀の物語は続くが、一応これ以降は神話ではなく歴史、ということになっている。
では、これからその日向神話について順を追って見てみよう。なお、内容は基本的に『古事記』に沿うが、適宜『日本書紀』を参照する。
アマテラスにより、なぜか日向の地に派遣されたニニギの一行だったが、彼らが降りて来たのが「高千穂のクシフル岳」というところで、(書記によると)さらにそこから「吾田の長屋の笠狭の碕」へ到達したという。この「阿田」が阿多のことで、「長屋」は加世田と大浦の境界である長屋山あたりといい、「笠狭の碕」(古事記では「笠沙の御崎」)が笠沙の野間半島だというわけだ。
このように、南さつま市の笠沙は天孫ニニギが初めてその居を構えたという記念すべき土地なのである。確かに、雄渾で荒々しい絶景が広がる笠沙は、我が国の黎明を飾るにふさわしい。
しかし、実はこの笠沙という地名はごく最近つけられたもので、古くからの地名ではない。大正時代までは現在の笠沙町と大浦町を合わせた地域は「西加世田村」と呼ばれており、大正12年にこれが「笠砂村」と改称、昭和15年に「笠沙町」となった経緯がある。笠砂村と改称したのは、「加世田村」「東加世田村」もあって紛らわしいということと自治意識を高めるのが目的だったらしく、古事記に因んで「笠砂」と名付けたらしい。つまり、今の笠沙町一帯が元から笠沙と呼ばれていたのではないのである。
ではデタラメでつけた名前かというとそうでもなく、江戸末期(1843年)に編纂された『三国名勝図絵』では、野間半島は「笠砂御崎」と記載されており、野間岳は昔「笠砂嶽」と呼ばれていたとされている。さらに遡る1795年に編まれた『麑藩名勝考』でも加世田は「笠狭之崎」であり、加世田は笠狭に田をつけたものとし、要は加世田という地名は笠沙が訛ったものだと推測されている(※1)。ともかく、「笠沙の御崎」が南薩にあったという主張はかなり古いのである。
また、南薩のこのあたりは神代の伝説やそれを祭る神社が多いのは事実で、阿多として栄えた古代に加世田一帯が笠沙という地名であったとしてもおかしくはないようだ。ただ、直接の証拠はないのに、『三国名勝図絵』ではあまりに自信満々に「笠沙の御崎」が現在の笠沙と同地であるという主張をしていて、客観性が足りないようにも見える。当時から「笠沙の御崎」は宮崎にあるという主張もあったが、同書ではこれを「無稽の妄説なり、詳に辨ぜずして明なり」と一蹴し、薩摩ナショナリズムを全開にしている(※2)。
それはさておき神話の方に戻ると、笠沙に到着したニニギは「ここは朝日の直刺(たださ)す国、夕日の日照(ほで)る国」だから、ここはとてもよい所だ、と言った。このフレーズはとても素敵で、普通いい国というのは農業・経済が盛んで地力があるところだと思うのだが、景色がいいからよい所だ、というのはなんともロマンチックだ。もともとアマテラスは、オオクニヌシが治めていた「豊葦原の水穂の国」という豊穣な国を譲ってもらいたかったわけだが、ニニギは朝日と夕日が美しいと喜んでいるのだから結構呑気な神である。
また「朝日の直刺す国、夕日の日照る国」というのは、笠沙の実態とも合致する。朝日の方は見たことはないが、東シナ海に沈む笠沙の夕日はとても美しい。まあこれは日本海側の多くの地域が該当するとは思うが。それから、「豊葦原の水穂の国」という美称と比べると、「褒めるのが風景しかなかったのかなあ」という気もしなくはないが(※3)、ロマンチックな言葉なので観光のPRにも使えると思う。
ちなみに、「笠沙の御崎」の位置については、北九州だという説もある。しかし、神話はそれ自体本当にあったことかどうかわからないわけで、どこかに確定できるものではないのは当然だし、いろいろ書いたが私としては別にどこでもいい。それより、「朝日の直刺す国、夕日の日照る国」みたいな素敵な言葉が神話の中だけに埋もれているのがもったいないと感じる次第である。
※1 この推測は『三国名勝図絵』で再説されているが、両書には微妙な違いがある。『麑藩名勝考』では加世田=笠沙ということで、「笠沙の御崎」が野間半島だとは限定していおらず、また推測として書いているのに対し、『三国…』の方になると野間半島のことを「笠砂御崎」と断定している。
※2 『三国名勝図絵』では、4ページ半に渡って「笠沙の御崎」=笠沙説を展開しているのだが、特に論証があるでもなく、「〜に違いない」式の記載が続く。一方で宮崎説についてはその内容を紹介せずに「辨ぜずして明」というのだから強気なものである。
※3 当時の信仰はアマテラス=太陽神を中心にした太陽信仰が濃厚なので、朝日夕日云々というのは、ただ景色がいいということではなくて、太陽祭祀に関係があるらしい。天孫降臨の地が出雲でなくて日向なのも、「日に向かう」ということと関係があるのかもしれない。でも神話というのは深読みするとキリがないので、素人はあまり深く考えない方がいいと思う。
【参考文献】
『古事記』1963年、倉野憲司 校注
『日本書紀 上(日本古典文學大系67)』1967年、坂本太郎、家永三郎、井上光貞、大野 晋 校注
『三国名勝図絵(第二七巻)』(復刻版)1982年、五代秀尭、橋口兼柄 編(青潮社版)
『麑藩名勝考(第一巻)』1795年、白尾国柱著
『笠沙町郷土誌(中巻)』1986年、笠沙町郷土誌編さん委員会
【アップデート】2012.12.5
『加世田再選史』についての記載を載せていたが、改めて調べてみると『三国名勝図絵』の方が古い資料だし、そもそも『麑藩名勝考』の方がもっと古かったのでこっちを参照することにした。また参考文献に『笠沙町郷土誌』を追加。
ということで、記紀神話について簡単に紹介する。これは天地ができてから神武天皇が誕生するまでを描いているが、大きく分けると次のような3部構成になっている。
第1部は高天原が舞台。イザナギとイザナミ夫婦が国産みを行い国土が完成、ところが火の神を産む時にイザナミは焼かれて死んだため、イザナギは黄泉の国までイザナミを追いかける。しかしその変わり果てた姿を見て退散。その禊ぎによってアマテラスやスサノオが誕生する。次がアマテラスとスサノオの姉弟ゲンカの話で、ケンカの結果スサノオは高天原から追放、落ちていったところが出雲である。
第2部はその出雲が舞台。高天原は「天界」なのでやや抽象的な話が多いが、出雲神話は地上の話なので具体性とストーリー性が強く、例えばスサノオのヤマタノオロチ退治、因幡の白ウサギなど人気の(?)神話が収録されている。スサノオの娘の旦那であるオオクニヌシの指導の下で国土が発展したのを見て、アマテラス一族はその国を譲ってもらおうと何度か使者を送り交渉した結果、結局オオクニヌシが国を譲ることを決定。
第3部はがらっと場面転換して日向(ひむか)、つまり九州が舞台。出雲を譲ってもらったはずのアマテラスだったが、孫のニニギをなぜか日向に派遣。ニニギは山の神の娘であるコノハナサクヤ姫と結ばれ、海幸彦と山幸彦の兄弟が誕生。山幸は海幸から借りた釣り針をなくしてしまい、海神の宮まで探しに行く。山幸はそこで海神の娘である豊玉姫と結ばれウガヤフキアエズが誕生、さらにその子どもがイワレヒコ=神武天皇であり、ここに記紀神話が終結する。なお、さらに記紀の物語は続くが、一応これ以降は神話ではなく歴史、ということになっている。
では、これからその日向神話について順を追って見てみよう。なお、内容は基本的に『古事記』に沿うが、適宜『日本書紀』を参照する。
アマテラスにより、なぜか日向の地に派遣されたニニギの一行だったが、彼らが降りて来たのが「高千穂のクシフル岳」というところで、(書記によると)さらにそこから「吾田の長屋の笠狭の碕」へ到達したという。この「阿田」が阿多のことで、「長屋」は加世田と大浦の境界である長屋山あたりといい、「笠狭の碕」(古事記では「笠沙の御崎」)が笠沙の野間半島だというわけだ。
このように、南さつま市の笠沙は天孫ニニギが初めてその居を構えたという記念すべき土地なのである。確かに、雄渾で荒々しい絶景が広がる笠沙は、我が国の黎明を飾るにふさわしい。
しかし、実はこの笠沙という地名はごく最近つけられたもので、古くからの地名ではない。大正時代までは現在の笠沙町と大浦町を合わせた地域は「西加世田村」と呼ばれており、大正12年にこれが「笠砂村」と改称、昭和15年に「笠沙町」となった経緯がある。笠砂村と改称したのは、「加世田村」「東加世田村」もあって紛らわしいということと自治意識を高めるのが目的だったらしく、古事記に因んで「笠砂」と名付けたらしい。つまり、今の笠沙町一帯が元から笠沙と呼ばれていたのではないのである。
ではデタラメでつけた名前かというとそうでもなく、江戸末期(1843年)に編纂された『三国名勝図絵』では、野間半島は「笠砂御崎」と記載されており、野間岳は昔「笠砂嶽」と呼ばれていたとされている。さらに遡る1795年に編まれた『麑藩名勝考』でも加世田は「笠狭之崎」であり、加世田は笠狭に田をつけたものとし、要は加世田という地名は笠沙が訛ったものだと推測されている(※1)。ともかく、「笠沙の御崎」が南薩にあったという主張はかなり古いのである。
また、南薩のこのあたりは神代の伝説やそれを祭る神社が多いのは事実で、阿多として栄えた古代に加世田一帯が笠沙という地名であったとしてもおかしくはないようだ。ただ、直接の証拠はないのに、『三国名勝図絵』ではあまりに自信満々に「笠沙の御崎」が現在の笠沙と同地であるという主張をしていて、客観性が足りないようにも見える。当時から「笠沙の御崎」は宮崎にあるという主張もあったが、同書ではこれを「無稽の妄説なり、詳に辨ぜずして明なり」と一蹴し、薩摩ナショナリズムを全開にしている(※2)。
それはさておき神話の方に戻ると、笠沙に到着したニニギは「ここは朝日の直刺(たださ)す国、夕日の日照(ほで)る国」だから、ここはとてもよい所だ、と言った。このフレーズはとても素敵で、普通いい国というのは農業・経済が盛んで地力があるところだと思うのだが、景色がいいからよい所だ、というのはなんともロマンチックだ。もともとアマテラスは、オオクニヌシが治めていた「豊葦原の水穂の国」という豊穣な国を譲ってもらいたかったわけだが、ニニギは朝日と夕日が美しいと喜んでいるのだから結構呑気な神である。
また「朝日の直刺す国、夕日の日照る国」というのは、笠沙の実態とも合致する。朝日の方は見たことはないが、東シナ海に沈む笠沙の夕日はとても美しい。まあこれは日本海側の多くの地域が該当するとは思うが。それから、「豊葦原の水穂の国」という美称と比べると、「褒めるのが風景しかなかったのかなあ」という気もしなくはないが(※3)、ロマンチックな言葉なので観光のPRにも使えると思う。
ちなみに、「笠沙の御崎」の位置については、北九州だという説もある。しかし、神話はそれ自体本当にあったことかどうかわからないわけで、どこかに確定できるものではないのは当然だし、いろいろ書いたが私としては別にどこでもいい。それより、「朝日の直刺す国、夕日の日照る国」みたいな素敵な言葉が神話の中だけに埋もれているのがもったいないと感じる次第である。
※1 この推測は『三国名勝図絵』で再説されているが、両書には微妙な違いがある。『麑藩名勝考』では加世田=笠沙ということで、「笠沙の御崎」が野間半島だとは限定していおらず、また推測として書いているのに対し、『三国…』の方になると野間半島のことを「笠砂御崎」と断定している。
※2 『三国名勝図絵』では、4ページ半に渡って「笠沙の御崎」=笠沙説を展開しているのだが、特に論証があるでもなく、「〜に違いない」式の記載が続く。一方で宮崎説についてはその内容を紹介せずに「辨ぜずして明」というのだから強気なものである。
※3 当時の信仰はアマテラス=太陽神を中心にした太陽信仰が濃厚なので、朝日夕日云々というのは、ただ景色がいいということではなくて、太陽祭祀に関係があるらしい。天孫降臨の地が出雲でなくて日向なのも、「日に向かう」ということと関係があるのかもしれない。でも神話というのは深読みするとキリがないので、素人はあまり深く考えない方がいいと思う。
【参考文献】
『古事記』1963年、倉野憲司 校注
『日本書紀 上(日本古典文學大系67)』1967年、坂本太郎、家永三郎、井上光貞、大野 晋 校注
『三国名勝図絵(第二七巻)』(復刻版)1982年、五代秀尭、橋口兼柄 編(青潮社版)
『麑藩名勝考(第一巻)』1795年、白尾国柱著
『笠沙町郷土誌(中巻)』1986年、笠沙町郷土誌編さん委員会
【アップデート】2012.12.5
『加世田再選史』についての記載を載せていたが、改めて調べてみると『三国名勝図絵』の方が古い資料だし、そもそも『麑藩名勝考』の方がもっと古かったのでこっちを参照することにした。また参考文献に『笠沙町郷土誌』を追加。
販売サイトを構築中…。
このところ、農産物販売のためのWEBサイトを作っているため、なんだか百姓ではなくて引きこもりみたいにPCに向かっている。
本当は夏にオープンさせるつもりだったが、いざ実際にやってみると私のWEBサイト構築の知識が古く、基本をちゃんと学ばないといけないことに気づいて構築が延び延びになっていた。
例えば、HTMLについては多少知っているつもりだったが、現在のWEBサイト構築ではHTMLで作ったコンテンツをCSSという仕組みで画面上にレイアウトする。このCSSについては、私は全く触れたことがなかったので一からの勉強しなくてはならず、なんとなく後回しにしてきた。しかし要点がわかってみると、以前のHTML一本のレイアウトに比べて随分と合理的で、実は簡単な気がしてきた。
もちろん基本的には面倒な作業の連続なので、正直、多くの農家にとってはこういう面倒な作業をしてまでインターネットで個人販売をするのは難しい。直売所などのリアルな販売の方が発送や入金確認などの手間もないし、合理的だろう。
しかし、そうなるとどうしても既存の客への販売という面が強くなる。私が主力の一つにしたいと思っているカンキツ系は皮を剝くのが面倒なためか若年層への人気がなく、消費が高齢の固定客に偏りつつある。つまり、将来の展開を考えると既存の客への販売だけには頼れないわけで、インターネットなどを通じて新規顧客の開拓を頑張る必要があるだろう。
私としては、あまりカンキツ系を食べない(と思われる)若い女性の客層を開拓したいと思っており、家内の協力も得て女性に受け入れられるデザインのサイトを作りたい。もちろんWEBサイトなどは作ってもほとんど見向きもされないものなので、今年は作り損だと思うが、いつ作ってもそれは変わらないから早めに作るに越したことはない。
また、もう一つ考えているのは、例えば「○○農園.com」みたいに自分の作った農産物だけを販売するのではなくて、地域の美味しいものを販売するような広がりも作れたらと思っている。先述のように個々の農家がインターネットでの販売に取り組むのは難しいので、もしインターネットで売りたいという人が周りにいれば、そういう人も利用できるようなWEBサイトにできたらいいなと思う。
本当は夏にオープンさせるつもりだったが、いざ実際にやってみると私のWEBサイト構築の知識が古く、基本をちゃんと学ばないといけないことに気づいて構築が延び延びになっていた。
例えば、HTMLについては多少知っているつもりだったが、現在のWEBサイト構築ではHTMLで作ったコンテンツをCSSという仕組みで画面上にレイアウトする。このCSSについては、私は全く触れたことがなかったので一からの勉強しなくてはならず、なんとなく後回しにしてきた。しかし要点がわかってみると、以前のHTML一本のレイアウトに比べて随分と合理的で、実は簡単な気がしてきた。
もちろん基本的には面倒な作業の連続なので、正直、多くの農家にとってはこういう面倒な作業をしてまでインターネットで個人販売をするのは難しい。直売所などのリアルな販売の方が発送や入金確認などの手間もないし、合理的だろう。
しかし、そうなるとどうしても既存の客への販売という面が強くなる。私が主力の一つにしたいと思っているカンキツ系は皮を剝くのが面倒なためか若年層への人気がなく、消費が高齢の固定客に偏りつつある。つまり、将来の展開を考えると既存の客への販売だけには頼れないわけで、インターネットなどを通じて新規顧客の開拓を頑張る必要があるだろう。
私としては、あまりカンキツ系を食べない(と思われる)若い女性の客層を開拓したいと思っており、家内の協力も得て女性に受け入れられるデザインのサイトを作りたい。もちろんWEBサイトなどは作ってもほとんど見向きもされないものなので、今年は作り損だと思うが、いつ作ってもそれは変わらないから早めに作るに越したことはない。
また、もう一つ考えているのは、例えば「○○農園.com」みたいに自分の作った農産物だけを販売するのではなくて、地域の美味しいものを販売するような広がりも作れたらと思っている。先述のように個々の農家がインターネットでの販売に取り組むのは難しいので、もしインターネットで売りたいという人が周りにいれば、そういう人も利用できるようなWEBサイトにできたらいいなと思う。
2012年12月1日土曜日
阿多という地名——南薩と神話(1)
古事記編纂1300年の今年も残り僅かとなってきたので、この機会に神話における南薩について思うところを数回書いてみたい。
さて、南さつま市の金峰町に、阿多という地名がある。
実はこの阿多という地名は、神話的古代に遡る来歴を持つ。阿多は今では狭い地域となっているが、古代には万之瀬川流域を中心とした薩摩半島西南部は広く阿多と呼ばれた。今で言う、南さつま市全体と日置市吹上町を合わせたところを阿多と言ったらしい。
金峰町は以前から「神話のふるさと」を自称してきたが、事実この「阿多」は古事記・日本書紀の記紀神話において重要な位置を占めている。具体的には、天孫ニニギが降臨し山の神の娘であるコノハナサクヤ姫と結ばれるのが阿多の笠沙であり(※1)、その他にも阿多に関する多くの記載が記紀にはある。
どうも、大和政権というのは、天皇家一族と出雲の勢力、そして阿多を中心とする隼人勢力の連立政権だったようで(※2)、そのために阿多の神話が記紀に多く取り入れられているようである。ちなみに、そのころ「薩摩」という地名はメジャーではなく、記紀には薩摩隼人は登場しないが、「阿多隼人」と「大隅隼人」というのが対置されて登場する。
例えば、日本書紀には、阿多隼人と大隅隼人が天覧相撲をして大隅隼人が勝った、という記述がある(※3)。これは史書における相撲の最初の記述であり、相撲の起源の一つは南九州にあるのである。今でも鹿児島では神事としての相撲がとても盛んで、夏祭りでは綱引きと相撲がよく行われるし、金峰町の錫山相撲などは350年以上の歴史がある。
この阿多隼人と大隅隼人は、おそらくは天皇一族との連立政権を組むため(※4)、古代に畿内へ大量移住しており、今でも畿内には鹿児島に因む地名がある。例えば、奈良県五條市の阿陀(あだ)は阿多に起源を持つと言い、京都府京田辺市の大住(おおすみ)では大住隼人舞という芸能も行われている(近年復活させたもの)。
畿内隼人は律令制の中で「隼人司(はやとのつかさ)」という機関に所属せられ、歌舞などの芸能や竹製品の製造を担当した。また、天皇一族の護衛(近習隼人)や御陵の警護、そして殯(もがり)の儀礼にも参加させられたという。これらは隼人の持つ呪能を期待したものだったらしい。どうやら、古代において隼人というのは、神秘的な力を持つ民族と捉えられていたようだ。
このように大和朝廷において重要な働きをしたらしい隼人だが、大和朝廷が氏族支配の体制から律令制(法治国家)に移行するにつれ利害が対立し、702年、713年、720年に朝廷への反乱を起こす(隼人の乱)。ちなみに最後の反乱で朝廷から派遣された将軍が、歌人として著名な大伴旅人である。旅人によりこの反乱は鎮圧され、以後隼人は不遇の時代を迎えることとなる。2回目の反乱の後には、6年に1度の朝貢も求められている(六年一替の制)。これは江戸時代の参勤交代制度に似ているが、定期的な朝貢を求められたのは全国でも隼人しかいないのである。
この他にも、阿多隼人の記事は『古事記』や『日本書紀』に散見される。そして『続日本紀』(797年成立)くらいまではかなりの存在感がある阿多隼人だが、続く『万葉集』になると、阿多という地名は全く出てこないし、「隼人」という言葉も半ば思い出の中に表現されるだけである。 どうもこれは、阿多隼人の場合、中心勢力が畿内に移住してしまったために、地元の政治的重要性が低下していったということもあるようだ。
こうして、神話的古代に栄えた阿多は、阿多郡→阿多郷→阿多村とどんどんその領域を縮小していき、今では金峰町の一地名として残っているだけである。寂しいとも言えるが、古代から引き継がれた地名が交差点の名称として普通に使われているのは面白い。地元でも特段アピールされないけれど、阿多という地名は、鹿児島にとっての記紀神話への入り口なのである。
※1 「この「阿多」は鹿児島の阿多ではなくて、宮崎県の吾田(あがた)だ!」 とする主張もある。宮崎県は、神話の舞台が鹿児島ではなく宮崎にあったとする主張を頑張っていて、これはまた機会があったら書きたいが理由のないことではない。延岡市には笠沙の御崎もある。神話の本拠地の競争をするのではなく、姉妹都市になったら面白いと思う。
※2 「隼人は天皇家に服属させられた民族」というのが従来の常識だったが、最近こういう考え方になりつつある。
※3 『日本書紀』天武天皇11年の条。
※4 これは(※2)と関連するが、従来は天皇家への服属のため強制移住させられたと考えられていた。しかし江戸時代の外様大名のように敵対勢力は遠ざける方が合理的であることを考えると、この移住は自主的なものであったと考えた方がよい、ということになりつつある。
【参考文献】
『熊襲と隼人』1978年、井上辰雄
『隼人の古代史』2001年、中村明蔵
さて、南さつま市の金峰町に、阿多という地名がある。
実はこの阿多という地名は、神話的古代に遡る来歴を持つ。阿多は今では狭い地域となっているが、古代には万之瀬川流域を中心とした薩摩半島西南部は広く阿多と呼ばれた。今で言う、南さつま市全体と日置市吹上町を合わせたところを阿多と言ったらしい。
金峰町は以前から「神話のふるさと」を自称してきたが、事実この「阿多」は古事記・日本書紀の記紀神話において重要な位置を占めている。具体的には、天孫ニニギが降臨し山の神の娘であるコノハナサクヤ姫と結ばれるのが阿多の笠沙であり(※1)、その他にも阿多に関する多くの記載が記紀にはある。
どうも、大和政権というのは、天皇家一族と出雲の勢力、そして阿多を中心とする隼人勢力の連立政権だったようで(※2)、そのために阿多の神話が記紀に多く取り入れられているようである。ちなみに、そのころ「薩摩」という地名はメジャーではなく、記紀には薩摩隼人は登場しないが、「阿多隼人」と「大隅隼人」というのが対置されて登場する。
例えば、日本書紀には、阿多隼人と大隅隼人が天覧相撲をして大隅隼人が勝った、という記述がある(※3)。これは史書における相撲の最初の記述であり、相撲の起源の一つは南九州にあるのである。今でも鹿児島では神事としての相撲がとても盛んで、夏祭りでは綱引きと相撲がよく行われるし、金峰町の錫山相撲などは350年以上の歴史がある。
この阿多隼人と大隅隼人は、おそらくは天皇一族との連立政権を組むため(※4)、古代に畿内へ大量移住しており、今でも畿内には鹿児島に因む地名がある。例えば、奈良県五條市の阿陀(あだ)は阿多に起源を持つと言い、京都府京田辺市の大住(おおすみ)では大住隼人舞という芸能も行われている(近年復活させたもの)。
畿内隼人は律令制の中で「隼人司(はやとのつかさ)」という機関に所属せられ、歌舞などの芸能や竹製品の製造を担当した。また、天皇一族の護衛(近習隼人)や御陵の警護、そして殯(もがり)の儀礼にも参加させられたという。これらは隼人の持つ呪能を期待したものだったらしい。どうやら、古代において隼人というのは、神秘的な力を持つ民族と捉えられていたようだ。
このように大和朝廷において重要な働きをしたらしい隼人だが、大和朝廷が氏族支配の体制から律令制(法治国家)に移行するにつれ利害が対立し、702年、713年、720年に朝廷への反乱を起こす(隼人の乱)。ちなみに最後の反乱で朝廷から派遣された将軍が、歌人として著名な大伴旅人である。旅人によりこの反乱は鎮圧され、以後隼人は不遇の時代を迎えることとなる。2回目の反乱の後には、6年に1度の朝貢も求められている(六年一替の制)。これは江戸時代の参勤交代制度に似ているが、定期的な朝貢を求められたのは全国でも隼人しかいないのである。
この他にも、阿多隼人の記事は『古事記』や『日本書紀』に散見される。そして『続日本紀』(797年成立)くらいまではかなりの存在感がある阿多隼人だが、続く『万葉集』になると、阿多という地名は全く出てこないし、「隼人」という言葉も半ば思い出の中に表現されるだけである。 どうもこれは、阿多隼人の場合、中心勢力が畿内に移住してしまったために、地元の政治的重要性が低下していったということもあるようだ。
こうして、神話的古代に栄えた阿多は、阿多郡→阿多郷→阿多村とどんどんその領域を縮小していき、今では金峰町の一地名として残っているだけである。寂しいとも言えるが、古代から引き継がれた地名が交差点の名称として普通に使われているのは面白い。地元でも特段アピールされないけれど、阿多という地名は、鹿児島にとっての記紀神話への入り口なのである。
※1 「この「阿多」は鹿児島の阿多ではなくて、宮崎県の吾田(あがた)だ!」 とする主張もある。宮崎県は、神話の舞台が鹿児島ではなく宮崎にあったとする主張を頑張っていて、これはまた機会があったら書きたいが理由のないことではない。延岡市には笠沙の御崎もある。神話の本拠地の競争をするのではなく、姉妹都市になったら面白いと思う。
※2 「隼人は天皇家に服属させられた民族」というのが従来の常識だったが、最近こういう考え方になりつつある。
※3 『日本書紀』天武天皇11年の条。
※4 これは(※2)と関連するが、従来は天皇家への服属のため強制移住させられたと考えられていた。しかし江戸時代の外様大名のように敵対勢力は遠ざける方が合理的であることを考えると、この移住は自主的なものであったと考えた方がよい、ということになりつつある。
【参考文献】
『熊襲と隼人』1978年、井上辰雄
『隼人の古代史』2001年、中村明蔵
2012年11月26日月曜日
南さつま市定住化促進委員会:市長に報告書を提出
南さつま市定住化促進検討委員会が、報告書をまとめて本坊市長に手渡し、終了した。
本坊市長からは「単に南さつま市が人口減少で困っているから来て下さいと言っても、それで来る人はいない。「こんな暮らしをしたい」とか、人それぞれ叶えたい夢があるわけだから、 その夢を応援できるように取り組んでいきたい」というような趣旨の抱負もいただいた。
報告書の内容は、委員の意見を最大限取り入れる形になっており、こういう委員会にありがちな「役所の作った下案をオーソライズするだけ」という形骸化したものにならずによかった。正直、自分としてもここまで意見が取り入れられるとは思っていなかったので、ちょっと見直した部分がある。
報告書の内容だが、要約すると次のような感じである。
そして私個人としては、このような委員会に参画する機会を与えてもらったことを感謝したいし、ここで得た縁を、別の面でも生かせていけたらと思う。関係者のみなさん、ありがとうございました。
【参考リンク】
南さつま市定住化促進委員会(第1回)
南さつま市定住化促進委員会(第2回)
南さつま市定住化促進委員会(第3回)
南さつま市定住化促進委員会(第4回)
本坊市長からは「単に南さつま市が人口減少で困っているから来て下さいと言っても、それで来る人はいない。「こんな暮らしをしたい」とか、人それぞれ叶えたい夢があるわけだから、 その夢を応援できるように取り組んでいきたい」というような趣旨の抱負もいただいた。
報告書の内容は、委員の意見を最大限取り入れる形になっており、こういう委員会にありがちな「役所の作った下案をオーソライズするだけ」という形骸化したものにならずによかった。正直、自分としてもここまで意見が取り入れられるとは思っていなかったので、ちょっと見直した部分がある。
報告書の内容だが、要約すると次のような感じである。
- キャッチコピーは『あなたの「夢」応援します』
- 「あなたの移住“とことん”応援事業」として、総合窓口と「移住・定住促進コンシェルジュ」の設置、各地域で専門性や人脈を持つ人を「地域コンシェルジュ」に任命。移住者等へのケア体制を充実させる。
- 「あなたの起業”とことん”応援事業」として、移住者のみならず現在の住民も対象に含めて資金・情報面などで起業家を応援。
- 移住定住のための広報を強化。
- その他、推進施策として既存施策も含めていろいろ推進。例えば、住宅所得補助金やアパートの家賃助成、空き屋バンク制度の活性化のための「片付け補助金」の創設など。
そして私個人としては、このような委員会に参画する機会を与えてもらったことを感謝したいし、ここで得た縁を、別の面でも生かせていけたらと思う。関係者のみなさん、ありがとうございました。
【参考リンク】
南さつま市定住化促進委員会(第1回)
南さつま市定住化促進委員会(第2回)
南さつま市定住化促進委員会(第3回)
南さつま市定住化促進委員会(第4回)
2012年11月24日土曜日
果樹の有機栽培を(理屈はともかく)実践的に述べた本
来期から果樹生産を有機栽培に切り替えたいなあ、と思って『有機栽培の果樹・茶つくり』(小祝 政明 著)でお勉強。
著者の主張は単純で、農薬を使わずに病害虫を防除するためには植物体自体を充実させなくてはダメで、そのためにはミネラルと有機のチッソが重要だ、という。
ミネラルは植物の生育に必須なものであるにも関わらず、意識して投与しないと不足がちになるのでわかるが、「有機のチッソ」というのはなんだかよくわからない。要はアミノ酸のことらしいが、著者曰く「有機のチッソはそのまま細胞づくりに使えるので、光合成でつくられた炭水化物の消費が少なく、糖度を高めることができる」(p.31)とのこと。
植物は無機物の窒素(硝酸とか、アンモニウムとか)だけを吸収すると思われているが、実は有機物の窒素(アミノ酸の一部として存在する窒素)も少量ながら吸収するようだ、と最近言われ始めた。じゃあどのくらい有機物の窒素を吸収するのか、というのは手元に資料がないが、多分無機物の窒素吸収率とオーダー(桁)が一つ違うと思う。
つまり、植物がアミノ酸を吸収できないとは言わないが、アミノ酸では直接は肥料にならないのではなかろうか。そのあたりの疑問に対しては本書は何も答えない。実際にそれでうまくいっているのだから理屈にはこだわらない、ということだと思う。
ところで、有機栽培の本にしては珍しく、本書にはほとんど土壌微生物の話が出てこない。有機栽培の要諦は土作りだと思うが、そのための土壌微生物の活発化・安定化が触れられないというのは奇異である。というか、有機の窒素=アミノ酸肥料を投与すると、これを直接的に栄養にするのは土壌微生物なわけだから、著者が「そのまま細胞づくりに使える」という「有機のチッソ」こそ土壌微生物の活発化の話なのではないか。
しかも、本書では「施肥は早めにやった方がいい。春肥は降雪前に」と述べるのだが、これは、アミノ酸を土壌微生物が分解して窒素を無機態にするために時間がかかるからだと解釈できる。 本書では早めの施肥の理由を「肥料分が土壌に浸透するのに時間がかかるから」と解説しているが、微生物の働きを考えた方が合理的だ。
ちなみに、著者は農家や学者ではなくてジャパンバイオファームという農業資材屋さんであり、本書には自社資材の普及の意図もあるのかもしれないが、そういう広告めいた記載は全くなく、基本的には信頼できる。その理屈の部分では疑問符がつくようなところもあるが、果樹の有機栽培について実践的に述べた本は少ないので、貴重な本ではある。ぜひ来期のポンカン栽培に生かしたい。本書でも「中晩柑類の有機栽培はこれから非常に面白い局面を迎えるのではないか」(p.190)とあって勇気づけられた。
著者の主張は単純で、農薬を使わずに病害虫を防除するためには植物体自体を充実させなくてはダメで、そのためにはミネラルと有機のチッソが重要だ、という。
ミネラルは植物の生育に必須なものであるにも関わらず、意識して投与しないと不足がちになるのでわかるが、「有機のチッソ」というのはなんだかよくわからない。要はアミノ酸のことらしいが、著者曰く「有機のチッソはそのまま細胞づくりに使えるので、光合成でつくられた炭水化物の消費が少なく、糖度を高めることができる」(p.31)とのこと。
植物は無機物の窒素(硝酸とか、アンモニウムとか)だけを吸収すると思われているが、実は有機物の窒素(アミノ酸の一部として存在する窒素)も少量ながら吸収するようだ、と最近言われ始めた。じゃあどのくらい有機物の窒素を吸収するのか、というのは手元に資料がないが、多分無機物の窒素吸収率とオーダー(桁)が一つ違うと思う。
つまり、植物がアミノ酸を吸収できないとは言わないが、アミノ酸では直接は肥料にならないのではなかろうか。そのあたりの疑問に対しては本書は何も答えない。実際にそれでうまくいっているのだから理屈にはこだわらない、ということだと思う。
ところで、有機栽培の本にしては珍しく、本書にはほとんど土壌微生物の話が出てこない。有機栽培の要諦は土作りだと思うが、そのための土壌微生物の活発化・安定化が触れられないというのは奇異である。というか、有機の窒素=アミノ酸肥料を投与すると、これを直接的に栄養にするのは土壌微生物なわけだから、著者が「そのまま細胞づくりに使える」という「有機のチッソ」こそ土壌微生物の活発化の話なのではないか。
しかも、本書では「施肥は早めにやった方がいい。春肥は降雪前に」と述べるのだが、これは、アミノ酸を土壌微生物が分解して窒素を無機態にするために時間がかかるからだと解釈できる。 本書では早めの施肥の理由を「肥料分が土壌に浸透するのに時間がかかるから」と解説しているが、微生物の働きを考えた方が合理的だ。
ちなみに、著者は農家や学者ではなくてジャパンバイオファームという農業資材屋さんであり、本書には自社資材の普及の意図もあるのかもしれないが、そういう広告めいた記載は全くなく、基本的には信頼できる。その理屈の部分では疑問符がつくようなところもあるが、果樹の有機栽培について実践的に述べた本は少ないので、貴重な本ではある。ぜひ来期のポンカン栽培に生かしたい。本書でも「中晩柑類の有機栽培はこれから非常に面白い局面を迎えるのではないか」(p.190)とあって勇気づけられた。
2012年11月21日水曜日
農業にとってのTPP
日本全国の農村がそうだと思うが、うちの周りにも「TPP参加断固阻止!」のノボリや看板がよく立っている。
衆院選の争点の一つでもあり、農業者以外の関心も高いと思われるが、どうもその議論は感情的なものが多いように思われる。そこで、国際貿易に関してはズブの素人であるが、農業分野に限ってTPPについて自分の見解をまとめておきたい。
まず、最初に断っておくが、私は農業分野に関してはどちらかと言えばTPP推進派である。理由は、東大の本間正義教授が推進派だからだ。自分の頭で考えろと言われるかもしれないが、国際貿易というのは経済学の中でも非常に込み入っていて、素人が少し調べたくらいで実態がわかるものではない。私は官僚時代に日・EU科学技術協力協定の締結にちょっとだけ関わったが、ことに国際貿易の協定というものは複雑なもので「分かった気」になるのは逆に危険である。
そのため、素人としては、信頼できる(あるいは立場が近い)専門家の見解を信じるしかない、と思う。本間先生は農業経済学の重鎮で若いころから国際貿易の研究に取り組み、国際交渉の現場もよくご存じであるし、途上国等の関税アドバイザー的なこともやっていた(と思う。記憶が違っていたらすいません)。 自由貿易論者ではあるけれど、適切な関税で自国産業を保護することの重要性も強調するので、バランスも取れている。
というわけで、本間先生の見解をベースに、農業分野におけるTPPの意味をまとめてみる。
また、本間先生は「TPP参加は農政改革とセットに行う必要があり、もし農政改革なしにTPPに参加したら農業は大打撃を受けるだろう」と言っているが、TPPに参加しなくても農家の自然減が想定される以上、減少分を補うために大規模農家への優遇政策が取られる必要がある。規模拡大を図りたい農家にとってみれば、TPPに参加すれば零細米耕作農家が早めに淘汰されるのでチャンスとも言える。
ところでTPPだけに限らないが、高齢化・少子化によって基本的に日本の将来というのは暗いので、「TPPに参加して経済成長!」とかはあまり真に受けない方がいい。来るべき衆院選も、有権者はどちらに明るい将来がありそうかで選んではいけない。日本の未来は暗鬱としたものであることを前提にして、より傷口が浅い方を選ぶという非常に後ろ向きな考えをする必要があると思う。
とはいいうものの、TPP参加の方がより傷口が浅いのかどうかは、実はよくわからない。今回は米だけにフォーカスしたが、畜産についても検討しなくてはならないし、そもそも農業分野はTPPのほんの一部で、投資や知的財産など20の分野を含む(※)。金額的な影響としては金融などの方が農業より圧倒的に大きいと思われるので、分野ごとに細かい検証が必要だ。非関税障壁の扱いについても考慮しなくてはならない。冒頭に述べたように国際貿易というのは非常に難しいのだが、こうした複雑さを捨象し、「TPPに乗り遅れると大変なことになる!」とか「TPP参加で国が滅びる!」のような極端な主張ばかりが目立つのが気になる。
もちろんTPPの現実の意味は、その間のグレーな部分にある。まずは交渉参加してどのくらいグレーなのかを探るのがいいのではないだろうか。私としては強い推進の気持ちはないので、どちらに転んでもいいと思うが、TPP問題で冷静な議論が行われ、我が国の産業の未来を考える機会になるとよいと思っている。
※ 24の作業部会があり、うち4つは「首席交渉官会議」「紛争解決」「協力」「横断的事項特別部会」なのでこれを外すと20になる。
【参考】
本間正義教授が日本記者クラブで行った講演。
衆院選の争点の一つでもあり、農業者以外の関心も高いと思われるが、どうもその議論は感情的なものが多いように思われる。そこで、国際貿易に関してはズブの素人であるが、農業分野に限ってTPPについて自分の見解をまとめておきたい。
まず、最初に断っておくが、私は農業分野に関してはどちらかと言えばTPP推進派である。理由は、東大の本間正義教授が推進派だからだ。自分の頭で考えろと言われるかもしれないが、国際貿易というのは経済学の中でも非常に込み入っていて、素人が少し調べたくらいで実態がわかるものではない。私は官僚時代に日・EU科学技術協力協定の締結にちょっとだけ関わったが、ことに国際貿易の協定というものは複雑なもので「分かった気」になるのは逆に危険である。
そのため、素人としては、信頼できる(あるいは立場が近い)専門家の見解を信じるしかない、と思う。本間先生は農業経済学の重鎮で若いころから国際貿易の研究に取り組み、国際交渉の現場もよくご存じであるし、途上国等の関税アドバイザー的なこともやっていた(と思う。記憶が違っていたらすいません)。 自由貿易論者ではあるけれど、適切な関税で自国産業を保護することの重要性も強調するので、バランスも取れている。
というわけで、本間先生の見解をベースに、農業分野におけるTPPの意味をまとめてみる。
- 既に米、麦、食肉、乳製品以外の農産物の関税は低いか実質無税なので影響はない。
- 例外品目の中で影響が大きいのが米。関税撤廃は段階的にすることが可能だが、猶予は10年なのでその間に米耕作の産業構造を変革する必要がある。農水省は9割が壊滅するという試算をしているが、それは大げさにしても零細兼業農家を中心に2/3くらいが廃業し、大規模耕作者(15ha以上)に集約される可能性がある。狭小な農地については耕作放棄地も増える。
- 一方農産物の輸出については、TPPによって大幅に増加することはないが、共通のルールで公正な競争ができれば、伸びるところもある。懸念される自給率低下については、そもそも自給率という指標自体にあまり意味がない。
- TPPがなくても近い将来日本の米農業は変わって行かざるを得ない以上、TPPに参加して早いうちに米農業の構造改革を進めた方がよい。TPPに参加するメリットは必ずしも大きくないが、旧来型の構造を温存し続けるリスクの方が大きい。
また、本間先生は「TPP参加は農政改革とセットに行う必要があり、もし農政改革なしにTPPに参加したら農業は大打撃を受けるだろう」と言っているが、TPPに参加しなくても農家の自然減が想定される以上、減少分を補うために大規模農家への優遇政策が取られる必要がある。規模拡大を図りたい農家にとってみれば、TPPに参加すれば零細米耕作農家が早めに淘汰されるのでチャンスとも言える。
ところでTPPだけに限らないが、高齢化・少子化によって基本的に日本の将来というのは暗いので、「TPPに参加して経済成長!」とかはあまり真に受けない方がいい。来るべき衆院選も、有権者はどちらに明るい将来がありそうかで選んではいけない。日本の未来は暗鬱としたものであることを前提にして、より傷口が浅い方を選ぶという非常に後ろ向きな考えをする必要があると思う。
とはいいうものの、TPP参加の方がより傷口が浅いのかどうかは、実はよくわからない。今回は米だけにフォーカスしたが、畜産についても検討しなくてはならないし、そもそも農業分野はTPPのほんの一部で、投資や知的財産など20の分野を含む(※)。金額的な影響としては金融などの方が農業より圧倒的に大きいと思われるので、分野ごとに細かい検証が必要だ。非関税障壁の扱いについても考慮しなくてはならない。冒頭に述べたように国際貿易というのは非常に難しいのだが、こうした複雑さを捨象し、「TPPに乗り遅れると大変なことになる!」とか「TPP参加で国が滅びる!」のような極端な主張ばかりが目立つのが気になる。
もちろんTPPの現実の意味は、その間のグレーな部分にある。まずは交渉参加してどのくらいグレーなのかを探るのがいいのではないだろうか。私としては強い推進の気持ちはないので、どちらに転んでもいいと思うが、TPP問題で冷静な議論が行われ、我が国の産業の未来を考える機会になるとよいと思っている。
※ 24の作業部会があり、うち4つは「首席交渉官会議」「紛争解決」「協力」「横断的事項特別部会」なのでこれを外すと20になる。
【参考】
本間正義教授が日本記者クラブで行った講演。
2012年11月18日日曜日
質素だが誠実な展示「南さつま神話の旅」
南さつま市金峰町にある歴史交流館 金峰で「南さつま神話の旅」という企画展が開催中である。
企画展自体は、十数枚程度の手作りポスターパネルと、いくばくかの土器が並べられているだけの質素な展示である。正直なところ、これを見て「面白い!」という人は少数派だろう。だが、その内容は意外によくまとまっていて、普段体系的に示されることのない南さつま市の神話の旧跡が外観でき、勉強になる。お金もかかっていないし、派手さもないが、誠実に作られた企画展である。
特にその誠実さを感じるのが冒頭の説明。要約すると、
日本神話が戦争の遂行に利用されたことはよく知られているが、残された史蹟が「昭和の遺産」であるとまで述べられることは少ない。多分「神代聖蹟」がそういう陰影を持つものだということを認識している人も少ないだろう。
今年は古事記編纂1300年に当たるということで、特に島根県(出雲地方)と宮崎県が観光キャンペーンに力を入れていた。この2県は首都圏の電車に車内広告を大量に打つなど、昨年来、多くの広告費用を投入して「神話のふるさと」のイメージ形成と観光促進を行った。これ自体は同じく神話のふるさとである鹿児島県も見習うべきところもあると思うが、観光という商業振興を重視するあまり、「我が県には神話にゆかりがある所がたくさんあって凄いでしょ!」というアピールだけになってしまったきらいもある。
だが実際には、先述のように日本神話は戦争に利用された負の歴史がある。島根県についてはよく知らないが、宮崎県では政府の皇紀2600年記念事業で宮崎神宮が大幅拡張されたり、日本海軍発祥の地碑(神武天皇御東遷時お舟出の地)を建立したりするなど、国威発揚の片棒を担いでいる(担がされている)。そういう歴史を反省することなしに、商業主義的に観光を推進しようというだけでは少し空疎な感じも受ける。
そういう意味では、本企画展では冒頭に誠実な説明があるだけでなく、個々のパネルの内容も割と醒めた態度で書かれていて、好感が持てた。歴史交流館の嘱託職員の方が企画・作成したらしいが、見識のある方とお見受けするので一度話を聞いてみたいものである。
ところで、商業主義的すぎるのも問題だが、鹿児島県のようにせっかくの神話資産を無視するのもいただけない。 8年後の2020年には日本書紀編纂1300年になるので、その時には鹿児島県もいろいろとやってはどうか。アピール競争をする必要はなく、他県とも連携しつつ、観光だけでなく歴史研究・教育なども振興するいい機会としてもらいたい。自分としても、南薩の神話について近々自分なりにまとめてみたいと思っている。
【参考】
古事記編纂1300年記念企画展 南さつま神話の旅
開催期間:2012年09月21日 ~ 2012年12月24日
場 所:南さつま市 歴史交流館金峰
料 金:高校生以上300円、小人150円
連絡先: TEL: 0993-58-4321
企画展自体は、十数枚程度の手作りポスターパネルと、いくばくかの土器が並べられているだけの質素な展示である。正直なところ、これを見て「面白い!」という人は少数派だろう。だが、その内容は意外によくまとまっていて、普段体系的に示されることのない南さつま市の神話の旧跡が外観でき、勉強になる。お金もかかっていないし、派手さもないが、誠実に作られた企画展である。
特にその誠実さを感じるのが冒頭の説明。要約すると、
- 南さつま市には鹿児島県が12カ所に作った「神代聖蹟」の9つまでが集中している。
- 「神代聖蹟」とは、皇紀2600年記念事業として作られたもので、日本神話の舞台となったところを指定する石碑。
- 皇紀2600年は戦争中の昭和15年。「神代聖蹟」は戦争遂行のための国威発揚に日本神話を利用したものであり、つまり「昭和の遺産」。
日本神話が戦争の遂行に利用されたことはよく知られているが、残された史蹟が「昭和の遺産」であるとまで述べられることは少ない。多分「神代聖蹟」がそういう陰影を持つものだということを認識している人も少ないだろう。
今年は古事記編纂1300年に当たるということで、特に島根県(出雲地方)と宮崎県が観光キャンペーンに力を入れていた。この2県は首都圏の電車に車内広告を大量に打つなど、昨年来、多くの広告費用を投入して「神話のふるさと」のイメージ形成と観光促進を行った。これ自体は同じく神話のふるさとである鹿児島県も見習うべきところもあると思うが、観光という商業振興を重視するあまり、「我が県には神話にゆかりがある所がたくさんあって凄いでしょ!」というアピールだけになってしまったきらいもある。
だが実際には、先述のように日本神話は戦争に利用された負の歴史がある。島根県についてはよく知らないが、宮崎県では政府の皇紀2600年記念事業で宮崎神宮が大幅拡張されたり、日本海軍発祥の地碑(神武天皇御東遷時お舟出の地)を建立したりするなど、国威発揚の片棒を担いでいる(担がされている)。そういう歴史を反省することなしに、商業主義的に観光を推進しようというだけでは少し空疎な感じも受ける。
そういう意味では、本企画展では冒頭に誠実な説明があるだけでなく、個々のパネルの内容も割と醒めた態度で書かれていて、好感が持てた。歴史交流館の嘱託職員の方が企画・作成したらしいが、見識のある方とお見受けするので一度話を聞いてみたいものである。
ところで、商業主義的すぎるのも問題だが、鹿児島県のようにせっかくの神話資産を無視するのもいただけない。 8年後の2020年には日本書紀編纂1300年になるので、その時には鹿児島県もいろいろとやってはどうか。アピール競争をする必要はなく、他県とも連携しつつ、観光だけでなく歴史研究・教育なども振興するいい機会としてもらいたい。自分としても、南薩の神話について近々自分なりにまとめてみたいと思っている。
【参考】
古事記編纂1300年記念企画展 南さつま神話の旅
開催期間:2012年09月21日 ~ 2012年12月24日
場 所:南さつま市 歴史交流館金峰
料 金:高校生以上300円、小人150円
連絡先: TEL: 0993-58-4321
2012年11月16日金曜日
二番煎じでも美しい。鹿児島県立農業大学校のキャンパス
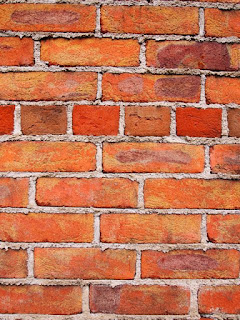 |
| とにかくレンガが美しい。積み方も凝っている。 |
研修はさておき、初めて入った農大のキャンパスがとてもおしゃれでびっくりした。ハンドメイド風の赤煉瓦と緑の屋根の色彩が美しく、鉄骨ではなく集成材を使った構造で内装にも木がふんだんに使われ高級感がある。コンクリートの柱はギリシャ風とすら見える重厚な作りで強度もある一方、細かい意匠も凝らされてデザイン全体の配慮が行き届いている。さらに夜になると間接照明を多用した瀟洒なライティングがなされ、まるで結婚式場のようである。
誰がこのキャンパスを設計したのかと思い、農大職員のご協力を得て調べてみると、施工者は鹿児島県建築設計監理事業共同組合だが、実際は日建設計が主導したようだ。日建設計といえば、最近だと東京スカイツリー、東京ミッドタウン、首相官邸、京都迎賓館など大規模プロジェクトを数多く手がけた我が国を代表する建築設計事務所。日建設計であれば、農大キャンパスのクオリティの異常な高さも納得である。
総工費は調べられなかったが、建築開始時の新聞によれば500億円程度とのこと。もちろん校舎だけでなく、造成、栽培施設・設備も含めてだから施設が何億円なのかはわからないが、レンガ一つとっても特別にヨーロッパ(多分イギリス)から取り寄せたものらしく金に糸目をつけていない雰囲気があり、民間施設とは比べものにならない価格なのは間違いない。緩やかにカーブするコリドー(回廊)、全棟切妻屋根、特注品の巨大ガラス(1m×7m程度)など、豪華な部分を挙げていけばきりがないほどだ。
ちなみに、驚くべきことに実はこのデザインは高知工科大学のキャンパスの二番煎じのようだ。高知工科大キャンパスは同じく日建設計が手がけ、これは公共建築賞特別賞等を受賞するなどすばらしい出来らしく、同校は「日本一美しいキャンパス」を自称している。どうもこれが農大の雛形になっているようで、レンガの取り寄せまで高知工科大と共通している。農大のランドマークともなっているドミトリー(学生寮)などは高知工科大ドミトリーと瓜二つで、日建設計が同時期に設計したとはいえ、ここまで似ていると手抜きじゃないかと思いたくなるほどだ。
ただ、屋根の色と形など細かいところで基本デザインにも当然違いはあり、また農大の方が低層(2階建て以上がない)で落ちついていて、土地もゆったり使っており景観との親和性も高いように思われる。ぜひ高知工科大も実見して比べてみたいところである。両校の学生が相互に訪問したら、そのキャンパスの相似に驚きつつも、細かい相違も気づいて面白いだろう。
キャンパスをいろいろ褒めたが、農大の職員もどこが設計したのか知らなかったくらいで、せっかくの素晴らしいキャンパスがあまり注目を浴びていないようなのは残念だ。日建設計が二番煎じの建物を作ったからなのかもしれないが、二番煎じであっても非常に素晴らしい建築なので誇るべき財産だ。もちろん、「農大にそんな贅沢なキャンパスはいらんだろう。税金の無駄遣いだ!」という感想も抱くが、まあ一次産業に将来をかけている鹿児島県の意気込みを表した建物だということにしておこう。
2012年11月10日土曜日
廃校利用のものすごく斬新なアイデア
先日、廃校になっている笠沙高校の敷地に入る機会があった。
県立笠沙高校は2006年に廃校になってもう6年以上経つが、跡地利用がなされないまま放置されているようでもったいない。
市でも「笠沙高校跡地対策協議会」なるものを設置して有効利用できないかと検討してきたようだが、意見がまとまらないまま宙ぶらりんになっていたようだ。先日所有者である県から「グラウンドをメガソーラー設置の用地にしたい」という打診があったということでこれを受諾。あわせて、校舎等については既に痛みが激しいということで、委員会では撤去して更地にするよう県に要望することとしたという。
有効活用の良案もないので県の打診を受けたのだろうが、グラウンドへのメガソーラー設置には惹かれない。アクセスのよい広い土地をメガソーラー用地などにするのはもったいないし、そもそもメガソーラーなんて補助金が切れれば一発で赤字になる事業だ。ゴミになったソーラーの山で埋まらないとよいが…。
さらに、建物が傷んでいるから取り壊す、とのことだが、これだけの施設であり取り壊しにもかなりの金がかかる。外観からしか判断できないが、修繕した方が安上がりなのでは? というのが率直な感想だ。もちろん更地にした後の利用のめどがあるならいいのだが。
そんな中、先輩農家Kさんが、ものすごく斬新な跡地利用のアイデアを世間話で言っていた。曰く「納骨堂にしてしまえばいい」とのこと。大浦・笠沙は高度経済成長期に人口が非常に流出した地域であるが、今後10年程度で流出した団塊世代が一挙に老後を迎えることを考えると墓・納骨堂は意外に供給不足である。
都会に墓を作る人もいるだろうが、墓くらいは故郷に…という人も多いだろう。その際、古くからの集落の共同墓地・共同納骨堂に入れられればいいが、子や孫が定期的に管理することができない場合、寺や墓地会社の永代供養の方が好ましい。荒唐無稽なアイデアに見えて、実は経営的にいけるのではないか。
さらに、もし大規模な納骨堂ができれば定期的に法事があるので地元経済も潤う。花卉類、食事はもちろん、僻地なので宿泊にもお金が落ちるだろう。もちろんテナント利用や企業誘致など、経済効果の高い利用法の方が望ましいのはいうまでもないが、この過疎地域に高望みはできないことを思えば、納骨堂は悪くない。それに、かつて若者が歓声を上げた学舎が納骨堂となるとなれば、高齢化時代の最先端ということで廃校利用の極北として注目も集めそうである。
全国的にも、今後10年程度で団塊世代がどんどん鬼籍に入る時代が来る。つまりその前に、墓地需要は日本史上空前絶後の高まりを見せるのが明白である。今後20年くらいは、夥しい人間が死ぬ時代、そのために心のよりどころを求める宗教の時代になると思う。私がシキミに注目したのも、そういう背景がある。廃校利用の納骨堂はともかくとして、葬儀ビジネスは有望だと思うので、地方活性化の一つの方策になるかもしれない。実際に、静岡県新居町では商工会で葬儀ビジネスに取り組んで成功しているという。葬儀ビジネスというとなんだかアコギな印象もあるが、今の葬儀はなんだか味気なく形式的な感じがあるので、地域で暖かな葬儀や埋葬ができ、かつ経済的にもうまくいけばとてもいいことだ。
県立笠沙高校は2006年に廃校になってもう6年以上経つが、跡地利用がなされないまま放置されているようでもったいない。
市でも「笠沙高校跡地対策協議会」なるものを設置して有効利用できないかと検討してきたようだが、意見がまとまらないまま宙ぶらりんになっていたようだ。先日所有者である県から「グラウンドをメガソーラー設置の用地にしたい」という打診があったということでこれを受諾。あわせて、校舎等については既に痛みが激しいということで、委員会では撤去して更地にするよう県に要望することとしたという。
有効活用の良案もないので県の打診を受けたのだろうが、グラウンドへのメガソーラー設置には惹かれない。アクセスのよい広い土地をメガソーラー用地などにするのはもったいないし、そもそもメガソーラーなんて補助金が切れれば一発で赤字になる事業だ。ゴミになったソーラーの山で埋まらないとよいが…。
さらに、建物が傷んでいるから取り壊す、とのことだが、これだけの施設であり取り壊しにもかなりの金がかかる。外観からしか判断できないが、修繕した方が安上がりなのでは? というのが率直な感想だ。もちろん更地にした後の利用のめどがあるならいいのだが。
そんな中、先輩農家Kさんが、ものすごく斬新な跡地利用のアイデアを世間話で言っていた。曰く「納骨堂にしてしまえばいい」とのこと。大浦・笠沙は高度経済成長期に人口が非常に流出した地域であるが、今後10年程度で流出した団塊世代が一挙に老後を迎えることを考えると墓・納骨堂は意外に供給不足である。
都会に墓を作る人もいるだろうが、墓くらいは故郷に…という人も多いだろう。その際、古くからの集落の共同墓地・共同納骨堂に入れられればいいが、子や孫が定期的に管理することができない場合、寺や墓地会社の永代供養の方が好ましい。荒唐無稽なアイデアに見えて、実は経営的にいけるのではないか。
さらに、もし大規模な納骨堂ができれば定期的に法事があるので地元経済も潤う。花卉類、食事はもちろん、僻地なので宿泊にもお金が落ちるだろう。もちろんテナント利用や企業誘致など、経済効果の高い利用法の方が望ましいのはいうまでもないが、この過疎地域に高望みはできないことを思えば、納骨堂は悪くない。それに、かつて若者が歓声を上げた学舎が納骨堂となるとなれば、高齢化時代の最先端ということで廃校利用の極北として注目も集めそうである。
全国的にも、今後10年程度で団塊世代がどんどん鬼籍に入る時代が来る。つまりその前に、墓地需要は日本史上空前絶後の高まりを見せるのが明白である。今後20年くらいは、夥しい人間が死ぬ時代、そのために心のよりどころを求める宗教の時代になると思う。私がシキミに注目したのも、そういう背景がある。廃校利用の納骨堂はともかくとして、葬儀ビジネスは有望だと思うので、地方活性化の一つの方策になるかもしれない。実際に、静岡県新居町では商工会で葬儀ビジネスに取り組んで成功しているという。葬儀ビジネスというとなんだかアコギな印象もあるが、今の葬儀はなんだか味気なく形式的な感じがあるので、地域で暖かな葬儀や埋葬ができ、かつ経済的にもうまくいけばとてもいいことだ。
2012年11月6日火曜日
ぽんかんドレッシングのチラシをデザインしました
果樹農家の先輩が開発している農産加工品のチラシを作らせてもらった。
写真撮影、文面作成、デザインの全てが素人仕事なので、本職がつくるものに比べて詰めが甘い部分があるが、それなりのものが出来たと思う(自画自賛)。
商品の内容については下のチラシを見てもらいたいが、要は、廃園寸前のポンカン園で無農薬栽培したポンカンの果汁を、ふんだんに使って作ったドレッシング。味は、単体では「めちゃうまい!」というものではないが、独特な風味・酸味があり、これとマッチする料理にかけると本領発揮する。
個人的に一番のオススメは、(季節外れだけれど)冷やし中華にごまドレッシングと混ぜてかけることで、これは工夫すればご当地グルメとしてヒットするレベルだと思う。ごまの甘さとポンカンの酸味というのは、かつて組み合わされたことがなかったのではないか。意外だが非常にうまい。この他、唐揚げにかけるのもかなりイケる。ポンカンの香りと爽やかな酸味で、ありふれた普通の料理がかけるだけでいつもとは違うテイストになるのがいい。
なお、チラシに載せているドレッシングは去年制作されたもので、今年のドレッシングは現在制作途中。ちぎる時期や、搾汁方法が昨年と変更されており、順調に完成までこぎつけるか実は未知数であるが、農産加工は自分としても取り組みたい分野なのでぜひ成功してもらいたい。このチラシが、少しでもそのお役に立てればいいのだが。
ちなみに、まだ非売品なので、発売されたら改めてお知らせすることにしたい。
写真撮影、文面作成、デザインの全てが素人仕事なので、本職がつくるものに比べて詰めが甘い部分があるが、それなりのものが出来たと思う(自画自賛)。
商品の内容については下のチラシを見てもらいたいが、要は、廃園寸前のポンカン園で無農薬栽培したポンカンの果汁を、ふんだんに使って作ったドレッシング。味は、単体では「めちゃうまい!」というものではないが、独特な風味・酸味があり、これとマッチする料理にかけると本領発揮する。
個人的に一番のオススメは、(季節外れだけれど)冷やし中華にごまドレッシングと混ぜてかけることで、これは工夫すればご当地グルメとしてヒットするレベルだと思う。ごまの甘さとポンカンの酸味というのは、かつて組み合わされたことがなかったのではないか。意外だが非常にうまい。この他、唐揚げにかけるのもかなりイケる。ポンカンの香りと爽やかな酸味で、ありふれた普通の料理がかけるだけでいつもとは違うテイストになるのがいい。
なお、チラシに載せているドレッシングは去年制作されたもので、今年のドレッシングは現在制作途中。ちぎる時期や、搾汁方法が昨年と変更されており、順調に完成までこぎつけるか実は未知数であるが、農産加工は自分としても取り組みたい分野なのでぜひ成功してもらいたい。このチラシが、少しでもそのお役に立てればいいのだが。
ちなみに、まだ非売品なので、発売されたら改めてお知らせすることにしたい。
2012年11月1日木曜日
南さつま市定住化促進委員会(その4)
既に1週間ほど前になるが、第4回の「南さつま市定住化促進委員会」が開かれた。
「あなたの移住トコトン! 応援事業」と「起業家支援事業」の2本立ての施策案をまとめ、その他いろいろな施策をパッケージにしたものを移住定住推進施策群とする方向だ。
この構造はこれまでの議論で大体決まった感じだったので、今回はやや細かい話となった。意見交換全体の内容は要約しないが、私が空き屋バンクについて発言した内容をちょっとだけ紹介したい。
空き屋バンクについては以前このブログでも取り上げたが、その利用は低調だ。その理由は次の2つが大きいと思う。第1に、法事などで時々使用するからということ。そして第2に、人に貸すにはまず片付けなければならないが、片付けるのが面倒だということ。実際、ほとんど倉庫的な利用がされている空き屋は多いと思われる。
しかし、倉庫とはいえ内実はガラクタの山というケースがほとんどだろう。つまり、処分するのが面倒だから事実上置きっぱなしにしているだけで、家財管理としての倉庫ではない。また、そうなっている場合は既に所有者は現地を離れており、さらに高齢化している場合も多い。持ち主側としても、結局いつかは身辺整理をしなくてはならない、という懸案をかかえたまま過ごしているのではないか。
そこで、「片付けて空き屋バンクに登録すれば補助金を出す」という制度があったらどうか、と発言した次第である。空き屋を貸して賃料をもらいたいという人は少ないと思うが、いつかはしなければならない片付けに補助金が出るとなれば、飛びつく人もいるかもしれない。
事実、「片付け補助金」というのは他の自治体で既にあり、ちょっと調べただけだが例えば島根県飯南町で実施されている。飯南町の場合は「経費の半額を助成」だが、定額でもいいと思うし、いっそのこと「役所が無料で片付けます」でもよい。
その代わり、片付け当日に置いてある家財は問答無用で全て回収することにして、廃校になった小学校の教室にでも置いておき、市民が少額で購入できるようにすると面白い。 古民家のようなところも多いので、見る人が見れば価値の高い民具や家具も集まるかもしれない。もちろんほとんどはガラクタだろうけど、その方が宝探しのようで楽しいと思う。
我が家の周りにも空き屋が数軒どころではなくあるが、有効利用されているとは言い難い。つまり、空き屋はあるのに入居可能な「物件」はない。いろいろと事情があるのはわかるが、この地域で家探しをしてもほとんど物件が見つからないのは、移住者を呼び込む以前に、住民にとっても困った問題である。
役所の方では、新築への補助金とか、市有地をデベロッパーに格安で払い下げてマンション等を開発するとかの案を出していて、新しく家を建てる方に熱心なようだ。しかし、空き屋問題はこれからどんどん加速していくことが予期されるので、そういう観点でも施策を検討してもらいたいと思う。空き屋をこのまま放置していると、この地域は廃屋だらけのゴーストタウンになってしまいそうである。
【参考リンク】
南さつま市定住化促進委員会(第1回)
南さつま市定住化促進委員会(第2回)
南さつま市定住化促進委員会(第3回)
「あなたの移住トコトン! 応援事業」と「起業家支援事業」の2本立ての施策案をまとめ、その他いろいろな施策をパッケージにしたものを移住定住推進施策群とする方向だ。
この構造はこれまでの議論で大体決まった感じだったので、今回はやや細かい話となった。意見交換全体の内容は要約しないが、私が空き屋バンクについて発言した内容をちょっとだけ紹介したい。
空き屋バンクについては以前このブログでも取り上げたが、その利用は低調だ。その理由は次の2つが大きいと思う。第1に、法事などで時々使用するからということ。そして第2に、人に貸すにはまず片付けなければならないが、片付けるのが面倒だということ。実際、ほとんど倉庫的な利用がされている空き屋は多いと思われる。
しかし、倉庫とはいえ内実はガラクタの山というケースがほとんどだろう。つまり、処分するのが面倒だから事実上置きっぱなしにしているだけで、家財管理としての倉庫ではない。また、そうなっている場合は既に所有者は現地を離れており、さらに高齢化している場合も多い。持ち主側としても、結局いつかは身辺整理をしなくてはならない、という懸案をかかえたまま過ごしているのではないか。
そこで、「片付けて空き屋バンクに登録すれば補助金を出す」という制度があったらどうか、と発言した次第である。空き屋を貸して賃料をもらいたいという人は少ないと思うが、いつかはしなければならない片付けに補助金が出るとなれば、飛びつく人もいるかもしれない。
事実、「片付け補助金」というのは他の自治体で既にあり、ちょっと調べただけだが例えば島根県飯南町で実施されている。飯南町の場合は「経費の半額を助成」だが、定額でもいいと思うし、いっそのこと「役所が無料で片付けます」でもよい。
その代わり、片付け当日に置いてある家財は問答無用で全て回収することにして、廃校になった小学校の教室にでも置いておき、市民が少額で購入できるようにすると面白い。 古民家のようなところも多いので、見る人が見れば価値の高い民具や家具も集まるかもしれない。もちろんほとんどはガラクタだろうけど、その方が宝探しのようで楽しいと思う。
我が家の周りにも空き屋が数軒どころではなくあるが、有効利用されているとは言い難い。つまり、空き屋はあるのに入居可能な「物件」はない。いろいろと事情があるのはわかるが、この地域で家探しをしてもほとんど物件が見つからないのは、移住者を呼び込む以前に、住民にとっても困った問題である。
役所の方では、新築への補助金とか、市有地をデベロッパーに格安で払い下げてマンション等を開発するとかの案を出していて、新しく家を建てる方に熱心なようだ。しかし、空き屋問題はこれからどんどん加速していくことが予期されるので、そういう観点でも施策を検討してもらいたいと思う。空き屋をこのまま放置していると、この地域は廃屋だらけのゴーストタウンになってしまいそうである。
【参考リンク】
南さつま市定住化促進委員会(第1回)
南さつま市定住化促進委員会(第2回)
南さつま市定住化促進委員会(第3回)
2012年10月23日火曜日
「国産紅茶終焉の地」としての枕崎
鹿児島の枕崎市に、「紅茶碑」というのがある。また、インド アッサムから導入した紅茶の原木もある。
曰く「この地に於いて我が国で初めて紅茶栽培が成功した。当時、枕崎町長今給黎誠吾氏は昭和6年印度アッサム種の栽培に着目してこの地に育て…」とのこと。ともかく枕崎は「日本国産紅茶発祥の地」を誇っているのであるが、これは事実だろうか?
私はこれに違和感を感じ、いろいろと調べてみたが、結論を先に言えばこれは事実ではない。残念なことに、枕崎は国産紅茶発祥の地ではないのだ。では、国産紅茶の歴史において枕崎はどのように位置づけられるのだろうか? 非常にマニアックになるが、国産紅茶の歴史を繙き、枕崎における紅茶生産の持つ意味を探ってみたい。
日本紅茶の歴史は、殖産興業に邁進していた明治政府が「紅茶産業が有望では?」と目をつけたことに始まる。明治政府は、静岡に移住し茶栽培に取り組んでいた旧幕臣の多田元吉を役人に取り立て、中国、ついでインドに派遣し栽培・製造方法を習得させる。中国式の製造法はうまくいかなかったが、インド式の製造法で成功し、ここに日本紅茶の生産が開始する。
多田がインドから帰国したのが1877(明治10)年。同年、高知県安丸村に試験場を設けて自生茶を原料として紅茶が作られた。本当の日本紅茶発祥の地は、この高知県安丸村であると言うべきである。ただし、この紅茶はあくまで日本在来の緑茶の樹を使い、製法のみインド式紅茶にしたわけだから本格的な紅茶生産の開始ではない(緑茶の茶葉を紅茶に転用しただけ)。
ちなみに、多田元吉は「近代日本茶業の父」などと呼ばれ、日本の紅茶・緑茶産業の基礎をつくった人物である。多田はアッサムから持ち帰った紅茶の種子を自身の農場である静岡県丸子(まりこ)で栽培するとともに、各地に播種した。紅茶用茶樹の栽培に初めて成功したのはこの静岡県丸子であり、「紅茶碑」にいう「この地に於いて我が国で初めて紅茶栽培が成功した」というのは事実ではない。これは「紅茶碑」の昭和6年に先立つこと50年以上も前の話である。
それからの日本紅茶産業の歴史は波瀾万丈で非常に面白い。紅茶は緑茶と違いグローバル商材であるため、世界情勢に大きな影響を受け、その歴史はまさに世界(主に米国)に翻弄された歴史であった。
まず、多田帰国の翌年である1878年には政府は各地に伝習所(研修施設)を作り、技術の向上に努め、そのおかげで1883年に米国への販路が開けたところが近代紅茶産業の幕開けとなる。ちなみに、それまでは政府は三井物産に委託してロンドンへ紅茶を販売するなどしており、このおかげで三井物産は大もうけし、これは後の日東紅茶へと繋がっていく。
実は、米国は紅茶よりも遙かに多い量の緑茶も日本から輸入していたのだが、1899年、米国はスペインとの戦費調達のため茶に高額な輸入税をかけ、これが日本の緑茶・紅茶業界に打撃を与えた。これは米西戦争後すぐに撤廃されたが、続いて1911年、米国は「着色茶輸入禁止令」を制定。どうもこの頃の日本紅茶は着色料で色つけしていたらしく、これも日本の紅茶業界に衝撃を与えた。明治後半は、米国の政策により茶業界が翻弄された時代といえる。
このように重要顧客である米国への輸出が不安定だった中、1914年に第一次世界大戦が開戦、これにより日本紅茶業界は空前の好況を迎える。これは、イギリスがインド・セイロンからの紅茶輸送船を戦争に徴用して、イギリスからの米国向け紅茶輸出が激減したためであった。しかしこの期に乗じて日本は木茎混入品など低劣な紅茶を大量に輸出。これで米国消費者の不信を買い、流通が正常に戻った戦後は対米輸出はむしろ低迷することになる。折しも1920年、米国は「禁酒法」を制定。インドやセイロン、ジャワなど紅茶産地はこれを好機と見て米国で紅茶の大キャンペーンを開始するが、これに乗り遅れた日本紅茶の存在感はさらに希薄になっていく。空前の好況の後の低迷、これが大正期の日本茶業だった。
1919年、政府は国立茶業試験場を設立し、それまで不十分だった紅茶用の茶樹の育種に取り組み始める。紅茶の価格は国際情勢(というより米国の情勢)に大きく左右され、その品質を高めようというインセンティブが少なかったためか、明治後期に行われていた茶の指定試験(国費により各地の試験場で行われる試験)がこの頃は中止されていたのだった。国立茶業試験場の設立を契機として1929(昭和4)年に指定試験を再開。全国各地で紅茶の指定試験が行われたが、知覧(※1)と枕崎(※2)でもこれが行われた。昭和初期は、紅茶の品質向上が目指された時代だった。
そうした中で1933年、突如として日本の紅茶産業に空前絶後の好況が訪れる。世界恐慌で世界的に紅茶の需要が減り、在庫が激増、価格が半分ほどにまでに下落。これを受けてインド、セイロン、ジャワという紅茶の中心産地が5年間の輸出制限協定を締結し、世界的に紅茶の流通が一気に減少したのだった。そこで日本紅茶への注目が集まったというわけで、輸出量は1年でなんと20倍以上に増え、イギリスまでもが相当量の日本紅茶を買い付けたといわれる。輸出制限の最終年である1937(昭和12)年には、日本紅茶は史上最高の輸出を記録。しかし、これが日本紅茶産業の最後の仇花であった。
全国各地で行われていた紅茶の試験は、この好況の中でも徐々に廃され、1940年度には鹿児島に集約された。その理由は明確でないが、価格の浮沈が激しいだけでなく、国民所得(賃金)の増加によって世界的な競争力を失いつつあった紅茶への関心が薄れ、日本の茶業界が緑茶に収斂していった結果のようである。つまり、国内の誰もが紅茶を見捨てていく中で、鹿児島だけが細々と紅茶研究を続けていく(いかされる)ことになった。しかも、太平洋戦争によって紅茶用茶樹の品種改良は戦前にはあまり成果をあげられなかった。
戦後、高度経済成長によって国産紅茶は国際競争力を失い、国内市場でも緑茶が支配的になる中、1963(昭和38)年3月、枕崎に九州農業試験場枕崎支場が設立され、ここが紅茶栽培奨励と紅茶用品種の開発に邁進することとなる。しかしこれは、紅茶の試験場としては遅すぎる出発だったと言わざるをえない。というのも、同年2月、農林省が「国産紅茶の奨励はもう行わない」ことを決定しているのである。ちなみに、知覧に存在していた農事試験場茶業分場も枕崎支場に統合され、この枕崎支場は国内唯一にして最後の紅茶試験場であった。
なお、枕崎では昭和初期に紅茶の試験地(試験場ではない)が設置されたことから、その栽培もその頃から行われていた。日東紅茶も枕崎に直営の茶園と工場を経営していたし、昭和40年代では県内の紅茶生産量の約半分が枕崎産であった。しかし、枕崎支場が設置された時期には輸出用の紅茶は競争力を完全に失っており、枕崎の生産は国内向けだった。ところが1971年の紅茶輸入自由化で国内消費の命脈も絶たれ、同年紅茶の集荷は中止。高知県安丸村で始まった日本近代紅茶産業の歴史は、ここに枕崎でその幕を下ろしたのである。
つまり、枕崎は「日本国産紅茶発祥の地」というより、「日本国産紅茶終焉の地」なのだ。これでは余りにネガティブな表現だと思われるだろうが、実はこの紅茶奨励にあたった県の職員が、「今になってみれば『何んであのようなボッチな計画を立てたのだろう。』」と当時を苦々しく述懐している。そして自分の仕事は「紅茶産業の終戦処理」だったとまで述べた上、「20数年間にわたり多額の投資をして、紅茶奨励に失敗した過去を反省し、ご迷惑をかけた生産者にお詫び申し上げ、紅茶産業奨励の思い出とする次第です」と結んでいる(※3)。どうも、枕崎の紅茶産業は、既に斜陽化していたものを引き受けさせられた形であり、輝かしい過去といえる過去がないようなのである。
しかし、しかしである。先日紹介したように、現在の枕崎では「姫ふうき」という絶品の紅茶が作られている。そしてこの「姫ふうき」を生み出している「べにふうき」という紅茶用の品種は、多田元吉がアッサムから持ち帰った紅茶の種子を品種改良することで、ようやく1995年になって遅咲きの枕崎支場において生み出されたものなのである。私は、昭和40年代に行われていた紅茶用品種の研究が、細々と続けられてきたことに驚愕した次第である。しかも、この「べにふうき」は日本紅茶開発史の到達点とも言うべき優れた品種なのであるが、それだけではない。この品種に含有されるメチル化カテキンという物質が抗アレルギー作用を有していることが近年明らかになり、花粉症対策などとしてその緑茶が次々と製品化されている。
よく、「鹿児島は周回遅れのトップランナー」と言われる。 この「べにふうき」開発までの長い歴史を見ても、そう感じるのは私だけではないだろう。一度終焉を迎えた日本紅茶が最近各地で復活の兆しを見せているが、その最高峰に枕崎の「姫ふうき」があるのは面白い。残念ながら枕崎にある紅茶の原木と「べにふうき」に系統関係はないが、紆余曲折を経ながらも受け継がれた国産紅茶の歴史が、今後、枕崎でまた新たな展開を見せることを期待している。
※1 正確には、鹿児島県立農事試験場知覧茶業分場
※2 正確には、鹿児島県立農事試験場知覧茶業分場枕崎紅茶試験地
※3 参考文献に挙げた『紅茶百年史』p511 「紅茶産業奨励の思い出」(鹿児島県園芸課 池田高雄)より引用
【参考文献】
『紅茶百年史』1977年、 全日本紅茶振興会
曰く「この地に於いて我が国で初めて紅茶栽培が成功した。当時、枕崎町長今給黎誠吾氏は昭和6年印度アッサム種の栽培に着目してこの地に育て…」とのこと。ともかく枕崎は「日本国産紅茶発祥の地」を誇っているのであるが、これは事実だろうか?
私はこれに違和感を感じ、いろいろと調べてみたが、結論を先に言えばこれは事実ではない。残念なことに、枕崎は国産紅茶発祥の地ではないのだ。では、国産紅茶の歴史において枕崎はどのように位置づけられるのだろうか? 非常にマニアックになるが、国産紅茶の歴史を繙き、枕崎における紅茶生産の持つ意味を探ってみたい。
日本紅茶の歴史は、殖産興業に邁進していた明治政府が「紅茶産業が有望では?」と目をつけたことに始まる。明治政府は、静岡に移住し茶栽培に取り組んでいた旧幕臣の多田元吉を役人に取り立て、中国、ついでインドに派遣し栽培・製造方法を習得させる。中国式の製造法はうまくいかなかったが、インド式の製造法で成功し、ここに日本紅茶の生産が開始する。
多田がインドから帰国したのが1877(明治10)年。同年、高知県安丸村に試験場を設けて自生茶を原料として紅茶が作られた。本当の日本紅茶発祥の地は、この高知県安丸村であると言うべきである。ただし、この紅茶はあくまで日本在来の緑茶の樹を使い、製法のみインド式紅茶にしたわけだから本格的な紅茶生産の開始ではない(緑茶の茶葉を紅茶に転用しただけ)。
ちなみに、多田元吉は「近代日本茶業の父」などと呼ばれ、日本の紅茶・緑茶産業の基礎をつくった人物である。多田はアッサムから持ち帰った紅茶の種子を自身の農場である静岡県丸子(まりこ)で栽培するとともに、各地に播種した。紅茶用茶樹の栽培に初めて成功したのはこの静岡県丸子であり、「紅茶碑」にいう「この地に於いて我が国で初めて紅茶栽培が成功した」というのは事実ではない。これは「紅茶碑」の昭和6年に先立つこと50年以上も前の話である。
それからの日本紅茶産業の歴史は波瀾万丈で非常に面白い。紅茶は緑茶と違いグローバル商材であるため、世界情勢に大きな影響を受け、その歴史はまさに世界(主に米国)に翻弄された歴史であった。
まず、多田帰国の翌年である1878年には政府は各地に伝習所(研修施設)を作り、技術の向上に努め、そのおかげで1883年に米国への販路が開けたところが近代紅茶産業の幕開けとなる。ちなみに、それまでは政府は三井物産に委託してロンドンへ紅茶を販売するなどしており、このおかげで三井物産は大もうけし、これは後の日東紅茶へと繋がっていく。
実は、米国は紅茶よりも遙かに多い量の緑茶も日本から輸入していたのだが、1899年、米国はスペインとの戦費調達のため茶に高額な輸入税をかけ、これが日本の緑茶・紅茶業界に打撃を与えた。これは米西戦争後すぐに撤廃されたが、続いて1911年、米国は「着色茶輸入禁止令」を制定。どうもこの頃の日本紅茶は着色料で色つけしていたらしく、これも日本の紅茶業界に衝撃を与えた。明治後半は、米国の政策により茶業界が翻弄された時代といえる。
このように重要顧客である米国への輸出が不安定だった中、1914年に第一次世界大戦が開戦、これにより日本紅茶業界は空前の好況を迎える。これは、イギリスがインド・セイロンからの紅茶輸送船を戦争に徴用して、イギリスからの米国向け紅茶輸出が激減したためであった。しかしこの期に乗じて日本は木茎混入品など低劣な紅茶を大量に輸出。これで米国消費者の不信を買い、流通が正常に戻った戦後は対米輸出はむしろ低迷することになる。折しも1920年、米国は「禁酒法」を制定。インドやセイロン、ジャワなど紅茶産地はこれを好機と見て米国で紅茶の大キャンペーンを開始するが、これに乗り遅れた日本紅茶の存在感はさらに希薄になっていく。空前の好況の後の低迷、これが大正期の日本茶業だった。
1919年、政府は国立茶業試験場を設立し、それまで不十分だった紅茶用の茶樹の育種に取り組み始める。紅茶の価格は国際情勢(というより米国の情勢)に大きく左右され、その品質を高めようというインセンティブが少なかったためか、明治後期に行われていた茶の指定試験(国費により各地の試験場で行われる試験)がこの頃は中止されていたのだった。国立茶業試験場の設立を契機として1929(昭和4)年に指定試験を再開。全国各地で紅茶の指定試験が行われたが、知覧(※1)と枕崎(※2)でもこれが行われた。昭和初期は、紅茶の品質向上が目指された時代だった。
そうした中で1933年、突如として日本の紅茶産業に空前絶後の好況が訪れる。世界恐慌で世界的に紅茶の需要が減り、在庫が激増、価格が半分ほどにまでに下落。これを受けてインド、セイロン、ジャワという紅茶の中心産地が5年間の輸出制限協定を締結し、世界的に紅茶の流通が一気に減少したのだった。そこで日本紅茶への注目が集まったというわけで、輸出量は1年でなんと20倍以上に増え、イギリスまでもが相当量の日本紅茶を買い付けたといわれる。輸出制限の最終年である1937(昭和12)年には、日本紅茶は史上最高の輸出を記録。しかし、これが日本紅茶産業の最後の仇花であった。
全国各地で行われていた紅茶の試験は、この好況の中でも徐々に廃され、1940年度には鹿児島に集約された。その理由は明確でないが、価格の浮沈が激しいだけでなく、国民所得(賃金)の増加によって世界的な競争力を失いつつあった紅茶への関心が薄れ、日本の茶業界が緑茶に収斂していった結果のようである。つまり、国内の誰もが紅茶を見捨てていく中で、鹿児島だけが細々と紅茶研究を続けていく(いかされる)ことになった。しかも、太平洋戦争によって紅茶用茶樹の品種改良は戦前にはあまり成果をあげられなかった。
戦後、高度経済成長によって国産紅茶は国際競争力を失い、国内市場でも緑茶が支配的になる中、1963(昭和38)年3月、枕崎に九州農業試験場枕崎支場が設立され、ここが紅茶栽培奨励と紅茶用品種の開発に邁進することとなる。しかしこれは、紅茶の試験場としては遅すぎる出発だったと言わざるをえない。というのも、同年2月、農林省が「国産紅茶の奨励はもう行わない」ことを決定しているのである。ちなみに、知覧に存在していた農事試験場茶業分場も枕崎支場に統合され、この枕崎支場は国内唯一にして最後の紅茶試験場であった。
なお、枕崎では昭和初期に紅茶の試験地(試験場ではない)が設置されたことから、その栽培もその頃から行われていた。日東紅茶も枕崎に直営の茶園と工場を経営していたし、昭和40年代では県内の紅茶生産量の約半分が枕崎産であった。しかし、枕崎支場が設置された時期には輸出用の紅茶は競争力を完全に失っており、枕崎の生産は国内向けだった。ところが1971年の紅茶輸入自由化で国内消費の命脈も絶たれ、同年紅茶の集荷は中止。高知県安丸村で始まった日本近代紅茶産業の歴史は、ここに枕崎でその幕を下ろしたのである。
つまり、枕崎は「日本国産紅茶発祥の地」というより、「日本国産紅茶終焉の地」なのだ。これでは余りにネガティブな表現だと思われるだろうが、実はこの紅茶奨励にあたった県の職員が、「今になってみれば『何んであのようなボッチな計画を立てたのだろう。』」と当時を苦々しく述懐している。そして自分の仕事は「紅茶産業の終戦処理」だったとまで述べた上、「20数年間にわたり多額の投資をして、紅茶奨励に失敗した過去を反省し、ご迷惑をかけた生産者にお詫び申し上げ、紅茶産業奨励の思い出とする次第です」と結んでいる(※3)。どうも、枕崎の紅茶産業は、既に斜陽化していたものを引き受けさせられた形であり、輝かしい過去といえる過去がないようなのである。
しかし、しかしである。先日紹介したように、現在の枕崎では「姫ふうき」という絶品の紅茶が作られている。そしてこの「姫ふうき」を生み出している「べにふうき」という紅茶用の品種は、多田元吉がアッサムから持ち帰った紅茶の種子を品種改良することで、ようやく1995年になって遅咲きの枕崎支場において生み出されたものなのである。私は、昭和40年代に行われていた紅茶用品種の研究が、細々と続けられてきたことに驚愕した次第である。しかも、この「べにふうき」は日本紅茶開発史の到達点とも言うべき優れた品種なのであるが、それだけではない。この品種に含有されるメチル化カテキンという物質が抗アレルギー作用を有していることが近年明らかになり、花粉症対策などとしてその緑茶が次々と製品化されている。
よく、「鹿児島は周回遅れのトップランナー」と言われる。 この「べにふうき」開発までの長い歴史を見ても、そう感じるのは私だけではないだろう。一度終焉を迎えた日本紅茶が最近各地で復活の兆しを見せているが、その最高峰に枕崎の「姫ふうき」があるのは面白い。残念ながら枕崎にある紅茶の原木と「べにふうき」に系統関係はないが、紆余曲折を経ながらも受け継がれた国産紅茶の歴史が、今後、枕崎でまた新たな展開を見せることを期待している。
※1 正確には、鹿児島県立農事試験場知覧茶業分場
※2 正確には、鹿児島県立農事試験場知覧茶業分場枕崎紅茶試験地
※3 参考文献に挙げた『紅茶百年史』p511 「紅茶産業奨励の思い出」(鹿児島県園芸課 池田高雄)より引用
【参考文献】
『紅茶百年史』1977年、 全日本紅茶振興会
2012年10月21日日曜日
サクラノヤカタでボンチャチーノを飲む
南九州市の川辺に、清水磨崖仏という仏教遺跡があり当地は公園となっているが、そこに「サクラノヤカタ」というカフェがある。
そこで、梵字をあしらったボンチーノ(カプチーノ)、ボンチャチーノ(抹茶ラテ)というものを飲むことができるというので行ってみた。
家内が頼んだボンチーノは、カプチーノとしても美味しいということだったが、ボンチャチーノの方は、味はまあそれなりというものであった。しかし、梵字をあしらった抹茶ラテなど他の場所では飲めないわけで、相当にプレミアム感があり、非常によいメニューだと思う。
ちなみに、この店には同様に梵字をあしらった「梵字プリン」や「梵字ロール(ロールケーキ)」もあり、こちらもなかなか面白い。
「どうして抹茶ラテに梵字が?」というのがわからない人のために一応解説すると、これは清水磨崖仏に由来している。この磨崖仏は、平安後期から明治までの長い間に断崖絶壁に刻まれた一群の仏教彫刻を指すが、特に秀麗なのが「月輪三大梵字」(鎌倉時代)と、日本一大きな五輪塔表現と言われる「大五輪塔」(平安時代後期)であり、ともに梵字の薬研彫り表現が素晴らしい。
つまり梵字は清水磨崖仏を象徴するものであり、これをカプチーノや抹茶ラテに配することで「いかにも清水磨崖仏」な雰囲気を出しているというわけだ。梵字というと、なぜか血気盛んな男性に人気があり、最近はシルバーアクセサリーなどによく使われるが、この場所で梵字を使うことはわざとらしくもなく、特別感もあり、素晴らしい工夫だと思う。こういうちょっとした工夫をしてくれるだけで、満足感は全く違ったものになる。
ちなみにこの「サクラノヤカタ」、建物がめっぽう変わっている。川辺仏壇の工芸の技を活かして作られた建物ということで、池に浮かぶ金閣や銀閣を模しており、立派な柱と工芸品を使った丁寧かつ豪華な作りであるだけでなく、その奇怪な外観とは裏腹に非常に心地よい空間である。
だが、どうしてこの磨崖仏の地に室町文化の金閣銀閣なのだろう? 磨崖仏文化のピークは平安から鎌倉であり、室町はあまり中心的でない。さらに、金閣も銀閣も禅寺の建築であるが、磨崖仏は密教(真言宗・天台宗)と修験道の文化であり、禅とは関係がない。
つまり、室町時代の禅院を模したこの建物は、時代的にも教義的にも磨崖仏にそぐわない。だからダメとはいわない(むしろ建築としては面白いし居心地もいい)が、やはりチグハグ感は否めない。 しかも、サクラノヤカタという名称は、平安から鎌倉期へかけて当地を支配した川邊氏の館である「桜の屋形」にちなむ。その館の遺跡は残っていないが、当然ながら室町期の禅院様式であったはずではなく、どうしてこのようなコンセプトでこの建物が作られたのか理解に苦しむ。
この建物は総工費1億6千万円(平成6年竣工)だそうだが、金をかけてチグハグなものを作るより、ボンチャチーノのようにちょっとした工夫でその場に即したものを作る方が、私にはよほどスマートに見える。ただ、この建物は、コンセプトはチグハグであっても居心地はよいので、何度も行きたくなる素敵な場所である。
そこで、梵字をあしらったボンチーノ(カプチーノ)、ボンチャチーノ(抹茶ラテ)というものを飲むことができるというので行ってみた。
家内が頼んだボンチーノは、カプチーノとしても美味しいということだったが、ボンチャチーノの方は、味はまあそれなりというものであった。しかし、梵字をあしらった抹茶ラテなど他の場所では飲めないわけで、相当にプレミアム感があり、非常によいメニューだと思う。
ちなみに、この店には同様に梵字をあしらった「梵字プリン」や「梵字ロール(ロールケーキ)」もあり、こちらもなかなか面白い。
「どうして抹茶ラテに梵字が?」というのがわからない人のために一応解説すると、これは清水磨崖仏に由来している。この磨崖仏は、平安後期から明治までの長い間に断崖絶壁に刻まれた一群の仏教彫刻を指すが、特に秀麗なのが「月輪三大梵字」(鎌倉時代)と、日本一大きな五輪塔表現と言われる「大五輪塔」(平安時代後期)であり、ともに梵字の薬研彫り表現が素晴らしい。
つまり梵字は清水磨崖仏を象徴するものであり、これをカプチーノや抹茶ラテに配することで「いかにも清水磨崖仏」な雰囲気を出しているというわけだ。梵字というと、なぜか血気盛んな男性に人気があり、最近はシルバーアクセサリーなどによく使われるが、この場所で梵字を使うことはわざとらしくもなく、特別感もあり、素晴らしい工夫だと思う。こういうちょっとした工夫をしてくれるだけで、満足感は全く違ったものになる。
ちなみにこの「サクラノヤカタ」、建物がめっぽう変わっている。川辺仏壇の工芸の技を活かして作られた建物ということで、池に浮かぶ金閣や銀閣を模しており、立派な柱と工芸品を使った丁寧かつ豪華な作りであるだけでなく、その奇怪な外観とは裏腹に非常に心地よい空間である。
だが、どうしてこの磨崖仏の地に室町文化の金閣銀閣なのだろう? 磨崖仏文化のピークは平安から鎌倉であり、室町はあまり中心的でない。さらに、金閣も銀閣も禅寺の建築であるが、磨崖仏は密教(真言宗・天台宗)と修験道の文化であり、禅とは関係がない。
つまり、室町時代の禅院を模したこの建物は、時代的にも教義的にも磨崖仏にそぐわない。だからダメとはいわない(むしろ建築としては面白いし居心地もいい)が、やはりチグハグ感は否めない。 しかも、サクラノヤカタという名称は、平安から鎌倉期へかけて当地を支配した川邊氏の館である「桜の屋形」にちなむ。その館の遺跡は残っていないが、当然ながら室町期の禅院様式であったはずではなく、どうしてこのようなコンセプトでこの建物が作られたのか理解に苦しむ。
この建物は総工費1億6千万円(平成6年竣工)だそうだが、金をかけてチグハグなものを作るより、ボンチャチーノのようにちょっとした工夫でその場に即したものを作る方が、私にはよほどスマートに見える。ただ、この建物は、コンセプトはチグハグであっても居心地はよいので、何度も行きたくなる素敵な場所である。
2012年10月19日金曜日
一人あたり医療費の地域間格差
 |
| 医療費の地域格差指数 |
さらに、先輩農家Kさんから「医療費が高い理由は、薬の処方が多かったり、通院の回数が多かったり、医者への信頼度が高くて無批判的に診療を受けるからでは?」という示唆もいただいた。ということで、なぜ南さつま市の一人あたり医療費が異常に高いのか、改めて考えてみたい(以下、「一人あたり医療費」を単に「医療費」と略す)。
ただ、南さつま市の詳しい医療費のデータは公表されていないので個別の分析は不可能であり、あくまで一般論、全国的な傾向を元にした話になることをお断りしておく。
まず、医療費にはかなり大きな地域間格差があるのはご存じだろうか。医療費の多寡は高齢化率と相関があるが、仮に世代構成が等しかったと仮定して計算しても、その差は大きい。これを医療費の地域格差指数といい、毎年厚生労働省がデータを公表している。具体的には、全国平均を1として、一人あたりの医療費が全国平均の何倍であるかを示したものである(図を参照)。
図を見てすぐにわかることは、赤っぽく示される医療費の高い地域が西日本と北海道に偏っていることである。これを俗に「医療費の西高東低北高」という。なぜこのような格差が存在するのかというのは謎で定説はないが、西日本や北海道の人が生来的に不健康ということはあり得ないので、病院との関わり方に違いがあると考えられている。
ちなみに、南さつま市の地域間格差指数は約1.3(つまり全国平均の1.3倍の医療費がかかっている)で、全国27位である。これは1700以上ある基礎自治体での27位であるから全国的にトップクラスである。これによって、当市の医療費の高さの原因が高齢化ではないことがわかる。なお、本市と比較可能な規模の市レベルでは、全国9位となる。
ところで、よく言われるのは、医療費は人口あたりの医師数と病床数に強い相関があるということだ。このことから、西日本は医療体制が充実しているから人々がよく病院に行き、結果として医療費が高くなるのではないかと考える人もいる。南さつま市も、過疎地の割には病院が多くあり、この理屈が当てはまりそうな気もする。
ただ、この相関は論理関係が逆なのかもしれない。つまり、人々がよく病院に行くから、結果的に病院がたくさん出来たということも考えられる。私の感覚だと、どちらかというとこちらの方がしっくり来る。病院というのは、高齢者でない限り身近にあるから頻繁に行くというものではない。
ここでKさんの指摘をもう少し紹介する。私自身は南さつま市で診療を受けたことがないのでわからないが、若干誇張して言えば、当地の医療は「お医者さんが絶対的に信頼されていて、診察しても病名も説明されないし、薬は大量に処方されるし、無闇に通院させられたりするが、それを疑問に思う人もいない」というものらしい。家内や子供が行く病院ではこういうことはないようなので、地域全体の医療機関がこうだとは思わないが、そういうところが多いのかもしれない。
今では常識となっているインフォームド・コンセントとか、セカンド・オピニオン、ジェネリック医薬品とかいったものは日本の端っこである南さつま市にはまだ十分に普及していないのかもしれないし、これが医療費を押し上げていてもおかしくはない。つまり、医療体制が充実しているのではなく、逆に医療体制が効率的でないために医療費が高いという可能性がある。ただ、福岡など都市部を含め西日本の広範囲で医療費が高い現象が見られ、一方で東北の僻地でも医療費は低いので、この仮説だけでは医療費の高さを説明しきれない。
ちなみに、西日本の医療費を押し上げているのは主に入院費用である。入院は、診察や治療の他にホテル的な費用がかかるので金額的な影響が大きい。実は、西日本の人は入院する時は長期に入院するという傾向がある。データはないが、もしかしたら頻繁に入院するということもあるかもしれない。つまり、西日本では入院に対する心理的障壁が低く、たいしたことでなくても入院し、必要最低限の期間を超えて入院するのではないか。
病床数が限られている場合、病院側は必要日数以上の入院はさせないので、病床が不足傾向にある東日本では入院が抑制されていると考えられる。病床数が余り気味の西日本ではそうした抑制がきかないので、必要以上の入院がされている可能性は大きい。特に鹿児島は平均在院日数(入院期間)が長く、全国平均を10日以上超える47.8日となっており、都道府県別ではダントツの1位なのである。最短の岐阜(28.3日)と比べると約20日も違い、この差は鹿児島県民の異常な入院好きを示しているとしか思えない。
ところで、病床数や医師数が西日本に比べ少ない東日本では、人々が十分な医療を受けられず苦労したり、それが原因で深刻な病状に陥ったりしているのだろうか? 実はこれが一番衝撃的なデータなのであるが、実は総じて東日本の人の方が健康寿命が長い。健康寿命とは、介護などを受けず健康に過ごせる期間のことを言う。つまり、東日本では医療体制は充実していないのに、人々は健康で過ごせる期間が長いのである。これだけ見ると、病院にはなるべく行かない方が長く健康で過ごせるということになりそうである。
なお、健康寿命と医療費の地域間格差には相関がある。健康寿命が短ければ、闘病や介護の期間が長いということだから医療費が嵩むのは当然だ。しかし、ここでちょっとした謎がある。実は、鹿児島の健康寿命は長い方なのである。これはどう考えるべきか。
図をもう一度よく見てみると、その答えがわかる。見えにくいが、実は鹿児島県でも大隅半島の方は地域格差指数が低い。医療費に関しては、薩摩半島と大隅半島で著しい対照があるのだ。細かいデータはないので明言できないが、鹿児島県民の健康寿命を押し上げているのは、大隅半島の人だと思う。逆に言えば、薩摩半島には不健康な人が多いということになる。
さて、いろいろとデータを見てみたが、南さつま市特有の原因は特定できないながら、まとめると一般論として次のような医療費高騰の原因が考えられる。
- ジェネリック医薬品など、廉価な医療が未だ普及していない。
- 医師への信頼性が高く、高額な医療行為を鵜呑みに受け入れている。
- 病床数や医師数に余裕があるため、来院・入院の心理的障壁が低い。特に入院期間が長い。
- 健康寿命が短く、そもそも不健康な期間が長い。
すなわち、行政が主導して、廉価な医療の導入や入院期間の短縮化を図る努力をすれば改善できる余地があるということだ。具体的には、(これまではタブーであった)医療機関の評価を行い、市民に公表することにより、効率的で低廉な医療を提供している医療機関が一目瞭然になれば公正な競争が期待できる。これは、もし実施すれば全国的に注目を集めるような施策であり、鹿児島大学等と協力して学術的にもしっかりとしたものを実施すれば医療費の高騰にあえぐ他の自治体の役にも立つだろう。
それはさておき、今回いろいろなデータを調べてみて、医療費の西高東低北高という地域間格差の原因が謎とされていることにまず驚かされた。今後さらに負担が増すと考えられている医療費の問題を考える上で、このような基礎的で重要なことがしっかりと研究されていないというのは不可解だ。医療費高騰というと、新聞等では「高齢化の影響で」と不可避的な書き方がされるが、実は私たちの心のありようを変えるだけで、相当違ってくるものなのかもしれない。
【参考データ】
「医療費の地域差(医療費マップ)」平成22年度 厚生労働省
「推計1入院当たり医療費の動向等 -都道府県別、制度別及び病床規模別等-」(平成22年度のデータ) 厚生労働省
「健康寿命の算定結果」平成22年度 健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班
「国民医療費の謎(2)-医療費の地域格差」瀬岡 吉彦
「国民医療費抑制策の実施とその課題」松井 宏樹
2012年10月15日月曜日
南さつま市の一人あたり医療費は、なぜか異常に高い
我が家の移住後の生活において、最も金銭的負担が大きいのは、実は国民健康保険の保険料(国保税)である。
国保税は、市民税・県民税などと同じく前年の所得に応じて算定されるため、移住によってほとんど無収入になっても大きな負担を払わなくてはならない。派遣切りなど、自己都合でない収入減の場合は減免措置があるが、自己都合で収入が減った場合にはそういった救済措置はない。日本の税体系は終身雇用のサラリーマン社会を前提としているから、こういうことになるのだろう。農家を始めとして、所得が不安定な人はこのおかげで随分割を食っていると思う。
ところで、我が南さつま市は「一人あたりの医療費が高い」とよく言われているのだが、どれくらい高いのか疑問に思い、厚生労働省のデータベース(平成22年度)で調べてみた。
結果は、全国の市町村においてなんと28位。全国で1700以上ある基礎自治体の中での28位だからこれは本当に高い。ちなみに一人あたり年間42万円程度。
さらによくデータを見てみると、一位の和歌山県北山村は54万円だが人口500人たらずの小さな村であり、同村を始めとして人口千人以下と思われる過疎の村が上位のほとんどを占める。28位以上の自治体の規模(被保険者数)を調べてみると、なんと本市より規模の大きな自治体は北海道小樽市(23位)しかない。
同サイズと言えそうなのは、同じ鹿児島県のいちき串木野市(18位)だけで、その他はほとんど零細自治体である。つまり、本市と比較可能な市レベルで言えば、本市の一人あたり医療費は全国3位だということだ。
しかも、平成23年度のデータでは本市の一人あたり医療費がさらに増えて45万円を越えており、他の自治体の額にほぼ変動がないとすれば、平成23年度には本市の一人あたり医療費は市レベルでは日本一になる(全国のデータは未発表)。
一人あたり医療費は高齢化率と相関があり、要は年寄りばかりの自治体はこれが高くなるのは当然であるが、実は、本市の高齢化率は全国的に突出して高いわけではない。具体的には、本市の高齢化率は35%で全国264位であり、高いとはいえこれだけでは医療費の高さを説明できない。
こうしたデータだけから見ると、(実際どうなのかはよくわからないが)本市には不健康な人が多いということになりそうである。本市の一人あたり医療費が異様に高い本当の理由はさらに詳細なデータを確認しなくてはならないが、不名誉なランキングであることだけは間違いない。
これは財政面でも危機的状況なのは言うまでもないことで、今年度から本市の国保税は一気に13.6%も負担が引き上げられた。しかしこの問題の本質的な解決のためには、なぜ本市の一人あたり医療費がやたらに高いのかという理由を究明して、これを低減させていく努力が必要だ。
国民健康保険の財政的危機は、このまま高齢化が進むにつれどこの自治体でも顕在化してくる話だ。本市はこれを先取りしている上に、さらに何かの要因で医療費が高くなっているわけで、課題先進地域として問題に果敢に取り組んで、医療費低減の方策を見つけ、発信していただきたいと思う。シンプルに言えば、本市が病院に頼らなくても長生きできる地域になって欲しいと切に願う。
ちなみに、一人あたりの医療費が高いということは、要は国民健康保険から病院に払われているお金が一人あたりで多いということだ。これを逆に言うと、南さつま市民が行っている病院には一人あたりで高い代金が支払われている、つまり客単価が高いということになる。では、本市の病院はやたらに儲けているのだろうか? ぜひともこの統計を見てみたいものである。
【参考データ】
「医療費の地域差(医療費マップ)」(平成22年度) 厚生労働省
「平成22年度国勢調査 都道府県・市区町村別統計表」 総務省
国保税は、市民税・県民税などと同じく前年の所得に応じて算定されるため、移住によってほとんど無収入になっても大きな負担を払わなくてはならない。派遣切りなど、自己都合でない収入減の場合は減免措置があるが、自己都合で収入が減った場合にはそういった救済措置はない。日本の税体系は終身雇用のサラリーマン社会を前提としているから、こういうことになるのだろう。農家を始めとして、所得が不安定な人はこのおかげで随分割を食っていると思う。
ところで、我が南さつま市は「一人あたりの医療費が高い」とよく言われているのだが、どれくらい高いのか疑問に思い、厚生労働省のデータベース(平成22年度)で調べてみた。
結果は、全国の市町村においてなんと28位。全国で1700以上ある基礎自治体の中での28位だからこれは本当に高い。ちなみに一人あたり年間42万円程度。
さらによくデータを見てみると、一位の和歌山県北山村は54万円だが人口500人たらずの小さな村であり、同村を始めとして人口千人以下と思われる過疎の村が上位のほとんどを占める。28位以上の自治体の規模(被保険者数)を調べてみると、なんと本市より規模の大きな自治体は北海道小樽市(23位)しかない。
同サイズと言えそうなのは、同じ鹿児島県のいちき串木野市(18位)だけで、その他はほとんど零細自治体である。つまり、本市と比較可能な市レベルで言えば、本市の一人あたり医療費は全国3位だということだ。
しかも、平成23年度のデータでは本市の一人あたり医療費がさらに増えて45万円を越えており、他の自治体の額にほぼ変動がないとすれば、平成23年度には本市の一人あたり医療費は市レベルでは日本一になる(全国のデータは未発表)。
一人あたり医療費は高齢化率と相関があり、要は年寄りばかりの自治体はこれが高くなるのは当然であるが、実は、本市の高齢化率は全国的に突出して高いわけではない。具体的には、本市の高齢化率は35%で全国264位であり、高いとはいえこれだけでは医療費の高さを説明できない。
こうしたデータだけから見ると、(実際どうなのかはよくわからないが)本市には不健康な人が多いということになりそうである。本市の一人あたり医療費が異様に高い本当の理由はさらに詳細なデータを確認しなくてはならないが、不名誉なランキングであることだけは間違いない。
これは財政面でも危機的状況なのは言うまでもないことで、今年度から本市の国保税は一気に13.6%も負担が引き上げられた。しかしこの問題の本質的な解決のためには、なぜ本市の一人あたり医療費がやたらに高いのかという理由を究明して、これを低減させていく努力が必要だ。
国民健康保険の財政的危機は、このまま高齢化が進むにつれどこの自治体でも顕在化してくる話だ。本市はこれを先取りしている上に、さらに何かの要因で医療費が高くなっているわけで、課題先進地域として問題に果敢に取り組んで、医療費低減の方策を見つけ、発信していただきたいと思う。シンプルに言えば、本市が病院に頼らなくても長生きできる地域になって欲しいと切に願う。
ちなみに、一人あたりの医療費が高いということは、要は国民健康保険から病院に払われているお金が一人あたりで多いということだ。これを逆に言うと、南さつま市民が行っている病院には一人あたりで高い代金が支払われている、つまり客単価が高いということになる。では、本市の病院はやたらに儲けているのだろうか? ぜひともこの統計を見てみたいものである。
【参考データ】
「医療費の地域差(医療費マップ)」(平成22年度) 厚生労働省
「平成22年度国勢調査 都道府県・市区町村別統計表」 総務省
2012年10月12日金曜日
増えるイノシシ被害へどう対処するか
最近、若いイノシシが庭に来るようになって困っている。
そこら中に穴を掘るのはまだ許せるとして、裏庭にほぼ毎日糞をしていくのは本当に辞めて欲しい。我が家はすっかりお散歩コースになってしまったようだ。
近隣の農地においても被害は多発しており、電柵を設置している圃場が多い。しかし獣害対策は本質的には駆除が必要であり、個人による対処療法的な方法では限界が見えている。
野生動物と共存できないのか? という意見もあるだろうが、残念ながら現代の日本では駆除は必須だ。というのも、日本の森林の生態系の頂点であったニホンオオカミが絶滅してしまっているからだ。近年全国的にシカ害やイノシシ害が深刻化している一因は、オオカミ不在の影響がジワジワ効いてきたからということが大きい。
捕食動物は生態系のバランスの要石であって、これが不在になると草食動物が野放図に増殖し、森林の若木等も食い尽くしてしまって、農地のみならず自然の植生体系も攪乱される。オオカミを絶滅させてしまった以上、自然のバランスを保つためにはシカやイノシシは人間が責任を持って一定数駆除しなくてはならないのである。
その一方で、銃刀法改正によって猟銃保持は一層難しくなり(※)、猟銃を返納する人が多いと聞く。猟友会は高齢化し、若手のハンターが加入しないため今後の駆除体制が不透明になりつつある。人力での駆除には限界があるということで、日本にもオオカミを再導入してはどうかという議論もあるが、政治的に困難であり、これからも従来型の駆除に頼らざるをえないことを考えるとこの状況は危機的だ。
害獣の駆除問題は全国的に深刻化しているが、一方で新しい動きもある。ジビエを地域振興に役立てようという取り組みだ。フランス料理では、カモや野ウサギ、シカといった狩猟による野生動物の肉をジビエといい、食肉の中でもとりわけ貴重で上等な食材とされる。先日、増えるエゾシカに対処するため北海道が「エゾシカ対策条例(仮)」を検討中というニュースがあったが、その中でもシカ肉の消費拡大を盛り込む予定らしい。
私は、南さつま市も、僻地にあるという条件を活かして、シシ肉による地域振興に取り組んだらいいと思う。当地には、お隣の南九州市の川辺牛のようなブランド肉もないので、役所的にも推進しやすいだろう。役所が窓口になりイノシシを買い取り、食肉加工を民間に委託して商品開発を行ってはどうか。幸いなことに、当市には食肉加工企業であるスターゼンの工場もある。ここと協力できれば独自性が出せるし、猪鍋や焼き肉といった無骨な料理が中心のイノシシも、ハムやパストラミにすると新しい美味しさが発見できるかもしれない。
最初は官製の取り組みであっても、世間の耳目を集めて消費が拡大すればイノシシの価格が上昇し、狩猟の規模拡大が期待できる。単に駆除ではなく、その肉を食べるのであれば駆除に対する心理的抵抗感も少ない。当地大浦町は、かつて島津氏の鷹狩りの猟場であったとされ、狩集(かりあつまり)という地名・人名も残るなど歴史との関連で話題性も期待できる。獣害対策一つにしても、いろいろな手法やアイデアを組み合わせて、解決策を探っていく必要があると思う。
※ 銃刀法改正…猟銃の所持のために、医師の診断書、技能講習の受講、実弾の帳簿付けなどが義務化された。猟銃の所持がものすごく面倒くさくなった感じ。2009年施行。
そこら中に穴を掘るのはまだ許せるとして、裏庭にほぼ毎日糞をしていくのは本当に辞めて欲しい。我が家はすっかりお散歩コースになってしまったようだ。
近隣の農地においても被害は多発しており、電柵を設置している圃場が多い。しかし獣害対策は本質的には駆除が必要であり、個人による対処療法的な方法では限界が見えている。
野生動物と共存できないのか? という意見もあるだろうが、残念ながら現代の日本では駆除は必須だ。というのも、日本の森林の生態系の頂点であったニホンオオカミが絶滅してしまっているからだ。近年全国的にシカ害やイノシシ害が深刻化している一因は、オオカミ不在の影響がジワジワ効いてきたからということが大きい。
捕食動物は生態系のバランスの要石であって、これが不在になると草食動物が野放図に増殖し、森林の若木等も食い尽くしてしまって、農地のみならず自然の植生体系も攪乱される。オオカミを絶滅させてしまった以上、自然のバランスを保つためにはシカやイノシシは人間が責任を持って一定数駆除しなくてはならないのである。
その一方で、銃刀法改正によって猟銃保持は一層難しくなり(※)、猟銃を返納する人が多いと聞く。猟友会は高齢化し、若手のハンターが加入しないため今後の駆除体制が不透明になりつつある。人力での駆除には限界があるということで、日本にもオオカミを再導入してはどうかという議論もあるが、政治的に困難であり、これからも従来型の駆除に頼らざるをえないことを考えるとこの状況は危機的だ。
害獣の駆除問題は全国的に深刻化しているが、一方で新しい動きもある。ジビエを地域振興に役立てようという取り組みだ。フランス料理では、カモや野ウサギ、シカといった狩猟による野生動物の肉をジビエといい、食肉の中でもとりわけ貴重で上等な食材とされる。先日、増えるエゾシカに対処するため北海道が「エゾシカ対策条例(仮)」を検討中というニュースがあったが、その中でもシカ肉の消費拡大を盛り込む予定らしい。
私は、南さつま市も、僻地にあるという条件を活かして、シシ肉による地域振興に取り組んだらいいと思う。当地には、お隣の南九州市の川辺牛のようなブランド肉もないので、役所的にも推進しやすいだろう。役所が窓口になりイノシシを買い取り、食肉加工を民間に委託して商品開発を行ってはどうか。幸いなことに、当市には食肉加工企業であるスターゼンの工場もある。ここと協力できれば独自性が出せるし、猪鍋や焼き肉といった無骨な料理が中心のイノシシも、ハムやパストラミにすると新しい美味しさが発見できるかもしれない。
最初は官製の取り組みであっても、世間の耳目を集めて消費が拡大すればイノシシの価格が上昇し、狩猟の規模拡大が期待できる。単に駆除ではなく、その肉を食べるのであれば駆除に対する心理的抵抗感も少ない。当地大浦町は、かつて島津氏の鷹狩りの猟場であったとされ、狩集(かりあつまり)という地名・人名も残るなど歴史との関連で話題性も期待できる。獣害対策一つにしても、いろいろな手法やアイデアを組み合わせて、解決策を探っていく必要があると思う。
※ 銃刀法改正…猟銃の所持のために、医師の診断書、技能講習の受講、実弾の帳簿付けなどが義務化された。猟銃の所持がものすごく面倒くさくなった感じ。2009年施行。
2012年10月11日木曜日
自家製ブルーベリーのタルト
先日、家内がブルーベリータルトを作ってくれた。
これがとても美味い。特に台となるクッキー様の生地が美味しく、ここに限って言えばケーキ屋さんなどで売っているものを越えていると思う。サクッとした食感は時間と共に失われていくから、作りたてが美味しいのは当然だが、それにしても美味しい。
ブルーベリーは、家庭菜園で採れたものと知人からもらったものを使ったのだが、味は市販されているものと遜色がない。ブルーベリーは熟しているかどうかの判断が意外に面倒で、若干熟していない実も入っていたと思うが、一粒ずつ食べるような果物ではないのであまり気にしなくてもいいのかもしれない。
ブルーベリーは寒冷地の果物と思われているが、暖地向けの品種もあって沖縄以外の日本全土で栽培可能である。健康によいということで注目を集めたためか、2000年頃から日本での生産量は急激に拡大しており、この10年間で生産量は2倍以上になった。ブルーベリーは背が高くならず管理が簡単なこと、無農薬栽培が容易であることから女性や高齢者にも栽培が可能であり、遊休地の活用作物としても有望視されている。反収も高い。
逆に作物としての難点は、順々に実が熟していくため収穫作業を何度もしなくてはならないことと、鳥に食べられやすいことである。そして最大の難点は、近年生産が急拡大しているとは言っても生産量がまだ少ないため流通が未熟であり、卸先が普通はないことだ。また、生食もされるがケーキのトッピングなどとして使われることが多く、単体で生の果実を食べることが少ないため、一般消費者が未加工のブルーベリーを購入することは稀だ。
そのため、ブルーベリーの栽培はジャムなどの加工とセットで行われる必要があり、それが作物生産としての限界を定めている面がある。しかし逆に言えば、加工所と組み合わされれば非常に有望な作物と言える。というのも、ブルーベリーは冷凍に強く、冷凍しても品質があまり劣化しないので通年加工が可能になるからだ。
事実、このタルトに使ったブルーベリーも冷凍したものを使っていて、初夏の味覚であるブルーベリーを、初秋の今タルトにして食べられるのもこの性質のおかげだ。実は、暖地のブルーベリーは味がイマイチなのではないかという危惧があったがそれは杞憂だったようなので、加工所との組み合わせができそうならブルーベリーの栽培もやってみたいと思っている。
これがとても美味い。特に台となるクッキー様の生地が美味しく、ここに限って言えばケーキ屋さんなどで売っているものを越えていると思う。サクッとした食感は時間と共に失われていくから、作りたてが美味しいのは当然だが、それにしても美味しい。
ブルーベリーは、家庭菜園で採れたものと知人からもらったものを使ったのだが、味は市販されているものと遜色がない。ブルーベリーは熟しているかどうかの判断が意外に面倒で、若干熟していない実も入っていたと思うが、一粒ずつ食べるような果物ではないのであまり気にしなくてもいいのかもしれない。
ブルーベリーは寒冷地の果物と思われているが、暖地向けの品種もあって沖縄以外の日本全土で栽培可能である。健康によいということで注目を集めたためか、2000年頃から日本での生産量は急激に拡大しており、この10年間で生産量は2倍以上になった。ブルーベリーは背が高くならず管理が簡単なこと、無農薬栽培が容易であることから女性や高齢者にも栽培が可能であり、遊休地の活用作物としても有望視されている。反収も高い。
逆に作物としての難点は、順々に実が熟していくため収穫作業を何度もしなくてはならないことと、鳥に食べられやすいことである。そして最大の難点は、近年生産が急拡大しているとは言っても生産量がまだ少ないため流通が未熟であり、卸先が普通はないことだ。また、生食もされるがケーキのトッピングなどとして使われることが多く、単体で生の果実を食べることが少ないため、一般消費者が未加工のブルーベリーを購入することは稀だ。
そのため、ブルーベリーの栽培はジャムなどの加工とセットで行われる必要があり、それが作物生産としての限界を定めている面がある。しかし逆に言えば、加工所と組み合わされれば非常に有望な作物と言える。というのも、ブルーベリーは冷凍に強く、冷凍しても品質があまり劣化しないので通年加工が可能になるからだ。
事実、このタルトに使ったブルーベリーも冷凍したものを使っていて、初夏の味覚であるブルーベリーを、初秋の今タルトにして食べられるのもこの性質のおかげだ。実は、暖地のブルーベリーは味がイマイチなのではないかという危惧があったがそれは杞憂だったようなので、加工所との組み合わせができそうならブルーベリーの栽培もやってみたいと思っている。
2012年10月9日火曜日
地域審議会に初参加
大浦地域審議会なるものの委員になり、本日会議が開かれた。
私も出席するまでその位置づけを正確に理解していなかったが、これは、市町村合併に伴って地域の実情が役所へ伝えづらくなることから、合併後10年間はまちづくり計画等に関して旧自治体ごとに意見を聞きましょう、ということらしい。
本日の内容は、今年度の市政推進状況に関して市役所から説明があり、それをマクラにして委員から意見を述べるという形だった。最初はあまり積極的な発言はなかったが、こういう委員会の常として後半になって発言が相次ぎ、最後は時間切れのような形になったため、残念ながら私自身は発言することができなかった。
市政全体に関することでいろいろ発言したいことはあったが、この会議は大浦地域の実情や要望を聞くことが目的だと思うので、次回か、別の機会に改めて発言したいと思う。発言はできなかったが、いろいろな話を聞けて勉強になり、このような機会をいただいたことに感謝したい。
ちなみに、市役所から配付されて説明があった「市政推進状況資料」というのは、なかなかよくまとまっていて現在の市政の重点がわかるよい資料だと思った。特に公表して差し支えがある部分があるようにも思えないので、南さつま市のWEBサイトに掲載したらいいと思う。
というより、地域審議会で配布する資料は全て市のWEBサイトで公表したらいい。もっというと、地域審議会だけでなく、市民が参加するあらゆる検討会や審議会の資料は、公表するべきだと思う。
国政では、既に審議会等の資料は公表することが原則であり、多くの場合は議事録も公開される。国政と市政では影響の大きさが桁違いだから別に議事録などは作成する必要はないと思うが、資料の公表くらいは国政に倣ってもよい。
それから、話が変わるが市からの説明の中で「くじら座礁10周年記念事業」として、大浦ふるさと館のくじらモニュメントの裏手(横?)に座礁したマッコウクジラの骨格を展示する「くじらの眠る丘」という施設を建設するという話があったが、その施設のデザイン案が凄かった。ちらっと見ただけだが、なんと、クジラ型の建物を作る案だったのである。
市役所の方がいろいろ検討した結果としての案なのだろうし、まだ何も公表されていない時点で批判めいたことは言いたくはないが、クジラ型の建物というのは悪趣味だし、そもそも既にクジラのモニュメントがある場所に2頭目のクジラを作るというのは重複感が否めない。特注品的な建物はメンテナンスも面倒だ。これは再考していただきたいというのが率直な感想である。
私も出席するまでその位置づけを正確に理解していなかったが、これは、市町村合併に伴って地域の実情が役所へ伝えづらくなることから、合併後10年間はまちづくり計画等に関して旧自治体ごとに意見を聞きましょう、ということらしい。
本日の内容は、今年度の市政推進状況に関して市役所から説明があり、それをマクラにして委員から意見を述べるという形だった。最初はあまり積極的な発言はなかったが、こういう委員会の常として後半になって発言が相次ぎ、最後は時間切れのような形になったため、残念ながら私自身は発言することができなかった。
市政全体に関することでいろいろ発言したいことはあったが、この会議は大浦地域の実情や要望を聞くことが目的だと思うので、次回か、別の機会に改めて発言したいと思う。発言はできなかったが、いろいろな話を聞けて勉強になり、このような機会をいただいたことに感謝したい。
ちなみに、市役所から配付されて説明があった「市政推進状況資料」というのは、なかなかよくまとまっていて現在の市政の重点がわかるよい資料だと思った。特に公表して差し支えがある部分があるようにも思えないので、南さつま市のWEBサイトに掲載したらいいと思う。
というより、地域審議会で配布する資料は全て市のWEBサイトで公表したらいい。もっというと、地域審議会だけでなく、市民が参加するあらゆる検討会や審議会の資料は、公表するべきだと思う。
国政では、既に審議会等の資料は公表することが原則であり、多くの場合は議事録も公開される。国政と市政では影響の大きさが桁違いだから別に議事録などは作成する必要はないと思うが、資料の公表くらいは国政に倣ってもよい。
それから、話が変わるが市からの説明の中で「くじら座礁10周年記念事業」として、大浦ふるさと館のくじらモニュメントの裏手(横?)に座礁したマッコウクジラの骨格を展示する「くじらの眠る丘」という施設を建設するという話があったが、その施設のデザイン案が凄かった。ちらっと見ただけだが、なんと、クジラ型の建物を作る案だったのである。
市役所の方がいろいろ検討した結果としての案なのだろうし、まだ何も公表されていない時点で批判めいたことは言いたくはないが、クジラ型の建物というのは悪趣味だし、そもそも既にクジラのモニュメントがある場所に2頭目のクジラを作るというのは重複感が否めない。特注品的な建物はメンテナンスも面倒だ。これは再考していただきたいというのが率直な感想である。
2012年10月7日日曜日
笠沙美術館——日本一眺めのいい美術館
南さつま市笠沙町のリアス式海岸を走る国道沿いに、「笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)」がある。
展示品は笠沙町出身の画家 黒瀬道則氏の寄贈作品がほとんどで、その好き嫌いは分かれるところだと思うが、この美術館からの眺望は文句なく素晴らしい。
エントランスからパティオに向かうと、東シナ海に浮かぶ沖秋目島(ビロウ島)が望め、それがさながら一幅の絵画のように建物で切り取られる。赤茶けた直線的な建物と、青い空と海が鋭く対比された風景は、むしろ南欧風ですらある。
聞くところでは、もともとこの美術館は展望所として計画されたものであるということで、絶景なのは当然だ。その建物も作品の展示というより、そこから望む風景を主体として設計されているように見える。ちなみに、建物のデザインは「つばめ」や「指宿のたまて箱」など、JR九州の多くの車両をデザインしたことで著名な水戸岡鋭治氏によるものらしい。そのデザインにただ者でないセンスを感じたが、納得である。
笠沙美術館は南さつま市にとって大きな財産だと思うが、来客もまばらであまり利用されていないのは残念だ。黒瀬氏の絵は、ミステリーの表紙になるような絵で面白味はあると思うが、正直なところ、何度も見たくなるようなものではないし、一般受けするものではない。せっかくの素晴らしい美術館が、郷土出身の画家の紹介だけに終わってしまってはもったいない。
そういうことから、私としては、ここをギャラリースペースとして積極的に活用し、多くの人に来てもらえるようにしたらいいと思う。小さなグループの個展などでも家族友人等でそれなりに人が来るので、この風景の素晴らしさを体感してくれれば口コミによる波及効果も期待できる。
ちなみに、今でもそういう利用ができないわけではないが、WEBサイトにも何も書いていないし、そもそも美術館の存在自体が積極的に広報されていない。なお、賃借料はギャラリーのみだと2100円/日で、全体を借りると5250円/日、展望所と駐車場は無料である。せっかくの素晴らしい資源なのだから、前向きに活用してもらいたいものだ。きっとここは、MOA美術館(熱海)や神奈川県立近代美術館(葉山)を越えて、日本一眺めのいい美術館といえるだろうから。
展示品は笠沙町出身の画家 黒瀬道則氏の寄贈作品がほとんどで、その好き嫌いは分かれるところだと思うが、この美術館からの眺望は文句なく素晴らしい。
エントランスからパティオに向かうと、東シナ海に浮かぶ沖秋目島(ビロウ島)が望め、それがさながら一幅の絵画のように建物で切り取られる。赤茶けた直線的な建物と、青い空と海が鋭く対比された風景は、むしろ南欧風ですらある。
聞くところでは、もともとこの美術館は展望所として計画されたものであるということで、絶景なのは当然だ。その建物も作品の展示というより、そこから望む風景を主体として設計されているように見える。ちなみに、建物のデザインは「つばめ」や「指宿のたまて箱」など、JR九州の多くの車両をデザインしたことで著名な水戸岡鋭治氏によるものらしい。そのデザインにただ者でないセンスを感じたが、納得である。
笠沙美術館は南さつま市にとって大きな財産だと思うが、来客もまばらであまり利用されていないのは残念だ。黒瀬氏の絵は、ミステリーの表紙になるような絵で面白味はあると思うが、正直なところ、何度も見たくなるようなものではないし、一般受けするものではない。せっかくの素晴らしい美術館が、郷土出身の画家の紹介だけに終わってしまってはもったいない。
そういうことから、私としては、ここをギャラリースペースとして積極的に活用し、多くの人に来てもらえるようにしたらいいと思う。小さなグループの個展などでも家族友人等でそれなりに人が来るので、この風景の素晴らしさを体感してくれれば口コミによる波及効果も期待できる。
ちなみに、今でもそういう利用ができないわけではないが、WEBサイトにも何も書いていないし、そもそも美術館の存在自体が積極的に広報されていない。なお、賃借料はギャラリーのみだと2100円/日で、全体を借りると5250円/日、展望所と駐車場は無料である。せっかくの素晴らしい資源なのだから、前向きに活用してもらいたいものだ。きっとここは、MOA美術館(熱海)や神奈川県立近代美術館(葉山)を越えて、日本一眺めのいい美術館といえるだろうから。
2012年10月5日金曜日
南さつま市定住化促進委員会(その3)
南さつま市定住化促進委員会も第3回である。
今回は、事務局がこれまで出された意見に基づき施策体系案を出してくれた。私が出した「起業家支援」も一応入っていてよかった。ただ、施策をバラバラに並べた感じがして焦点がぼやけているので、これをどんな風にまとめるか? どんなキャッチフレーズで推進するか? という話の流れになった。
そして会議の最後に、委員のI氏から大変いい意見が出た。要約すると、
(1)「あなたの移住トコトン応援!」をキャッチフレーズにし、
(2)役所には「南さつまコンシェルジュ」を置き移住者の種々の相談に対応、
(3)それぞれの分野に知識と人脈を持つ市民による「移住応援団」を作り、移住者の問題解決を支援。
という感じになる。 南さつまの売りは何なのか、という意見が前回にもあったが、これは移住者へのケア体制を充実させること自体を売りにしてはどうかという意見だと思う。補助金など金銭面の支援が中心になると、どうしても同種の補助を行う自治体との価格競争になるが、お金より熱意の支援体制であれば差別化ができる。
「あなたの移住トコトン応援!」、これは大変よいキャッチフレーズと思ったが、一方では、移住してくる人にとって移住はあくまでも手段で、南さつま市でどういう暮らし(仕事、生活、子育て等)をするか、ということが目的だ。
そう考えると、キャッチフレーズはさらに大風呂敷を広げた方がよく、「夢の実現をお手伝いします」くらいの方がいいのではないだろうか。里帰りも含めて、移住してくる人はそれぞれこんな暮らしをしたいという夢があると思う。自然が豊かなところで子育てしたいとか、古民家で暮らしたいとか、家庭菜園付きの家に住みたいとか。また、私が提案した起業家も、こんな店を持ちたいといった夢があるはずだ。移住はその夢を実現するための手段にすぎない。とすれば、夢の実現まで支援をしてみてはどうか。
すなわち、
(1)「南さつま市はあなたの夢の実現をお手伝いします」をキャッチフレーズとし、
(2)役所には「夢実現コンシェルジュ」を置き市民や移住者からの相談に対応、
(3)それぞれの分野に知識と人脈を持つ市民による「夢実現応援団」を作り、市民や移住者の問題解決を支援。
としてはどうか。そしてそれを支えるものとして、起業家支援や生活支援の具体的施策を位置づける。
単に移住を支援している自治体はたくさんあると思うが、そこでの理想の暮らしを実現するための支援をしている自治体などないと思う。「夢実現コンシェルジュ」を置くだけで、NHKが取材に来るレベルだろう。そしてこれは、移住者だけでなく現に今住んでいる人にとっても有意義なものだ。この仕組みがあったら、例えば私なら農産物加工所の開設のノウハウを聞いてみたい。
南さつま市は自然も豊かで、今若者に人気が出始めている一次産業も農林漁業が揃っている。一次産業は実は参入ハードルが高いので、役所が積極的に参入を支援してくれれば、首都圏から若者も移住してくるかもしれない。もちろん、「私の夢はフェラーリに乗ること」みたいな人もいるわけだが、さすがにそんな人は役所に来ないと思うので、「夢というと範囲が広すぎる」という心配は無用と思う。
少なくとも私は、こんな取り組みをしている自治体があったら、そこの住民を羨ましいと思うのだが、どうだろうか。
【参考リンク】
南さつま市定住化促進委員会(第1回)
南さつま市定住化促進委員会(第2回)
今回は、事務局がこれまで出された意見に基づき施策体系案を出してくれた。私が出した「起業家支援」も一応入っていてよかった。ただ、施策をバラバラに並べた感じがして焦点がぼやけているので、これをどんな風にまとめるか? どんなキャッチフレーズで推進するか? という話の流れになった。
そして会議の最後に、委員のI氏から大変いい意見が出た。要約すると、
(1)「あなたの移住トコトン応援!」をキャッチフレーズにし、
(2)役所には「南さつまコンシェルジュ」を置き移住者の種々の相談に対応、
(3)それぞれの分野に知識と人脈を持つ市民による「移住応援団」を作り、移住者の問題解決を支援。
という感じになる。 南さつまの売りは何なのか、という意見が前回にもあったが、これは移住者へのケア体制を充実させること自体を売りにしてはどうかという意見だと思う。補助金など金銭面の支援が中心になると、どうしても同種の補助を行う自治体との価格競争になるが、お金より熱意の支援体制であれば差別化ができる。
「あなたの移住トコトン応援!」、これは大変よいキャッチフレーズと思ったが、一方では、移住してくる人にとって移住はあくまでも手段で、南さつま市でどういう暮らし(仕事、生活、子育て等)をするか、ということが目的だ。
そう考えると、キャッチフレーズはさらに大風呂敷を広げた方がよく、「夢の実現をお手伝いします」くらいの方がいいのではないだろうか。里帰りも含めて、移住してくる人はそれぞれこんな暮らしをしたいという夢があると思う。自然が豊かなところで子育てしたいとか、古民家で暮らしたいとか、家庭菜園付きの家に住みたいとか。また、私が提案した起業家も、こんな店を持ちたいといった夢があるはずだ。移住はその夢を実現するための手段にすぎない。とすれば、夢の実現まで支援をしてみてはどうか。
すなわち、
(1)「南さつま市はあなたの夢の実現をお手伝いします」をキャッチフレーズとし、
(2)役所には「夢実現コンシェルジュ」を置き市民や移住者からの相談に対応、
(3)それぞれの分野に知識と人脈を持つ市民による「夢実現応援団」を作り、市民や移住者の問題解決を支援。
としてはどうか。そしてそれを支えるものとして、起業家支援や生活支援の具体的施策を位置づける。
単に移住を支援している自治体はたくさんあると思うが、そこでの理想の暮らしを実現するための支援をしている自治体などないと思う。「夢実現コンシェルジュ」を置くだけで、NHKが取材に来るレベルだろう。そしてこれは、移住者だけでなく現に今住んでいる人にとっても有意義なものだ。この仕組みがあったら、例えば私なら農産物加工所の開設のノウハウを聞いてみたい。
南さつま市は自然も豊かで、今若者に人気が出始めている一次産業も農林漁業が揃っている。一次産業は実は参入ハードルが高いので、役所が積極的に参入を支援してくれれば、首都圏から若者も移住してくるかもしれない。もちろん、「私の夢はフェラーリに乗ること」みたいな人もいるわけだが、さすがにそんな人は役所に来ないと思うので、「夢というと範囲が広すぎる」という心配は無用と思う。
少なくとも私は、こんな取り組みをしている自治体があったら、そこの住民を羨ましいと思うのだが、どうだろうか。
【参考リンク】
南さつま市定住化促進委員会(第1回)
南さつま市定住化促進委員会(第2回)
2012年10月2日火曜日
最高に美味しい枕崎の紅茶「姫ふうき」
枕崎に「手摘み 姫ふうき」というかなり高価な紅茶がある。
この紅茶はGreat Taste Awardsというイギリスの食品国際コンテストで2009年に日本からの出品として初めて三つ星金賞を取得している。飲んでみると、非常に上品で爽やかであり、芳醇な香りも素晴らしい。特に味や香りに際だった特徴があるというものではなく、全ての面でクオリティが高いという王道の紅茶である。
Great Taste Awardsというのは、1994年開始のどちらかというとイギリスローカルなコンテスト。人口に膾炙しているモンドセレクションは味のコンテストではなくて品質管理の認証だが、こちらは正真正銘の味のコンテストで、Webサイトの説明によると「イギリスの美味しいものをお知らせ」するためにイギリスの食品組合(The Guild of Fine Food)によって行われている。俗に「食のオスカー賞」と呼ばれ、三つ星金賞を5回獲ったら英国王室御用達になると言われるほど権威があるらしい(多分噂だろうが)。
私はアルコールがあまり飲めないので茶、紅茶、コーヒーなどは高価なものを飲んできた方だと思うが、確かにこの紅茶はこれまでで一番美味しいと思った。銀座の紅茶専門店で飲んだものよりも上だ。だが、実は価格も一番高かった。40gで1500円というのはかなり特別な紅茶なのは間違いない(まあ、10杯飲めると思えば一杯あたり150円だが…)。
とはいっても、この高価格には訳があり、有機栽培でしかも手摘みらしい。このため年間生産量は100〜150kgとかなり貴重だ。お茶と言えば機械化が当たり前の時代、手摘みの紅茶を作るなんてかなり異端と思うが、紅茶の本場であるイギリスで三つ星金賞を獲るくらいだから、異端も極めれば王道になるということだろうか。
ところで、日本にはこのGreat Taste Awardsの三つ星金賞を獲った紅茶がもう一つある。それは、知覧にある薩摩英国館の「夢ふうき」である。「夢ふうき」は「姫ふうき」に先立って2007年から金賞を連続受賞していたが、今年9月に発表されたGreat Taste Awards 2012において念願の三つ星金賞を受賞。これは薩摩英国館Webサイトにもまだ出ていない情報で、さっき検索していたら偶然知ったものだ。ちなみにこちらも有機栽培、手摘みである。
「夢ふうき」「姫ふうき」と名前が似ているが、この二つの紅茶は同じ「べにふうき」という品種の紅茶用茶樹から作られている。「べにふうき」は日本紅茶開発史の到達点とも言うべき優れた品種であり、本品種を擁した枕崎は「日本紅茶発祥の地」としてこれを誇っているのであるが、このことについてはまた稿を改めて書きたいと思う。
【長い蛇足】
Great Taste Awardsについて日本語ではちゃんとした(雰囲気が伝わる)紹介がなかったので、備忘のためにここに書いておきたい。
Webサイトや公表された審査風景などを見ると、このコンテストは「権威ある」という言葉から想像されるようなものではなく、もっと気軽な、お祭り気分のものだ。ヨーロッパでは、イギリス料理はまずいものの代表のように思われているが、そういう風潮に対して「イギリスにだってうまいものはあるんだからね!」という主張をするためにやっているようなところがあり、そもそもコンテストの趣旨の一つが「イギリスで一番うまいものを決めよう」なのである。
星ごとの評価も、一つ星「だいたい完璧」、二つ星「欠点なし」、三つ星「わお、これは是非食べるべき!」となっており、随分気楽な表現になっている。
こうした気楽なコンテストであるが、というかだからこそ審査はやたらと気合いが入っており、 一流シェフ、料理研究家などが大勢あつまってガチンコの審査をするわけである。その模様はBBCがレポートしているが、雰囲気としてはかつての「TVチャンピオン」に近い。
結果公表も、イギリスの地域ごとで三つ星を紹介するようなかたちになっており、「お住まいの近くにも美味しいものがあるから是非行ってください!」みたいな感じである。こんなガチンコのうまいもん発掘コンテストだからこそ、基本的にはイギリスローカルにも関わらず各国から食品が出品されているというわけで、海外からの食品は「TVチャンピオン」に譬えるなら「今回はアメリカから刺客が登場!」みたいな感じで扱われることになる。
というわけで、基本的にはイギリスのうまいもんを発掘・認定するためのコンテストにおいて、まさにイギリスのお家芸ともいうべき紅茶部門で日本からの出品が三つ星金賞を獲ったということは驚異的なことだと思う。このあたりのことが、日本のWEBサイトにはどこにも書いておらず、その意味があまり正確に理解されていないようなのは残念なことだ。
この紅茶はGreat Taste Awardsというイギリスの食品国際コンテストで2009年に日本からの出品として初めて三つ星金賞を取得している。飲んでみると、非常に上品で爽やかであり、芳醇な香りも素晴らしい。特に味や香りに際だった特徴があるというものではなく、全ての面でクオリティが高いという王道の紅茶である。
Great Taste Awardsというのは、1994年開始のどちらかというとイギリスローカルなコンテスト。人口に膾炙しているモンドセレクションは味のコンテストではなくて品質管理の認証だが、こちらは正真正銘の味のコンテストで、Webサイトの説明によると「イギリスの美味しいものをお知らせ」するためにイギリスの食品組合(The Guild of Fine Food)によって行われている。俗に「食のオスカー賞」と呼ばれ、三つ星金賞を5回獲ったら英国王室御用達になると言われるほど権威があるらしい(多分噂だろうが)。
私はアルコールがあまり飲めないので茶、紅茶、コーヒーなどは高価なものを飲んできた方だと思うが、確かにこの紅茶はこれまでで一番美味しいと思った。銀座の紅茶専門店で飲んだものよりも上だ。だが、実は価格も一番高かった。40gで1500円というのはかなり特別な紅茶なのは間違いない(まあ、10杯飲めると思えば一杯あたり150円だが…)。
とはいっても、この高価格には訳があり、有機栽培でしかも手摘みらしい。このため年間生産量は100〜150kgとかなり貴重だ。お茶と言えば機械化が当たり前の時代、手摘みの紅茶を作るなんてかなり異端と思うが、紅茶の本場であるイギリスで三つ星金賞を獲るくらいだから、異端も極めれば王道になるということだろうか。
ところで、日本にはこのGreat Taste Awardsの三つ星金賞を獲った紅茶がもう一つある。それは、知覧にある薩摩英国館の「夢ふうき」である。「夢ふうき」は「姫ふうき」に先立って2007年から金賞を連続受賞していたが、今年9月に発表されたGreat Taste Awards 2012において念願の三つ星金賞を受賞。これは薩摩英国館Webサイトにもまだ出ていない情報で、さっき検索していたら偶然知ったものだ。ちなみにこちらも有機栽培、手摘みである。
「夢ふうき」「姫ふうき」と名前が似ているが、この二つの紅茶は同じ「べにふうき」という品種の紅茶用茶樹から作られている。「べにふうき」は日本紅茶開発史の到達点とも言うべき優れた品種であり、本品種を擁した枕崎は「日本紅茶発祥の地」としてこれを誇っているのであるが、このことについてはまた稿を改めて書きたいと思う。
【長い蛇足】
Great Taste Awardsについて日本語ではちゃんとした(雰囲気が伝わる)紹介がなかったので、備忘のためにここに書いておきたい。
Webサイトや公表された審査風景などを見ると、このコンテストは「権威ある」という言葉から想像されるようなものではなく、もっと気軽な、お祭り気分のものだ。ヨーロッパでは、イギリス料理はまずいものの代表のように思われているが、そういう風潮に対して「イギリスにだってうまいものはあるんだからね!」という主張をするためにやっているようなところがあり、そもそもコンテストの趣旨の一つが「イギリスで一番うまいものを決めよう」なのである。
星ごとの評価も、一つ星「だいたい完璧」、二つ星「欠点なし」、三つ星「わお、これは是非食べるべき!」となっており、随分気楽な表現になっている。
こうした気楽なコンテストであるが、というかだからこそ審査はやたらと気合いが入っており、 一流シェフ、料理研究家などが大勢あつまってガチンコの審査をするわけである。その模様はBBCがレポートしているが、雰囲気としてはかつての「TVチャンピオン」に近い。
結果公表も、イギリスの地域ごとで三つ星を紹介するようなかたちになっており、「お住まいの近くにも美味しいものがあるから是非行ってください!」みたいな感じである。こんなガチンコのうまいもん発掘コンテストだからこそ、基本的にはイギリスローカルにも関わらず各国から食品が出品されているというわけで、海外からの食品は「TVチャンピオン」に譬えるなら「今回はアメリカから刺客が登場!」みたいな感じで扱われることになる。
というわけで、基本的にはイギリスのうまいもんを発掘・認定するためのコンテストにおいて、まさにイギリスのお家芸ともいうべき紅茶部門で日本からの出品が三つ星金賞を獲ったということは驚異的なことだと思う。このあたりのことが、日本のWEBサイトにはどこにも書いておらず、その意味があまり正確に理解されていないようなのは残念なことだ。
2012年9月29日土曜日
地方と首都圏の図書館格差
ある稀少な本をどうしても参照したくなって、国立国会図書館の本を取り寄せた。
あまり知られていないが、図書館間には「相互貸借」という制度があって、図書館同士で本を貸し借りすることができる。この制度を使うと、地元の小さな図書館を窓口にして、(理論的には)全国の図書館の本を借りられるのである。
というわけで、地元の大浦図書館で「国会図書館の本を借りたいんですが…」と気軽に申し込んだら、これがなかなか大変な事態を招いた。国会図書館の本の取り寄せは南さつま市で初めてのことらしく、まず国会図書館から相互貸借の承認を得るところからスタートしなくてはならない。
国会図書館の本は基本的に個人が持ち出すことは出来ないので、館内での閲覧になるのだが、そのためには館内の環境が整備されている必要がある。具体的には、専任職員の監視の目が行き届いていることや、施設設備が要件に合致していることなどが求められる。図書館の方は、それらの要件を満たしていることを証明するため、図書館の図面まで国会図書館に提出したらしい。大変なご迷惑をかけたと思う。
結果として、加世田の中央図書館が相互貸借の承認を受け、私はめでたく資料を閲覧することができた(大浦図書館は常時監視の専任職員がいないのでダメだった)。申し込んでから約3ヶ月もかかったのには正直辟易した部分もあったが、市役所の方々の努力には本当に感謝したい。
ところで、鹿児島の図書館は蔵書、管理、サービス全ての面で貧弱だ。そもそも国会図書館所蔵の本を求めたのも、鹿児島の図書館にあまりに本がないので仕方なくしたことだ。首都圏の図書館が充実しすぎているということもあるかもしれないが、地方と首都圏との図書館格差は非常に大きい。どれくらいの格差があるかというと、鹿児島県立図書館は、首都圏における小さめの区立図書館くらいの規模しかないのである。これは、移住してきて受けた(数少ない)カルチャーショックの一つだ。
田舎の人は都会の人に比べて本を読まないということはあるので、ある程度の格差はしょうがない。都会では長い電車通勤の暇つぶしのために本が消費されている面があるが、車社会の田舎では意識して時間を作らないと読書ができないから本はどうしても縁遠い存在になる。それに、あまり図書館を充実させてしまうと、ただでさえ経営が苦しい地方の零細書店を圧迫する可能性もあるのだろう。そして、いい意味でも悪い意味でも悠久の時間が流れる農村では、本からの知識は役に立たないことも多い。
しかし、やはり本は重要な情報源だと思うし、図書館で読む本とお金を出して買う本は性質が異なると思うので、田舎であっても図書館は充実させるべきだと思う。都市と地方の情報格差を図書館が拡大しているようでは仕方ない。情報の少ない田舎だからこそ、図書館を充実させて新しい情報をどんどん取り入れるべきだ。これには、予算も比較的かからない。
蛇足だが、鹿児島で一番大きな図書館である鹿児島大学の図書館からも、先日ある本を取り寄せた。これも南さつま市で初めてのことだったらしいが、鹿児島大学から郵送料をなんと960円も取られた。郵送料が必要とは事前に聞いていたが、せいぜい300円くらいのものかと思っていた。鹿児島大学図書館は、第一義的には学生のためのものとはいえ、鹿児島県民の最後の砦となる図書館なのだから、もう少し利用しやすくなってもらいたいと思う。
あまり知られていないが、図書館間には「相互貸借」という制度があって、図書館同士で本を貸し借りすることができる。この制度を使うと、地元の小さな図書館を窓口にして、(理論的には)全国の図書館の本を借りられるのである。
というわけで、地元の大浦図書館で「国会図書館の本を借りたいんですが…」と気軽に申し込んだら、これがなかなか大変な事態を招いた。国会図書館の本の取り寄せは南さつま市で初めてのことらしく、まず国会図書館から相互貸借の承認を得るところからスタートしなくてはならない。
国会図書館の本は基本的に個人が持ち出すことは出来ないので、館内での閲覧になるのだが、そのためには館内の環境が整備されている必要がある。具体的には、専任職員の監視の目が行き届いていることや、施設設備が要件に合致していることなどが求められる。図書館の方は、それらの要件を満たしていることを証明するため、図書館の図面まで国会図書館に提出したらしい。大変なご迷惑をかけたと思う。
結果として、加世田の中央図書館が相互貸借の承認を受け、私はめでたく資料を閲覧することができた(大浦図書館は常時監視の専任職員がいないのでダメだった)。申し込んでから約3ヶ月もかかったのには正直辟易した部分もあったが、市役所の方々の努力には本当に感謝したい。
ところで、鹿児島の図書館は蔵書、管理、サービス全ての面で貧弱だ。そもそも国会図書館所蔵の本を求めたのも、鹿児島の図書館にあまりに本がないので仕方なくしたことだ。首都圏の図書館が充実しすぎているということもあるかもしれないが、地方と首都圏との図書館格差は非常に大きい。どれくらいの格差があるかというと、鹿児島県立図書館は、首都圏における小さめの区立図書館くらいの規模しかないのである。これは、移住してきて受けた(数少ない)カルチャーショックの一つだ。
田舎の人は都会の人に比べて本を読まないということはあるので、ある程度の格差はしょうがない。都会では長い電車通勤の暇つぶしのために本が消費されている面があるが、車社会の田舎では意識して時間を作らないと読書ができないから本はどうしても縁遠い存在になる。それに、あまり図書館を充実させてしまうと、ただでさえ経営が苦しい地方の零細書店を圧迫する可能性もあるのだろう。そして、いい意味でも悪い意味でも悠久の時間が流れる農村では、本からの知識は役に立たないことも多い。
しかし、やはり本は重要な情報源だと思うし、図書館で読む本とお金を出して買う本は性質が異なると思うので、田舎であっても図書館は充実させるべきだと思う。都市と地方の情報格差を図書館が拡大しているようでは仕方ない。情報の少ない田舎だからこそ、図書館を充実させて新しい情報をどんどん取り入れるべきだ。これには、予算も比較的かからない。
蛇足だが、鹿児島で一番大きな図書館である鹿児島大学の図書館からも、先日ある本を取り寄せた。これも南さつま市で初めてのことだったらしいが、鹿児島大学から郵送料をなんと960円も取られた。郵送料が必要とは事前に聞いていたが、せいぜい300円くらいのものかと思っていた。鹿児島大学図書館は、第一義的には学生のためのものとはいえ、鹿児島県民の最後の砦となる図書館なのだから、もう少し利用しやすくなってもらいたいと思う。
2012年9月26日水曜日
島津家と修験道——大浦の宇留島家
 |
| 宇留島家の看経所 |
この宇留島家というのは、この大浦の地で代々島津家に仕えた修験者(山伏)の家であった。鹿児島はかつて修験道が盛んであり、特に南薩は金峰山を中心に修験の文化が色濃かったと考えられる。
鹿児島で修験道が盛んだった理由の一つに、藩主である島津家が山伏を重く用いたことがある。戦国期の島津家では政策や軍事の戦略を立てるのにクジ(御鬮)を使っていたが、クジを引くのは偶然に任せるのではなく神慮を得るためであり、宗教的な力が必要だった。そこでクジを引いたのが、その作法を心得ていた山伏だった。
戦の進退をクジで決めるというと、現代的観点からは非合理的に見えるが、私はそうでもないと思う。最適な戦略・戦術は事後的にしかわからないし、戦において冷静な判断は元より難しい。ましてや撤退の決定は非常に困難だ。また異論の出やすい戦場において、神慮の判断ならば反対派も黙らざるを得ない。そう考えると、重要な判断をクジに任すというのは、一見迷信的に見えて実は理に適っているのかもしれない。
しかも、山伏を軍事に活用するというのには実利もあっただろう。というのも、修験者は山林を跋渉して各国を渡っていたので、他国の事情にも詳しく人脈もあり、いわば一種のスパイとして活躍していたらしい。戦国期の関所とは国境であって、普通の人は自由に往来できなかったが、山伏はこれを自由に通行できた。『勧進帳』で源義経が山伏に偽装するのも、山伏は関所を通行できるという特権があったからである。しかも山伏は山中の行者道によって人知れず他国に移動することが可能で、密書一つ届けるにしても圧倒的に有利だ。
島津家が山伏を家老や老中として迎えたのは、戦勝祈願の霊験を得るためということ以上に、そういう山伏の持つネットワークを活用するためだったのではないかという気がする。宇留島家も土着の人間ではなく、千葉から南薩まで下向してきたらしい。
宇留島家は特に島津忠良(日新斎)の頃に重く用いられたが、それもある戦を契機としてのように思われる。忠良が1538年に加世田の別府城を攻めた際、宇留島十代東福坊重綱は山中で「三洛の秘法」とよばれる祈祷を行い、また忠良自身も久志地権現に籠もって戦勝を祈願した。その甲斐あってか別府城は落城。この戦いで加世田は島津家の支配に入り、同時にここ大浦も島津家の領地に組み込まれたようだ。この祈願の功により、東福坊は久志地権現、磯間権現等の別当職に任じられるとともに神田八町と宝物を下賜されている。
戦国期が終わり江戸時代に入ると、戦がなくなり島津家と修験者との関わりは希薄になっていく。宇留島家も島津家のために祈祷することはなくなるが、戦国期に得た八町(8ha)という広大な水田を経済力の源泉として、大浦でも有数の郷士となった。そして宇留島家は山伏として修行を続け、田畑の除虫祈祷や伊勢講の指導などを行い、庶民のための山伏としての性格を強めていった。
今ではこの地域に修験道の残映は感じることができないが、戦国から江戸期にかけて、修験道文化が色濃かったことは間違いない。修験の山である磯間嶽に向かい、かつて山伏が百姓を指導していたのかと思うと興味深い。
そういえば先日地域の古老から面白い話を聞いた。電話もなかった数十年前、うちの集落では地域の人への伝達事項がある時、合図として区長さん(集落のとりまとめ役)が法螺貝を吹いて知らせたのだそうだ。 これは、山伏がこの地域をまとめていたことの名残なのかもしれない。というのも、東福坊が下賜された神田八町の一部は、うちの集落の水田のようなのである。
【参考文献】
『さつま山伏 —山と湖の民俗と歴史—』 1996年、森田清美
『大浦町郷土誌』1995年、大浦町郷土誌編纂委員会
2012年9月15日土曜日
西欧近代農学小史
化学肥料も農薬も、トラクターもなかった頃の農業はどんなだっただろう? そして、現代農学の原型となっている西欧近代農学の成立はどんなだったのだろう? という興味から、『西欧古典農学の研究』(岩片 磯雄 著)という本を読んだ(※1)。
その内容はかなりマニアックだが、他では得られない情報をたくさん含んでいたので、備忘も兼ねて、ポイントをまとめてみたい。
さて、本書の対象となるのは18世紀初めから19世紀半ばのイギリスとドイツの農学であるが、その頃の農業先進国はなんといってもオランダであった。オランダでは既に低地の干拓を大規模に行っており、当時の新作物であったクローバーを導入した集約的な農業が行われていた。しかし海運の商業的成功による富のおかげで穀物は輸入に頼っており、農業がより集約性の高い畜産(チーズ作りなど)にシフトしていく趨勢もあった。そうした中で新興の農業国として勇躍するのがイギリスである。
イギリスの農民的地主であったジェスロ・タル(Jethro Tull)は、病気の治療のため訪れたヨーロッパ大陸において先進的農業を見、その経験に基づいて一連の農機を発明するとともに、イギリスで農業の新体系を構築した。タルの新農法の普及によってイギリスは農業生産性の飛躍的向上、つまり「農業革命」を成し遂げ、それによる人口増は産業革命の一因となったともいう。タルはしばしば「農業の発展に最も大きな影響を与えた人物」「近代農業の父」と言われる。
タルの新農法のポイントは、作付体系から休閑をなくしたことと、条播、中耕、そしてそのための機械化である。
その頃のヨーロッパでは中世以来の三圃制が行われていた。三圃制とは、圃場を3つに分け冬穀物−夏穀物−休閑のローテーションで耕作を行う体系であるが、これだと耕地の1/3は耕作をしないということで効率が悪い。そこで、この休閑をなくせないか? というのが西欧農学の発展の一つの軸になっていく。
では休閑をなぜ行うのだろうか? 歴史の教科書などには、「休耕地に放牧することで家畜の糞尿が肥料となり土地の力を回復させる」などと書いているが、これは正確ではない。元々の休閑とは、地力の回復ももちろんだが、同時に除草のためのものであった。当然除草剤などない時代なので、雑草は凄いことになっていたと思われる。しかも、当時は条播ではなく、散播(つまり畑に種をばらまく)であったため、人力による除草もしていなかったらしい。
となると、数年耕作すると雑草だらけになってしまいほとんど何も収穫できなくなってしまう。これを防ぐのが休閑の重要な目的なのだった。では休閑によってどのように除草するかというと、まず畑を放っておく。すると土中にある雑草の種が発芽し、やがて雑草が繁茂する。そこで乾燥した日などに草を刈ったり、棃耕(馬に棃を引かせて耕す)したりすると、雑草が枯れる。だが土中にはまだ発芽していない雑草の種があるので、また畑を放置し、雑草を敢えて生やしてから絶やし、棃耕する。これを何度か繰り返すとだんだん土中に含まれる雑草の種は減っていくわけだ。少なくとも4回、理想的には7回ほどこうしたことを繰り返すことで、雑草の種が含まれない清浄な畑になるらしいが、こうして穀作に備えたのが本来の休閑である。
つまり、本来の休閑とは何もしないのではなく、数次にわたる棃耕が必要な重労働なのだった。これをなんとかなくせないかと考えるのは当然だ。しかも、やがて人口増等によって家畜飼料等が足りなくなり、休閑地への放牧等が始まっていく。そうなると、当然棃耕も十分に行われなくなり、雑草の種が完全に排除されなくなる。この変容した休閑では本来の目的が達成できないので、その意味でも三圃制の変革が求められていたのだった。
これへのタルの解決策は、条播と中耕である。条播とは、線状に一定間隔で種を播くことで、中耕とは種を播いてからその周りを耕すことである。中世以来の散播を辞め、条播にしたことで播種後も圃場に入れるようにして中耕することで除草し、また(タルの理屈では)土を耕すことで地力を回復させた。またタルは休閑をなくすだけでなく、カブなどの根菜類やクローバーなどを導入し、冬穀物−カブ−夏穀物−クローバーというような休閑のない輪栽農法を確立させた。さらにこの農法のための畜力条播機、中耕機を発明し、農業全体を新しいものにつくりあげた。
またこの際、タルは植物の生理、栄養、土壌などの理論を反省して、いろいろな実験や観察を行い、総合的理論の上にこの農法を確立したのだが、それは「近代農学の父」と呼ぶにふさわしい。何より、数百年間無批判に行われてきた在来農法である三圃制を打ち破ったことは、タルの不朽の功績と言える。
タルはこれらを『新農法論』としてまとめ公刊するが、所詮は農民である彼の発案はそのままでは世の中に広まらなかった。その流布のきっかけとなったのがアーサー・ヤング(Arthur Young)による紹介である。ヤングはいわゆるジャーナリストだったが、農園を買って農業もやっていた。だが彼自身は農業では成功せず、3度も農園を変えて破産状態だったという。しかし農業に関する著作が売れたことで農学史に名を残すことになる。
彼はタルの農法を無批判に紹介したわけではなく、例えば条播や中耕の意義は認めなかったし、さらに一連の機械化に関しても批判的だった。ヤングとしては、昔ながらの散播なら種まき後は農民は何もやることがなく暇なのに、条播・中耕作業は大変だということ、さらに複雑な機械である条播機、中耕機の維持管理は無学な農民には不可能だ、というような考えだったようだ。にもかかわらず、ヤングは大規模経営の優越を説いているなど矛盾した部分があり、彼の言説は個人的にはあまり賛同できない部分が多いが、タルを始めとしたイギリス農民の叡智を体系化し、ヨーロッパ大陸に紹介・導入の契機となった功績は大きい。
そのヤングの著作を通して学び、近代的農業を確立したのがドイツのアルブレヒト・テーア(Albrecht Thaer)だ。医者だったテーアはイギリスの新農法に学び、それを科学的観点から批判検証し、単なる農法のみならず、いかにして農業経営において最高の収益を生み出せるかを考察した。その結果まとめられたのが大著『合理的農業の原理』(全4巻(※2))だ。
特にテーアの業績として重要なのが地力の源泉を土中の有機物に求めたことで、実はこれがタルとの決定的違いになる。タルは地力は耕すことによって増すと考え、休閑・放牧によって家畜糞尿を投入しなくても中耕によって地力は維持しうると考えたのだが、テーアは畑に有機物を投入することが重要であると説いた。これは、後にリービッヒにより窒素・リン酸・カリの肥料の3要素説で一応否定されることになるが、むしろ現代に至って有機物の重要性が再認識されており、ここに近代的な土壌学が開始されたと言える。
これ以外にも、テーアは近代農業を成立させるための様々な前提について考察した。例えば、土地の私有権、賦役労働の禁止、生産物販売の流通、農業経営のための固定資本と流動資本、農業経営への簿記の導入などだ。テーアの考察は非常に現代的であり、約200年前の著作であるにもかかわらず、現代においてもその意義は色褪せていない。「農業と工業の間には本質的に区別されるべきなんらの相違もない」といった彼の言葉は色褪せないどころか、現代においても十分に過激である。またテーアはプロシアの農政改革に参与し、ドイツの農業を封建的農業から資本主義的農業への転換を成し遂げた立役者でもある。
なお、これまで触れていなかったが、タルから続く西欧の農業の革命の背景には、地主−小作人という封建的関係の解消と近代資本主義の成立がある。ちょうどタルの頃、封建領主による閉鎖的かつ分散的な農業社会が解体し、囲い込みなどによって農地が集約化され、共同地が解消されて私有地に分割されるといった社会の激変があった。また、次第に土地所有と経営の分離が起こり、農業の目的が地代収入ではなく、収益の最大化へと変化していく。それに伴って、かつての農書は地主が小作人管理のために読むものだったが、次第に耕作者本人が読むものへと変化していく。地主に隷属した小作人から、独立した農業経営者が出現、同時に封建的地主からは資本家が出現するのである。それが、タルから続く農学の発展の原動力ともなっている。
最後に、テーアに対する論理的批判者として現れるのがヨハン・ハインリヒ・チューネン(Johann Heinrich von Thünen)である。彼は経済学者・地理学者であったが、自ら農園を経営し、詳細な経営記録をつけた結果、テーアの理論と相違が出てくる部分があったのでそれを理論化するとともに経済学的分析を行い、『孤立国』という本にまとめて公刊した。その批判点や主張はあまりに学問的なのでここでは触れないが、これにより農業が経済学に組み込まれて分析されることになった功績は大きい。
化学肥料・農薬の登場前夜であるこの時代の農学史を通して思うのは、これらの農業改革において病害虫の被害への対応の観点がほぼ全くと言っていいほどないことだ。アイルランドのジャガイモ飢饉は1845年からで彼らの活躍した時代より少しだけ後になるが、それまでも作物の大規模な病害虫被害はあったのだと思う。ただ、それに対処する方法がなかったから彼らは考察のしようがなかったのかもしれない。
20世紀に入って、化学肥料と農薬の開発、そしてトラクター等の燃料機械の開発で農業は抜本的に変わっていく。それまでは病害虫の忌避は基本的に輪作体系によって行われていたらしいが、土壌燻蒸剤の開発によって連作が可能になり、肥料の大量投入と除草剤の使用によって休閑も必要なくなった。しかし、農学の基礎は19世紀に確立しており、それを学ぶことは現代的な意義もある。別に取り立てて化学肥料や農薬を敵視するわけではないが、それ以前の農業の基本がこの時代の農学にはあるように思う。
こうなってくると俄然興味が出てくるのが江戸時代の日本の農書である。だが一書一書を読むような好事家ではないので、何かいい参考資料を探したいと思っている。
※1 Amazonで検索すると古本で1万円以上する高価な本。近所の図書館の廃棄処分に出ていたのをタダでもらってきた。
※2 日本語版だと3冊になっているが、原著は4巻本。
その内容はかなりマニアックだが、他では得られない情報をたくさん含んでいたので、備忘も兼ねて、ポイントをまとめてみたい。
さて、本書の対象となるのは18世紀初めから19世紀半ばのイギリスとドイツの農学であるが、その頃の農業先進国はなんといってもオランダであった。オランダでは既に低地の干拓を大規模に行っており、当時の新作物であったクローバーを導入した集約的な農業が行われていた。しかし海運の商業的成功による富のおかげで穀物は輸入に頼っており、農業がより集約性の高い畜産(チーズ作りなど)にシフトしていく趨勢もあった。そうした中で新興の農業国として勇躍するのがイギリスである。
イギリスの農民的地主であったジェスロ・タル(Jethro Tull)は、病気の治療のため訪れたヨーロッパ大陸において先進的農業を見、その経験に基づいて一連の農機を発明するとともに、イギリスで農業の新体系を構築した。タルの新農法の普及によってイギリスは農業生産性の飛躍的向上、つまり「農業革命」を成し遂げ、それによる人口増は産業革命の一因となったともいう。タルはしばしば「農業の発展に最も大きな影響を与えた人物」「近代農業の父」と言われる。
タルの新農法のポイントは、作付体系から休閑をなくしたことと、条播、中耕、そしてそのための機械化である。
その頃のヨーロッパでは中世以来の三圃制が行われていた。三圃制とは、圃場を3つに分け冬穀物−夏穀物−休閑のローテーションで耕作を行う体系であるが、これだと耕地の1/3は耕作をしないということで効率が悪い。そこで、この休閑をなくせないか? というのが西欧農学の発展の一つの軸になっていく。
では休閑をなぜ行うのだろうか? 歴史の教科書などには、「休耕地に放牧することで家畜の糞尿が肥料となり土地の力を回復させる」などと書いているが、これは正確ではない。元々の休閑とは、地力の回復ももちろんだが、同時に除草のためのものであった。当然除草剤などない時代なので、雑草は凄いことになっていたと思われる。しかも、当時は条播ではなく、散播(つまり畑に種をばらまく)であったため、人力による除草もしていなかったらしい。
となると、数年耕作すると雑草だらけになってしまいほとんど何も収穫できなくなってしまう。これを防ぐのが休閑の重要な目的なのだった。では休閑によってどのように除草するかというと、まず畑を放っておく。すると土中にある雑草の種が発芽し、やがて雑草が繁茂する。そこで乾燥した日などに草を刈ったり、棃耕(馬に棃を引かせて耕す)したりすると、雑草が枯れる。だが土中にはまだ発芽していない雑草の種があるので、また畑を放置し、雑草を敢えて生やしてから絶やし、棃耕する。これを何度か繰り返すとだんだん土中に含まれる雑草の種は減っていくわけだ。少なくとも4回、理想的には7回ほどこうしたことを繰り返すことで、雑草の種が含まれない清浄な畑になるらしいが、こうして穀作に備えたのが本来の休閑である。
つまり、本来の休閑とは何もしないのではなく、数次にわたる棃耕が必要な重労働なのだった。これをなんとかなくせないかと考えるのは当然だ。しかも、やがて人口増等によって家畜飼料等が足りなくなり、休閑地への放牧等が始まっていく。そうなると、当然棃耕も十分に行われなくなり、雑草の種が完全に排除されなくなる。この変容した休閑では本来の目的が達成できないので、その意味でも三圃制の変革が求められていたのだった。
これへのタルの解決策は、条播と中耕である。条播とは、線状に一定間隔で種を播くことで、中耕とは種を播いてからその周りを耕すことである。中世以来の散播を辞め、条播にしたことで播種後も圃場に入れるようにして中耕することで除草し、また(タルの理屈では)土を耕すことで地力を回復させた。またタルは休閑をなくすだけでなく、カブなどの根菜類やクローバーなどを導入し、冬穀物−カブ−夏穀物−クローバーというような休閑のない輪栽農法を確立させた。さらにこの農法のための畜力条播機、中耕機を発明し、農業全体を新しいものにつくりあげた。
またこの際、タルは植物の生理、栄養、土壌などの理論を反省して、いろいろな実験や観察を行い、総合的理論の上にこの農法を確立したのだが、それは「近代農学の父」と呼ぶにふさわしい。何より、数百年間無批判に行われてきた在来農法である三圃制を打ち破ったことは、タルの不朽の功績と言える。
タルはこれらを『新農法論』としてまとめ公刊するが、所詮は農民である彼の発案はそのままでは世の中に広まらなかった。その流布のきっかけとなったのがアーサー・ヤング(Arthur Young)による紹介である。ヤングはいわゆるジャーナリストだったが、農園を買って農業もやっていた。だが彼自身は農業では成功せず、3度も農園を変えて破産状態だったという。しかし農業に関する著作が売れたことで農学史に名を残すことになる。
彼はタルの農法を無批判に紹介したわけではなく、例えば条播や中耕の意義は認めなかったし、さらに一連の機械化に関しても批判的だった。ヤングとしては、昔ながらの散播なら種まき後は農民は何もやることがなく暇なのに、条播・中耕作業は大変だということ、さらに複雑な機械である条播機、中耕機の維持管理は無学な農民には不可能だ、というような考えだったようだ。にもかかわらず、ヤングは大規模経営の優越を説いているなど矛盾した部分があり、彼の言説は個人的にはあまり賛同できない部分が多いが、タルを始めとしたイギリス農民の叡智を体系化し、ヨーロッパ大陸に紹介・導入の契機となった功績は大きい。
そのヤングの著作を通して学び、近代的農業を確立したのがドイツのアルブレヒト・テーア(Albrecht Thaer)だ。医者だったテーアはイギリスの新農法に学び、それを科学的観点から批判検証し、単なる農法のみならず、いかにして農業経営において最高の収益を生み出せるかを考察した。その結果まとめられたのが大著『合理的農業の原理』(全4巻(※2))だ。
特にテーアの業績として重要なのが地力の源泉を土中の有機物に求めたことで、実はこれがタルとの決定的違いになる。タルは地力は耕すことによって増すと考え、休閑・放牧によって家畜糞尿を投入しなくても中耕によって地力は維持しうると考えたのだが、テーアは畑に有機物を投入することが重要であると説いた。これは、後にリービッヒにより窒素・リン酸・カリの肥料の3要素説で一応否定されることになるが、むしろ現代に至って有機物の重要性が再認識されており、ここに近代的な土壌学が開始されたと言える。
これ以外にも、テーアは近代農業を成立させるための様々な前提について考察した。例えば、土地の私有権、賦役労働の禁止、生産物販売の流通、農業経営のための固定資本と流動資本、農業経営への簿記の導入などだ。テーアの考察は非常に現代的であり、約200年前の著作であるにもかかわらず、現代においてもその意義は色褪せていない。「農業と工業の間には本質的に区別されるべきなんらの相違もない」といった彼の言葉は色褪せないどころか、現代においても十分に過激である。またテーアはプロシアの農政改革に参与し、ドイツの農業を封建的農業から資本主義的農業への転換を成し遂げた立役者でもある。
なお、これまで触れていなかったが、タルから続く西欧の農業の革命の背景には、地主−小作人という封建的関係の解消と近代資本主義の成立がある。ちょうどタルの頃、封建領主による閉鎖的かつ分散的な農業社会が解体し、囲い込みなどによって農地が集約化され、共同地が解消されて私有地に分割されるといった社会の激変があった。また、次第に土地所有と経営の分離が起こり、農業の目的が地代収入ではなく、収益の最大化へと変化していく。それに伴って、かつての農書は地主が小作人管理のために読むものだったが、次第に耕作者本人が読むものへと変化していく。地主に隷属した小作人から、独立した農業経営者が出現、同時に封建的地主からは資本家が出現するのである。それが、タルから続く農学の発展の原動力ともなっている。
最後に、テーアに対する論理的批判者として現れるのがヨハン・ハインリヒ・チューネン(Johann Heinrich von Thünen)である。彼は経済学者・地理学者であったが、自ら農園を経営し、詳細な経営記録をつけた結果、テーアの理論と相違が出てくる部分があったのでそれを理論化するとともに経済学的分析を行い、『孤立国』という本にまとめて公刊した。その批判点や主張はあまりに学問的なのでここでは触れないが、これにより農業が経済学に組み込まれて分析されることになった功績は大きい。
化学肥料・農薬の登場前夜であるこの時代の農学史を通して思うのは、これらの農業改革において病害虫の被害への対応の観点がほぼ全くと言っていいほどないことだ。アイルランドのジャガイモ飢饉は1845年からで彼らの活躍した時代より少しだけ後になるが、それまでも作物の大規模な病害虫被害はあったのだと思う。ただ、それに対処する方法がなかったから彼らは考察のしようがなかったのかもしれない。
20世紀に入って、化学肥料と農薬の開発、そしてトラクター等の燃料機械の開発で農業は抜本的に変わっていく。それまでは病害虫の忌避は基本的に輪作体系によって行われていたらしいが、土壌燻蒸剤の開発によって連作が可能になり、肥料の大量投入と除草剤の使用によって休閑も必要なくなった。しかし、農学の基礎は19世紀に確立しており、それを学ぶことは現代的な意義もある。別に取り立てて化学肥料や農薬を敵視するわけではないが、それ以前の農業の基本がこの時代の農学にはあるように思う。
こうなってくると俄然興味が出てくるのが江戸時代の日本の農書である。だが一書一書を読むような好事家ではないので、何かいい参考資料を探したいと思っている。
※1 Amazonで検索すると古本で1万円以上する高価な本。近所の図書館の廃棄処分に出ていたのをタダでもらってきた。
※2 日本語版だと3冊になっているが、原著は4巻本。
2012年9月14日金曜日
農業の技術と知識をどのように身につけるか
先日の研修旅行で、ある農家から言われた言葉が引っかかっている。
「引退するまで、あと何回植え付けて収穫ができるか考えないといけないよ。30年あっても30回しかできないんだから。」それは、向上の機会は限られているという意味なんだろうと思う。 だから、1年1年の作付けをしっかりしろというメッセージだと受け取った。
ただ、それは他の仕事でも同じことだ。例えば「概算要求」は役人の(役所的に)最も重要な仕事の一つで年に1回限りだ(補正予算は除く)。しかし「役人人生であと何回概算要求できるか考えないといけない」なんて言葉はついぞ聞いたことがない。どうしてだろう? その答えは簡単で、長い役所の歴史を通じて「概算要求のやり方」が確立しているからである(それがいいか悪いかは別として。というか多分悪いやり方が確立しているのだが)。
では、なぜ農業では1年1年の作付けを向上の機会として、工夫しなくてはならないのか。別の言葉で言えば、なぜ農業には常道が確立していないのか? 数千年続いている事業なのにもかかわらず、その知識と技術はどうして普遍化しないのだろう? 地域ごとに気候が様々だから、水利や土地利用は地域ごとに違うから、毎年新しい機械や肥料や農薬が出て日進月歩だから。そういう理由は当然あると思う。
しかし最も大きな理由は、 農業が家系的に担われていたからではなかろうか。技術の継承がほとんど家系的にしか行われず、せいぜい地域内での共有に基づいているため、技術と知識は体系化・普遍化しづらく、またその必要もなかったのだろう。
だが時代は変わり、農業の担い手の確保が問題になっている。新規就農にあたってのハードルはたくさんあるが、農業の技術と知識をどのように身につけるかもその一つだ。私は他分野については本から学ぶことが多いが、農業のハウツー本にはほとんどまともな説明がない。まず、どのような道具を揃えるのかという記載がないことが多く、「○月に播種する」「○月に中耕する」といったことが羅列されるだけで、その作業をどのように行うのかに言及されていないこともよくある。つまりは、実践的ではない。同じ播種でもやり方次第でいろいろな結果になると思うのだが。
だが一番の問題は、それが基本的なやり方を教えるだけで、応用は読者に委ねられていることだ。気候や条件は様々なので、農業は基本的に全てが応用だが、そのノウハウは本には書いておらず、経験者の頭の中にしかないのである。
これは何も新規就農の時だけの話ではなく、新しい農機、種苗、農薬の導入などにあたっては各農家が頭を悩まされているところだと思う。
そこでふと思ったのだが、「Yahoo! 知恵袋」とか「OKWave」のようなQ&Aサイトで、農家同士が質問・回答し合うような仕組みはできないものだろうか。いわば同業他社にあたる他の農家にわざわざノウハウを開陳するような農家がいるかどうかはよくわからないが、例えば回答すればポイントが溜まるようにして、ポイントに特典が付くようにすれば協力してくれるかもしれない。運営費用は農機メーカーや資材メーカーからの広告費等でまかなえばよい。
新しい種類の農機なども、開発されてもすぐには普及しないことが多い。周りの農家が実際に使っている様子を見て購入を検討する、というのが一般的だと思うが、こうしたサイトがあればその農機を使った人の声を聞くことができ購入の参考となるから、農機メーカーとしても有り難いのではないだろうか。
なお、以前OKWaveは「教えて!農業」というこのようなサイトを運営していたが、今年6月に閉鎖している(理由は不明)。
農業と同様に個人で活動することが多いITエンジニアの場合、ノウハウを教え合うことが普通であり、こうした教え合いサイトも多い。だから、「教えて!農業」は成功しなかったようだが、農業も工夫すれば技術と知識の普遍化をしていくことが出来ると思うし、そうすれば新規参入のハードルを一つ取り除くことになる。そしてそれ以上に、農業を形式知化することによって、さらなる効率化と農家全体の技術の向上が図られるはずだ。
なんでも本やインターネットで学べるようになるわけはないが、農業が本当に日進月歩なら、農家のネットワークによって技術と知識を向上させていくことが必要なのではないかと感じた次第である。
「引退するまで、あと何回植え付けて収穫ができるか考えないといけないよ。30年あっても30回しかできないんだから。」それは、向上の機会は限られているという意味なんだろうと思う。 だから、1年1年の作付けをしっかりしろというメッセージだと受け取った。
ただ、それは他の仕事でも同じことだ。例えば「概算要求」は役人の(役所的に)最も重要な仕事の一つで年に1回限りだ(補正予算は除く)。しかし「役人人生であと何回概算要求できるか考えないといけない」なんて言葉はついぞ聞いたことがない。どうしてだろう? その答えは簡単で、長い役所の歴史を通じて「概算要求のやり方」が確立しているからである(それがいいか悪いかは別として。というか多分悪いやり方が確立しているのだが)。
では、なぜ農業では1年1年の作付けを向上の機会として、工夫しなくてはならないのか。別の言葉で言えば、なぜ農業には常道が確立していないのか? 数千年続いている事業なのにもかかわらず、その知識と技術はどうして普遍化しないのだろう? 地域ごとに気候が様々だから、水利や土地利用は地域ごとに違うから、毎年新しい機械や肥料や農薬が出て日進月歩だから。そういう理由は当然あると思う。
しかし最も大きな理由は、 農業が家系的に担われていたからではなかろうか。技術の継承がほとんど家系的にしか行われず、せいぜい地域内での共有に基づいているため、技術と知識は体系化・普遍化しづらく、またその必要もなかったのだろう。
だが時代は変わり、農業の担い手の確保が問題になっている。新規就農にあたってのハードルはたくさんあるが、農業の技術と知識をどのように身につけるかもその一つだ。私は他分野については本から学ぶことが多いが、農業のハウツー本にはほとんどまともな説明がない。まず、どのような道具を揃えるのかという記載がないことが多く、「○月に播種する」「○月に中耕する」といったことが羅列されるだけで、その作業をどのように行うのかに言及されていないこともよくある。つまりは、実践的ではない。同じ播種でもやり方次第でいろいろな結果になると思うのだが。
だが一番の問題は、それが基本的なやり方を教えるだけで、応用は読者に委ねられていることだ。気候や条件は様々なので、農業は基本的に全てが応用だが、そのノウハウは本には書いておらず、経験者の頭の中にしかないのである。
これは何も新規就農の時だけの話ではなく、新しい農機、種苗、農薬の導入などにあたっては各農家が頭を悩まされているところだと思う。
そこでふと思ったのだが、「Yahoo! 知恵袋」とか「OKWave」のようなQ&Aサイトで、農家同士が質問・回答し合うような仕組みはできないものだろうか。いわば同業他社にあたる他の農家にわざわざノウハウを開陳するような農家がいるかどうかはよくわからないが、例えば回答すればポイントが溜まるようにして、ポイントに特典が付くようにすれば協力してくれるかもしれない。運営費用は農機メーカーや資材メーカーからの広告費等でまかなえばよい。
新しい種類の農機なども、開発されてもすぐには普及しないことが多い。周りの農家が実際に使っている様子を見て購入を検討する、というのが一般的だと思うが、こうしたサイトがあればその農機を使った人の声を聞くことができ購入の参考となるから、農機メーカーとしても有り難いのではないだろうか。
なお、以前OKWaveは「教えて!農業」というこのようなサイトを運営していたが、今年6月に閉鎖している(理由は不明)。
農業と同様に個人で活動することが多いITエンジニアの場合、ノウハウを教え合うことが普通であり、こうした教え合いサイトも多い。だから、「教えて!農業」は成功しなかったようだが、農業も工夫すれば技術と知識の普遍化をしていくことが出来ると思うし、そうすれば新規参入のハードルを一つ取り除くことになる。そしてそれ以上に、農業を形式知化することによって、さらなる効率化と農家全体の技術の向上が図られるはずだ。
なんでも本やインターネットで学べるようになるわけはないが、農業が本当に日進月歩なら、農家のネットワークによって技術と知識を向上させていくことが必要なのではないかと感じた次第である。
2012年9月13日木曜日
笠沙野間池の定置網観光
一行は福岡からいらっしゃったが、巡るのは南薩の地元だから私たちにとっては旅行という感じではないけれども、大変貴重な経験をさせていただいたと思う。ベテラン農家の方々ともう少し意見交換できればという不完全燃焼感はあったし、やはり圃場を実際に見てみないとよくわからないことが多かったように思うが、それでも他地域の専業農家の雰囲気を掴むのにはよかった。
ところで、この研修旅行では笠沙の野間池にある網元が経営する舟宿「のま池」に泊まったが、ここでは定置網観光ができる。要は定置網漁に同行できてその様子を見ることができるのだが、今回それを体験させていただいた(追加料金を払えば定置網にかかった魚も購入できる)。
舟には、かごしま水族館の方も乗船していた。定期的に漁船に乗せてもらい、どのような魚がどれくらい獲れているかを記録して、また水族館として欲しい魚が獲れれば譲ってもらうということなのだそうだ。
ちなみに、葛西臨海公園を始めとして、全国の多くの水族館が笠沙漁協から展示飼育用の魚を調達している。時には外国の水族館にも提供するらしい。その理由としては、第1に黒潮に乗って遠方の海からもたくさんの魚が集まり、年間500種もの魚が水揚げされるという笠沙の海の多様性が挙げられる。そして第2に、笠沙漁協は水族館の活動に対して理解があり、水族館へ魚を提供したり調査員を受け入れたりする体制が整っているということもあるのだそうだ。確かに、漁協の協力が得られなくては傷のない元気な魚を調達するのは困難だ。
出航は朝5時45分。海は凪ぎ。天候は快晴。漁船で野間半島を巡って定置網のポイントへ行き、漁師が網をたぐり寄せて網中の魚を追い込み、最後はタモで掬う。約1mくらいのバショウカジキが1匹、サワラが幾ばくか、大量のトビウオ、そしてアオウミガメが2匹 etc.。それが今回の成果(釣果?)だった。ちなみに、ウミガメは調査用のタグをつけて海に戻す。
この「のま池」の定置網はなんと明治のころから設置されており、百年以上の歴史があるのだそうだ。もちろん網自体は定期的に交換しているわけだし、そのやり方も機械化に伴ってどんどん変わってきたのだろうが、作業を見ると極めて合理化されていて、船員の動きには全く無駄がなく、軽々と作業しているように見えた。長い歴史に裏打ちされた作業という感じがする。流れ作業的になってしまって工夫の余地がなくなってしまうと面白くないのかもしれないけれど、仕事は、こういう風にこなしたいものだと思った。
2012年9月10日月曜日
一品種のスーパーマーケット:四角豆
ようやく四角豆が収穫できるようになった。
四角豆は、本土ではあまりなじみがないが、沖縄料理では「うりずん」とか「シカクマーミー」と言われて親しみのある食材。切り口が四角なので四角豆の呼び名がある。
原産はニューギニアで、耐暑性に優れ赤道直下の気候でもよく育つ上、大豆と同様タンパク質やビタミンが豊富で栄養素に富むことから、熱帯の国々ではメジャーな食材らしい。さらに、害虫や病気も深刻な被害を及ぼすことはなく、無農薬での栽培が容易だ。
しかも、英語で俗に「one species supermarket(一品種のスーパーマーケット)」というように、豆のみならず、根、葉、花など茎を除く植物体全てが可食で、いろいろな利用が可能である。特に根はイモ状になり、ジャガイモに似た味がして豆よりうまいらしい。葉は熱帯植物としては最高レベルのビタミンAを有するし、種を乾燥させるとコーヒーのような飲み物になるということだ。
豆は、若いサヤを食べるのだが、味を楽しむというよりパキッとした歯ごたえを楽しむ野菜で、あっさりとしていて味付けしやすいので、サラダなどにはちょうどいいと思う。一番美味しいのは天ぷらで、パキッとした四角豆をカリッと揚げれば最高だ。
栽培は容易と聞いていたが、今年は雨が異常に多かったせいか開花・着果が悪く、本来7月末には収穫可能になる予定が9月までずれ込み、さらに着果量も想定より少なく当てが大きく外れているが、例によって「大浦ふるさと館」で多少売ってみたい。
ちなみに、インターネットで検索すると、四角豆のレシピとしてカレーがけっこう多く出てきた(英語)。まだカレーにして食べてみたことはないが、イケるのだろうか。ちなみに、スライスした四角豆を茹でて冷やして冷やし中華に入れてみたが、麺に絡めて食べるとうまかった。
四角豆は、本土ではあまりなじみがないが、沖縄料理では「うりずん」とか「シカクマーミー」と言われて親しみのある食材。切り口が四角なので四角豆の呼び名がある。
原産はニューギニアで、耐暑性に優れ赤道直下の気候でもよく育つ上、大豆と同様タンパク質やビタミンが豊富で栄養素に富むことから、熱帯の国々ではメジャーな食材らしい。さらに、害虫や病気も深刻な被害を及ぼすことはなく、無農薬での栽培が容易だ。
しかも、英語で俗に「one species supermarket(一品種のスーパーマーケット)」というように、豆のみならず、根、葉、花など茎を除く植物体全てが可食で、いろいろな利用が可能である。特に根はイモ状になり、ジャガイモに似た味がして豆よりうまいらしい。葉は熱帯植物としては最高レベルのビタミンAを有するし、種を乾燥させるとコーヒーのような飲み物になるということだ。
豆は、若いサヤを食べるのだが、味を楽しむというよりパキッとした歯ごたえを楽しむ野菜で、あっさりとしていて味付けしやすいので、サラダなどにはちょうどいいと思う。一番美味しいのは天ぷらで、パキッとした四角豆をカリッと揚げれば最高だ。
栽培は容易と聞いていたが、今年は雨が異常に多かったせいか開花・着果が悪く、本来7月末には収穫可能になる予定が9月までずれ込み、さらに着果量も想定より少なく当てが大きく外れているが、例によって「大浦ふるさと館」で多少売ってみたい。
ちなみに、インターネットで検索すると、四角豆のレシピとしてカレーがけっこう多く出てきた(英語)。まだカレーにして食べてみたことはないが、イケるのだろうか。ちなみに、スライスした四角豆を茹でて冷やして冷やし中華に入れてみたが、麺に絡めて食べるとうまかった。
2012年9月8日土曜日
南さつま市定住化促進検討委員会(その2)
南さつま市定住化促進検討委員会の第2回が開催された。
前回の議論に基づき、市役所の企画課の方が対象者(若者世代、子育て世代、高齢者世代)ごとの定住化促進施策案を作ってきてくれ、それに基づいて議論することとなった。
が、市役所の方も仰っていたとおり、その案がどうも平凡で他の自治体と変わりばえがなく、仮にその全てを実施してもあまり効果がないような感じだった。そこで以前ブログに書いたように「対象を起業家に絞ってはどうか?」という意見を表明したところ、ある程度賛同が得られたのか、委員からは「テーマ性を持って移住定住を勧めるべき」「南さつまの売りを明確にした施策が必要」といった意見が出されたが、事務局(市役所)の反応が悪い。
どうも、「中心となる施策はあるべきだが、まず全体的に移住定住促進のための施策群を検討してから、それをまとめて売り出せばよい」ということのようで、私がいうのもなんだが役所的な考え方で残念だ。
確かに、ここで「南さつまは海がきれいだから、ダイバーにターゲットを絞った施策を考えよう!」とすると、「なんで山じゃないのか?」とかいろいろ異論は出てくる。あまりにも異論が出るような絞り方はしない方がいいのは当たり前だ。だが、他の自治体もやっているような施策ばかりでは、効果がないのも自明であり、異論もないが効果がないのでは税金の無駄遣いになる。
そもそも「南さつまの売りを明確にした施策を」という当然の意見に対しても、市役所においては「南さつま市の売り」がなんなのか明確ではないようだ。加世田時代は「砂丘と自転車の街」というキャッチコピーがあったようだが、合併して南さつま市になってこれが使えなくなり、どうも「南さつま市の売り」はまだ真面目に検討されていないように見える。
金峰山と米どころの神話の里「金峰」、広い平野と武家屋敷が残る中心地「加世田」、亀ヶ丘からの眺望と干拓の「大浦」、素晴らしい海と絶景の「笠沙」、歴史ある港町「坊津」。それぞれの良さや特色はあるが、「南さつま」全体として見た時、どのような魅力があるのか未だ明確でない。
役所的にまとめれば、各地域に配慮した無難なキャッチコピーはできるのだろうが、それでは面白くない。「これなら南さつま市が日本一」というような売り込み方をしてもらいたいと思う。そして、これは市の広報全ての話ではなくて、「移住・定住希望者に何を売り込むか」という話なのだから、過度に各地域・産業に配慮したものである必要はないと思う。
鹿児島に移住してきて笠沙に海来館をオープンさせた委員のI氏が「ワクワクするような施策を!」と言っていたが、まさにその通りで、住民がワクワクしないような施策であれば、部外者がワクワクするわけはなく、移住など進むはずがないと思うのである。無難にまとめるのではなく、「何か新しいことが始まるぞ」という期待感を持てるような方向になってもらいたい。
前回の議論に基づき、市役所の企画課の方が対象者(若者世代、子育て世代、高齢者世代)ごとの定住化促進施策案を作ってきてくれ、それに基づいて議論することとなった。
が、市役所の方も仰っていたとおり、その案がどうも平凡で他の自治体と変わりばえがなく、仮にその全てを実施してもあまり効果がないような感じだった。そこで以前ブログに書いたように「対象を起業家に絞ってはどうか?」という意見を表明したところ、ある程度賛同が得られたのか、委員からは「テーマ性を持って移住定住を勧めるべき」「南さつまの売りを明確にした施策が必要」といった意見が出されたが、事務局(市役所)の反応が悪い。
どうも、「中心となる施策はあるべきだが、まず全体的に移住定住促進のための施策群を検討してから、それをまとめて売り出せばよい」ということのようで、私がいうのもなんだが役所的な考え方で残念だ。
確かに、ここで「南さつまは海がきれいだから、ダイバーにターゲットを絞った施策を考えよう!」とすると、「なんで山じゃないのか?」とかいろいろ異論は出てくる。あまりにも異論が出るような絞り方はしない方がいいのは当たり前だ。だが、他の自治体もやっているような施策ばかりでは、効果がないのも自明であり、異論もないが効果がないのでは税金の無駄遣いになる。
そもそも「南さつまの売りを明確にした施策を」という当然の意見に対しても、市役所においては「南さつま市の売り」がなんなのか明確ではないようだ。加世田時代は「砂丘と自転車の街」というキャッチコピーがあったようだが、合併して南さつま市になってこれが使えなくなり、どうも「南さつま市の売り」はまだ真面目に検討されていないように見える。
金峰山と米どころの神話の里「金峰」、広い平野と武家屋敷が残る中心地「加世田」、亀ヶ丘からの眺望と干拓の「大浦」、素晴らしい海と絶景の「笠沙」、歴史ある港町「坊津」。それぞれの良さや特色はあるが、「南さつま」全体として見た時、どのような魅力があるのか未だ明確でない。
役所的にまとめれば、各地域に配慮した無難なキャッチコピーはできるのだろうが、それでは面白くない。「これなら南さつま市が日本一」というような売り込み方をしてもらいたいと思う。そして、これは市の広報全ての話ではなくて、「移住・定住希望者に何を売り込むか」という話なのだから、過度に各地域・産業に配慮したものである必要はないと思う。
鹿児島に移住してきて笠沙に海来館をオープンさせた委員のI氏が「ワクワクするような施策を!」と言っていたが、まさにその通りで、住民がワクワクしないような施策であれば、部外者がワクワクするわけはなく、移住など進むはずがないと思うのである。無難にまとめるのではなく、「何か新しいことが始まるぞ」という期待感を持てるような方向になってもらいたい。
枇杷茶をつくってみました
庭にあるビワを思い切ってかなり剪定したので、それで出たビワの葉を使って枇杷茶を作ってみた。無農薬のビワだからお茶にするには最適だ。
枇杷茶は古くからの健康飲料で、癌の予防を始め、ダイエット効果や疲労回復効果などがあると言われており、医療関係者にも愛飲している人が多いと聞く。それに健康茶にありがちなえぐみや臭みなどは全くなく、あっさりとしていてクセがない上品な味がする。
普通の枇杷茶は、ビワの葉をただ乾燥させるだけだが、せっかくなので本格的に作ろうと思い、発酵もさせてみた。といってもビニール袋に入れて生暖かい場所に置いておくだけで、本当に「発酵」(つまり乳酸菌等の繁殖)なのかどうかは不明。というか多分違う(※)。ただ、発酵中はビワの葉からまさにビワの果実の芳醇な香りがしてきて、葉っぱしか入っていないのが信じられないくらいだった。それでどれくらい味が向上しているのかはわからないが…。
ところで、鹿児島では「ねじめびわ茶」というのが有名で、けっこう高く売られている。50gで800円くらいだろうか。根占では枇杷茶用にビワを栽培していて、葉に栄養を集中させるために敢えて実を付けない栽培も行っているらしく、果実の副産物ではないからこの価格になるのだろう。
それに、作ってみて思ったが、最初は膨大にあると思われたビワの葉も、虫食いや病気の葉を取り除いたり、発酵・乾燥させるうちにどんどん嵩が減っていって、最終的に茶葉になったのはたったの600gしかなかった。枇杷茶は作るのに手間のかからないお茶と思われているが、真面目にやろうとすると実は効率が悪いようだ。
ちなみに、せっかく作ったので、ラベルも作り袋に入れて、「大浦ふるさと館」に置かせてもらうことにした。50gで200円。ちなみに、私自身は「健康になるから飲もう!」というアピールは好きではなく、あくまで美味しいから飲むというのが王道だと思うので、ラベルには「健康飲料」の文字は入れなかった。ねじめびわ茶も美味しいと思うが、先日ペットボトルのねじめびわ茶を飲んでみたら、それよりはうちの枇杷茶をちゃんと淹れて飲んだ方が美味しいと思ったのでお試しあれ。
※ 緑茶の製作工程でも「発酵」という言葉が使われるが、これは業界用語で「発酵」と言っているだけで本当の「発酵」ではない。乳酸菌や酵母は緑茶の製造には関与していない。では科学的にはなんなのかというと、実は「酸化」なのだ。緑茶には「酸化酵素」というのがあって、これが茶葉を酸化させて味が変わるのである。でも「酸化」というとどうしてもマイナスのイメージがあることと、昔からの慣例で、「発酵」という言葉が使われている。
枇杷茶は古くからの健康飲料で、癌の予防を始め、ダイエット効果や疲労回復効果などがあると言われており、医療関係者にも愛飲している人が多いと聞く。それに健康茶にありがちなえぐみや臭みなどは全くなく、あっさりとしていてクセがない上品な味がする。
普通の枇杷茶は、ビワの葉をただ乾燥させるだけだが、せっかくなので本格的に作ろうと思い、発酵もさせてみた。といってもビニール袋に入れて生暖かい場所に置いておくだけで、本当に「発酵」(つまり乳酸菌等の繁殖)なのかどうかは不明。というか多分違う(※)。ただ、発酵中はビワの葉からまさにビワの果実の芳醇な香りがしてきて、葉っぱしか入っていないのが信じられないくらいだった。それでどれくらい味が向上しているのかはわからないが…。
ところで、鹿児島では「ねじめびわ茶」というのが有名で、けっこう高く売られている。50gで800円くらいだろうか。根占では枇杷茶用にビワを栽培していて、葉に栄養を集中させるために敢えて実を付けない栽培も行っているらしく、果実の副産物ではないからこの価格になるのだろう。
それに、作ってみて思ったが、最初は膨大にあると思われたビワの葉も、虫食いや病気の葉を取り除いたり、発酵・乾燥させるうちにどんどん嵩が減っていって、最終的に茶葉になったのはたったの600gしかなかった。枇杷茶は作るのに手間のかからないお茶と思われているが、真面目にやろうとすると実は効率が悪いようだ。
ちなみに、せっかく作ったので、ラベルも作り袋に入れて、「大浦ふるさと館」に置かせてもらうことにした。50gで200円。ちなみに、私自身は「健康になるから飲もう!」というアピールは好きではなく、あくまで美味しいから飲むというのが王道だと思うので、ラベルには「健康飲料」の文字は入れなかった。ねじめびわ茶も美味しいと思うが、先日ペットボトルのねじめびわ茶を飲んでみたら、それよりはうちの枇杷茶をちゃんと淹れて飲んだ方が美味しいと思ったのでお試しあれ。
※ 緑茶の製作工程でも「発酵」という言葉が使われるが、これは業界用語で「発酵」と言っているだけで本当の「発酵」ではない。乳酸菌や酵母は緑茶の製造には関与していない。では科学的にはなんなのかというと、実は「酸化」なのだ。緑茶には「酸化酵素」というのがあって、これが茶葉を酸化させて味が変わるのである。でも「酸化」というとどうしてもマイナスのイメージがあることと、昔からの慣例で、「発酵」という言葉が使われている。
2012年9月6日木曜日
有機農業の是非を検証する
新規就農するというと、いろいろな人から「やっぱり野菜は有機栽培で作りたいよね」というようなことを言われる。私も、高付加価値商品を作る観点から有機農業に惹かれる部分はあるが、一方で、無批判に「有機農業はよい」というイメージだけが先行しているようにも感じている。
極端な話だが、有機農業というと「有機栽培の野菜を食べてアトピーが治った!」とか「元気で明るくなった!」とか宗教まがいの喧伝がされることも多い。実際、有機農業と宗教との関係は近く、養鶏を中心とした有機農業を発展させて人の生き方まで規定するに至った山岸巳代蔵は、農事組合法人でありながら宗教組織である「幸福会ヤマギシ会」を作ったし、酵素肥料なる(今ではインチキと考えられているが)ボカシ肥の元祖みたいなものを作った柴田欣志は祈祷師だった。有機農業による穀菜食を提唱している食品会社の三育フーズは、セブンズデー・アドベンチスト教団という米国のキリスト教系信仰宗教の一部門が運営している。こうした話を聞くたび、「有機農業は、科学的に考えて実際どうなのだろう?」という疑問が湧く。
そこで、少しマニアックな話になるが、有機農業の是非について考えてみたい。
まず、有機農法とは何か、ということを正確に定義しておこう。普通、有機農業とは「化学肥料と農薬を使わない農業」と思われているがこれは物事の一面でしかない。化学肥料や農薬を使わないというのは、手段であって目的ではないからだ。IFOAM(有機農業運動国際連盟)という団体が有機農業の詳細な定義を作っているが、それをまとめると有機農業の目的は「農業生態系と農村の物質循環を重視し、地力を維持・増進させて生産力を長期的に維持し、外部への環境負荷を防止して自然と調和しながら、十分な量の食料を生産し、農業者の満足感と所得を保障すること」である(※)。
要するに、有機農業の主要目的は、環境負荷を低減しつつ経済的にも自立可能な「持続可能な農業」をすることであり、こうした目的の下に行われる農業が有機農業なのだ。これは、近年喧しい「安心安全な農産物の生産」や「作物本来の美味しさ」などは全く関係がない。
この目的を達成するため、有機農業では農業生態系(圃場とその近辺)の外からの資材投入は出来るだけ少ない方がよいとされており、化学肥料のように外国で精製された物質はもちろん、堆肥であっても外部の畜産農家から仕入れるのではなく自家生産することが奨励されている。すなわち、物質循環をできるだけ農業生態系内で完結させることが求められているのである。
この理念を厳密に実行するのは日本では難しく、有畜農業が普通のヨーロッパにおいてすら簡単ではない。
また環境負荷を低減するため、化学農薬を基本的に使用しないのであるが、これは私には疑問だ。例えば、除草剤を使用しないために、有機農業ではマルチングの使用が必須となるが、なぜ石油合成製品であるビニールマルチはよくて、除草剤はダメなのか。また、2週間で自然分解される除草剤を使って草を枯らすのと、数時間ガソリンを使って草払いするのとどちらが環境負荷が軽いと言えるのか。そのほか、害虫の防除にも農薬が使えないことから天敵となる昆虫を大量に放すなどするが、これも一種の生態系の攪乱である。どのような手段が最も環境負荷が小さいかは科学的検証によって判明することであって、頭ごなしに「農薬はダメ」というのは科学的態度ではない。
なお重要なことだが、農薬を使用しないのは、決して「安全安心」のためではなくて環境負荷を低減し、農業生態系の中で物質循環させるためである。日本だけでなく世界で「有機農業による生産物は安全・安心だ」という思い込みがあるが、これは間違いとは言えないまでも正確ではない。
というのは、「有機農産物=安全・安心」は「慣行農業農産物=危険・不安」の裏返しなのだが、野放図に農薬を使っていた数十年前はともかく、現行の農薬規制は非常に厳しく作ってあり、普通の農産物が危険・不安というのは科学的態度ではない。農薬規制は「その農産物を一生食べ続けても影響がない」レベルになるよう調整されており、有機農産物をことさら「安全・安心」と喧伝することは、暗に慣行農業の農産物への危険を煽る不誠実な行為と言える。ただし、農薬に未知のリスク(長期使用による蓄積や複合的な影響)がある可能性はゼロではないのは事実だ。
といっても、農薬を使っていないから安全・安心というのは安直な考えで、農薬による防除を行わずに虫食いや病害などが起こったとすれば、植物はこれに対抗するために自ら毒性物質を生産するといった手段を講じる。これによって植物体の中に植物毒が蓄えられることもあり、農薬を使わない=毒性物質がない、ではない。
少し話が脱線するが、俗に言われる「農薬を使わず自然に育てた野菜が美味しい」とか自然農法に代表される「植物のありのままの力を活かすと美味しくなる」といった言説は、私には自然への冒瀆とすら感じる。「自然=美味しい」という図式がどうして成立したのかわからないが、自然の植物の多くは虫害・鳥害・病害などからその身を守るために植物毒を持っており、その毒性はしばしば極めて強力である。自然は荒々しいものであり、人間が気軽に利用できるような簡便なものではない。多くの栽培植物も、その起源においては毒性があったり利用しにくい性質を持っていたりしたが、少しでも美味しい株、利用しやすい株を増やすという数千年にわたる品種改良の結果、今の作物が生まれているわけで、「自然=美味しい」などという認識は、自然をなめきったものであると同時に、人類の農耕史をも貶める見方であると思う。
でも、「事実、有機農業の野菜は美味しいじゃないか!」という反論があるかもしれない。確かにこれは事実と思う。しかしそれは因果関係に飛躍がある。先ほどの目的からすると、有機農業を真面目に実施しようと思えば、大規模生産が難しいことは自明だ。そこで、有機生産農家は高付加価値商品の少量生産を行わざるを得ない。そのため、適切な施肥設計、作付計画、高品位な種苗の選択といったことが行われた結果、美味しい作物が収穫できるのであって、有機農業だから美味しいわけではない。当然、慣行農法の農家であってもそのような適切な管理を行う農家はいて、そういう農家が生産した作物は、有機農法による作物と同じように美味しいだろう。
つまり、「有機農業だから安全・安心で美味しい」は幻想に過ぎない。慣行農業においても安全・安心で美味しい農産物は得られる。ということは、有機農業の農産物を(通常の農産物より高い価格で)購入する消費者は、何に対してお金を払っているのだろうか? なんとなくよいもの、なんとなく高級なもの、というイメージにお金を払っているのだろうか?
ここでもう一度有機農業の目的を見直してみるとこの答えは明白だ。有機農業というのは、要は環境に配慮した農業なのだから、消費者は環境の保全のためにお金を払っているのである。しかし有機農業の農産物を買って割高なお金を払うのは一部の人である一方、環境が保全されてその利益を享受するのは共同体全員だ。そのため、ヨーロッパ各国では環境保全の意味合いから有機農業を行う農家に補助金を出している。有機農業は消費者のニーズに応えるために行うものではないから、政府がその費用の一部を支出しているのである。
そもそも有機農業がヨーロッパで広まった背景には、1980年代の食料の過剰生産がある。この頃、ヨーロッパでは農業の機械化・集約化によって生産力が高まって食料が余り、また農薬・肥料の過剰投入によって環境が汚染された。これを受け、日本風に言えば減反政策が実施されるのだが、その中の一つが有機農業の振興だったのである。つまり、大規模農業の代わりに少量生産の有機農業を広めることにより、減反と環境保全を両方達成しようとしたのであった。補助金がなければやっていけない農業は真の意味で「持続可能な農業」ではない、という批判もあるが、私はこの政策は合理的であったと思う。
翻って日本を見ると、減反と環境保全という有機農業の理念が正確に理解されているとは言い難い。日本においては食料生産レベルをさらに上げることが課題であり、農地の集約化・機械化による大規模化は長年の懸案だ。有機農業の振興は、ただでさえ小規模分散・手作業の多い日本農業を立ち遅らせることにならないか。また、有機農業の目的が環境保全にあることを理解している消費者も少なく、「安全・安心」のような漠然としたイメージに踊らされている面がある。本来なら、環境に配慮した農業という理念に共鳴し、環境保全のために高いお金を払うという認識になるのが正しいあり方だと思う。
しかも、有機農業は日本とは気候も環境も農業文化も違うヨーロッパから輸入された概念・手法になってしまっており、本当にIFOAMが定める「有機農業」が日本に合っているのかは一考を要する。有畜農業が基本になっているだけでも、畜産農家と作物農家が分かれている日本には相容れないものがあるし、作物体系も違う。日本での「持続可能な農業」は一体どんなものなのか、その解は出ておらず、真面目に検討されているとも言い難い。日本ならではの「有機農業」を形作っていく必要があると思う。
こうして有機農業の特質を検討してみた結果をまとめると次のようになる。
結論としては、「有機農業は理念はよいが現行の手法が最適なのかは一考の余地があり、日本ならではのやり方を確立すべき」、つまり「今の有機農業はいろいろな意味で未熟」ということになると思う。
しかし、未熟であるからこそ将来性もあるだろうし、化学肥料や燃料、化学合成の資材をふんだんに使える環境になったのは、つい最近のことに過ぎず、これが将来どうなるかは不透明だ。大量生産・大量消費の文明がどこまで続くかわからないが、これを支えている条件が崩れれば、人類はこうした便利な資材を使う農業を続けて行くことはできない。そうでなくても、近い将来にリン酸肥料の枯渇が予見されるなど、人口増に対応した肥料増産が今後可能かどうかわからない。人口増と新興国の生活レベルの向上によって食料生産が逼迫してきた時、今までのような農業を日本が続けていけるのか心もとない。
そうなった時の答えが有機農業なのかはよくわからないけれども、農業が変わって行かざるを得ないのは間違いない。その意味で有機農業の一つの利点は、「慣行農業に対して疑問を抱く」というスタンスにもある。主流派の動向を懐疑的に見る勢力が私は好きだ。いろいろ批判的なことを書いたけれども、自分なりに有機農業をやってみたいとは思っている。
※ 『有機栽培の基礎知識』1997年、西尾 道徳 より引用。
極端な話だが、有機農業というと「有機栽培の野菜を食べてアトピーが治った!」とか「元気で明るくなった!」とか宗教まがいの喧伝がされることも多い。実際、有機農業と宗教との関係は近く、養鶏を中心とした有機農業を発展させて人の生き方まで規定するに至った山岸巳代蔵は、農事組合法人でありながら宗教組織である「幸福会ヤマギシ会」を作ったし、酵素肥料なる(今ではインチキと考えられているが)ボカシ肥の元祖みたいなものを作った柴田欣志は祈祷師だった。有機農業による穀菜食を提唱している食品会社の三育フーズは、セブンズデー・アドベンチスト教団という米国のキリスト教系信仰宗教の一部門が運営している。こうした話を聞くたび、「有機農業は、科学的に考えて実際どうなのだろう?」という疑問が湧く。
そこで、少しマニアックな話になるが、有機農業の是非について考えてみたい。
まず、有機農法とは何か、ということを正確に定義しておこう。普通、有機農業とは「化学肥料と農薬を使わない農業」と思われているがこれは物事の一面でしかない。化学肥料や農薬を使わないというのは、手段であって目的ではないからだ。IFOAM(有機農業運動国際連盟)という団体が有機農業の詳細な定義を作っているが、それをまとめると有機農業の目的は「農業生態系と農村の物質循環を重視し、地力を維持・増進させて生産力を長期的に維持し、外部への環境負荷を防止して自然と調和しながら、十分な量の食料を生産し、農業者の満足感と所得を保障すること」である(※)。
要するに、有機農業の主要目的は、環境負荷を低減しつつ経済的にも自立可能な「持続可能な農業」をすることであり、こうした目的の下に行われる農業が有機農業なのだ。これは、近年喧しい「安心安全な農産物の生産」や「作物本来の美味しさ」などは全く関係がない。
この目的を達成するため、有機農業では農業生態系(圃場とその近辺)の外からの資材投入は出来るだけ少ない方がよいとされており、化学肥料のように外国で精製された物質はもちろん、堆肥であっても外部の畜産農家から仕入れるのではなく自家生産することが奨励されている。すなわち、物質循環をできるだけ農業生態系内で完結させることが求められているのである。
この理念を厳密に実行するのは日本では難しく、有畜農業が普通のヨーロッパにおいてすら簡単ではない。
また環境負荷を低減するため、化学農薬を基本的に使用しないのであるが、これは私には疑問だ。例えば、除草剤を使用しないために、有機農業ではマルチングの使用が必須となるが、なぜ石油合成製品であるビニールマルチはよくて、除草剤はダメなのか。また、2週間で自然分解される除草剤を使って草を枯らすのと、数時間ガソリンを使って草払いするのとどちらが環境負荷が軽いと言えるのか。そのほか、害虫の防除にも農薬が使えないことから天敵となる昆虫を大量に放すなどするが、これも一種の生態系の攪乱である。どのような手段が最も環境負荷が小さいかは科学的検証によって判明することであって、頭ごなしに「農薬はダメ」というのは科学的態度ではない。
なお重要なことだが、農薬を使用しないのは、決して「安全安心」のためではなくて環境負荷を低減し、農業生態系の中で物質循環させるためである。日本だけでなく世界で「有機農業による生産物は安全・安心だ」という思い込みがあるが、これは間違いとは言えないまでも正確ではない。
というのは、「有機農産物=安全・安心」は「慣行農業農産物=危険・不安」の裏返しなのだが、野放図に農薬を使っていた数十年前はともかく、現行の農薬規制は非常に厳しく作ってあり、普通の農産物が危険・不安というのは科学的態度ではない。農薬規制は「その農産物を一生食べ続けても影響がない」レベルになるよう調整されており、有機農産物をことさら「安全・安心」と喧伝することは、暗に慣行農業の農産物への危険を煽る不誠実な行為と言える。ただし、農薬に未知のリスク(長期使用による蓄積や複合的な影響)がある可能性はゼロではないのは事実だ。
といっても、農薬を使っていないから安全・安心というのは安直な考えで、農薬による防除を行わずに虫食いや病害などが起こったとすれば、植物はこれに対抗するために自ら毒性物質を生産するといった手段を講じる。これによって植物体の中に植物毒が蓄えられることもあり、農薬を使わない=毒性物質がない、ではない。
少し話が脱線するが、俗に言われる「農薬を使わず自然に育てた野菜が美味しい」とか自然農法に代表される「植物のありのままの力を活かすと美味しくなる」といった言説は、私には自然への冒瀆とすら感じる。「自然=美味しい」という図式がどうして成立したのかわからないが、自然の植物の多くは虫害・鳥害・病害などからその身を守るために植物毒を持っており、その毒性はしばしば極めて強力である。自然は荒々しいものであり、人間が気軽に利用できるような簡便なものではない。多くの栽培植物も、その起源においては毒性があったり利用しにくい性質を持っていたりしたが、少しでも美味しい株、利用しやすい株を増やすという数千年にわたる品種改良の結果、今の作物が生まれているわけで、「自然=美味しい」などという認識は、自然をなめきったものであると同時に、人類の農耕史をも貶める見方であると思う。
でも、「事実、有機農業の野菜は美味しいじゃないか!」という反論があるかもしれない。確かにこれは事実と思う。しかしそれは因果関係に飛躍がある。先ほどの目的からすると、有機農業を真面目に実施しようと思えば、大規模生産が難しいことは自明だ。そこで、有機生産農家は高付加価値商品の少量生産を行わざるを得ない。そのため、適切な施肥設計、作付計画、高品位な種苗の選択といったことが行われた結果、美味しい作物が収穫できるのであって、有機農業だから美味しいわけではない。当然、慣行農法の農家であってもそのような適切な管理を行う農家はいて、そういう農家が生産した作物は、有機農法による作物と同じように美味しいだろう。
つまり、「有機農業だから安全・安心で美味しい」は幻想に過ぎない。慣行農業においても安全・安心で美味しい農産物は得られる。ということは、有機農業の農産物を(通常の農産物より高い価格で)購入する消費者は、何に対してお金を払っているのだろうか? なんとなくよいもの、なんとなく高級なもの、というイメージにお金を払っているのだろうか?
ここでもう一度有機農業の目的を見直してみるとこの答えは明白だ。有機農業というのは、要は環境に配慮した農業なのだから、消費者は環境の保全のためにお金を払っているのである。しかし有機農業の農産物を買って割高なお金を払うのは一部の人である一方、環境が保全されてその利益を享受するのは共同体全員だ。そのため、ヨーロッパ各国では環境保全の意味合いから有機農業を行う農家に補助金を出している。有機農業は消費者のニーズに応えるために行うものではないから、政府がその費用の一部を支出しているのである。
そもそも有機農業がヨーロッパで広まった背景には、1980年代の食料の過剰生産がある。この頃、ヨーロッパでは農業の機械化・集約化によって生産力が高まって食料が余り、また農薬・肥料の過剰投入によって環境が汚染された。これを受け、日本風に言えば減反政策が実施されるのだが、その中の一つが有機農業の振興だったのである。つまり、大規模農業の代わりに少量生産の有機農業を広めることにより、減反と環境保全を両方達成しようとしたのであった。補助金がなければやっていけない農業は真の意味で「持続可能な農業」ではない、という批判もあるが、私はこの政策は合理的であったと思う。
翻って日本を見ると、減反と環境保全という有機農業の理念が正確に理解されているとは言い難い。日本においては食料生産レベルをさらに上げることが課題であり、農地の集約化・機械化による大規模化は長年の懸案だ。有機農業の振興は、ただでさえ小規模分散・手作業の多い日本農業を立ち遅らせることにならないか。また、有機農業の目的が環境保全にあることを理解している消費者も少なく、「安全・安心」のような漠然としたイメージに踊らされている面がある。本来なら、環境に配慮した農業という理念に共鳴し、環境保全のために高いお金を払うという認識になるのが正しいあり方だと思う。
しかも、有機農業は日本とは気候も環境も農業文化も違うヨーロッパから輸入された概念・手法になってしまっており、本当にIFOAMが定める「有機農業」が日本に合っているのかは一考を要する。有畜農業が基本になっているだけでも、畜産農家と作物農家が分かれている日本には相容れないものがあるし、作物体系も違う。日本での「持続可能な農業」は一体どんなものなのか、その解は出ておらず、真面目に検討されているとも言い難い。日本ならではの「有機農業」を形作っていく必要があると思う。
こうして有機農業の特質を検討してみた結果をまとめると次のようになる。
- 環境保全、持続可能な農業という有機農業の理念はよい。
- しかし、現行の化学肥料・農薬不使用というのは科学的なのかどうか不明。
- 消費者に有機農業の意味が正確に理解されておらずイメージだけが先行している。
- そもそもヨーロッパ基準の「有機農業」が日本に合致しているか不明。
結論としては、「有機農業は理念はよいが現行の手法が最適なのかは一考の余地があり、日本ならではのやり方を確立すべき」、つまり「今の有機農業はいろいろな意味で未熟」ということになると思う。
しかし、未熟であるからこそ将来性もあるだろうし、化学肥料や燃料、化学合成の資材をふんだんに使える環境になったのは、つい最近のことに過ぎず、これが将来どうなるかは不透明だ。大量生産・大量消費の文明がどこまで続くかわからないが、これを支えている条件が崩れれば、人類はこうした便利な資材を使う農業を続けて行くことはできない。そうでなくても、近い将来にリン酸肥料の枯渇が予見されるなど、人口増に対応した肥料増産が今後可能かどうかわからない。人口増と新興国の生活レベルの向上によって食料生産が逼迫してきた時、今までのような農業を日本が続けていけるのか心もとない。
そうなった時の答えが有機農業なのかはよくわからないけれども、農業が変わって行かざるを得ないのは間違いない。その意味で有機農業の一つの利点は、「慣行農業に対して疑問を抱く」というスタンスにもある。主流派の動向を懐疑的に見る勢力が私は好きだ。いろいろ批判的なことを書いたけれども、自分なりに有機農業をやってみたいとは思っている。
※ 『有機栽培の基礎知識』1997年、西尾 道徳 より引用。
登録:
投稿 (Atom)




















