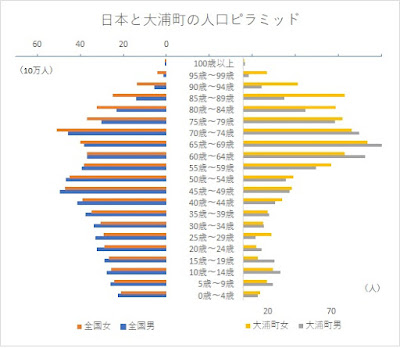鹿児島県議会議員選挙である。
が、私の住む「南さつま選挙区」は前回に続き無投票である。投票に参加できないどころか、選挙そのものがないのは、民主制の前提を満たしていないと思う。
全国でも、今回の統一地方選挙では立候補者の4人に1人が無投票当選で、4割弱の選挙区で無投票だったそうである。もはや日本の半分近くの地域で、選挙という枠組みが機能していない。
この由々しい事態を受け、立候補者を増やすために「議員報酬を増やそう」「政治への関心を高めよう」といった動きが報道されている。
しかし鹿児島県議の議員報酬は決して安くなく、全国的に見たら平均程度の月額78万円だ。市町村議会議員の報酬はともかく、県議ともなれば地方の水準では十分な報酬になっている。
また政治への関心については、若い人を含め、少なくともここ30年では今が一番高いと思う。それは日々の暮らしが政治によって脅かされている実感があるからだ。少なくとも政治がどこか遠い世界の話だった時代とは違い、今では我々の懐にまで「政治」が手を伸ばしつつある。
であれば、県議選も多くの立候補者が犇めいていてもおかしくない。それなのに現実は、鹿児島の21選挙区中の7選挙区で立候補者が議員定数を越えなかったのだ。
なぜか。少なくともそれは「政治への関心の低さ」だけでは説明できないことは確かだ。無投票の選挙区に住む一人としてちょっと考えてみたい。
県議への立候補者が少ないのは、第1に、市町村合併の影響があるだろう。
県議というのは、市町村議員が目指す場合が多い。だが市町村合併によって自治体の数がかなり減って、当然に市町村議会の数が減ったため、市町村議員は激減した。
例えば南さつま市は1市4町が合併してできた市だが、旧町時代はそれぞれ20人くらい市議・町議がいたので、計100人程度議員がいたと思う。それが合併後には約20人になったわけだから、議員数は5分の1になったことになる。
このように、県議に立候補する可能性が高かった市町村議が減ったことが、県議の立候補者が少ないことの第一の理由であると私は思う。
第2に、市議から県議への鞍替えが減ったことが挙げられる。
平成の大合併の前は、鹿児島の場合は人口1万人程度の「町」が多かったように思う。このサイズだと、町議になるには200票くらい入ればいい。そしてこの時代は、集落の自治会長が町議に立候補するのが定番だった。200票というと、自分の所属する集落の人たちを中心に、知り合いが投票してくれれば当選できた数だ。
だからこの頃は、自治会長をやるような、人付き合いがマメで少し声が大きなオジサンが、町議に立候補するものだったのである。ついでに言えば、自治会長そのものが町議へのステップの一つと見なされていたので、町議を狙うような人が率先して自治会長を担ってくれていたという側面もあったと思う。
しかし市町村合併によって選挙区が広くなると、当選ラインは500~1000票程度へと上がった。都市部の人から考えると500票も十分少なく感じるだろうが、500票になると直接の知り合いだけでは集められない規模になる。どうしても不特定多数の人に訴えなくてはならない。そうなると、「人付き合いがマメで少し声が大きなオジサン」程度では市議にはなれない。そういうわけで、市町村議員になる人はかなり減った。
結果、市町村議も定数がギリギリ(無投票の時も散見される)であるから、市議から県議になろうとするインセンティブが今はない。市民としても、後援している人が市議から県議になろうとするのを応援しづらい。その人が鞍替えするせいで市議選が無投票になるかもしれないのだから。
第3に、今の若い人は従来の選挙のやり方に意義を感じてない、ということがある。だから若い人が立候補しない。従来型の選挙のやり方の定番は、「辻立ち」「選挙カー(街宣カー)」「電話作戦」「ガンバロー集会」といったもので、これらは今でも票集めの活動としてある程度有効だが、政治に関心を持つ若い人はこうした活動を行う気になれない。
「辻立ち」は選挙期間以外でも行われ、街頭で「みなさんおはようございます! いってらっしゃいませ」などと元気よく声をかける活動。これで道行く人からの支持が得られる可能性はわずかだが、後援会のメンバーにとっては「〇〇さんも頑張っているんだから、我々も応援しなくては」という気持ちになる重要な活動である。というか「辻立ち」を疎かにすると後援会から「最近〇〇さんは地域に目が向いていない」「天狗になっている」などと批判されることもしばしばだ。
「選挙カー」は選挙期間中のみ可能で、いわゆる「連呼行為」という名前などを繰り返すことのみが走行中に認められている。これは街の人にとっては迷惑以外の何物でもない。しかし特に田舎における選挙においては、「この辺りには選挙カーすら来ない」という声はよく聞かれる。田舎では、地域をせめて一回りするくらいのことはします、という意思表示として受け取られていると思う。ただし都会での意義はたぶんほぼない。
「電話作戦」は、選挙では戸別訪問が禁止されているため、電話で「〇〇さんへの投票をよろしくお願いします」と後援会メンバーが呼びかけるものである。しかし最近の若い人は電話という手段を好んでおらず、できれば出たくないものと考えている節がある。また「電話作戦」は政策を訴えるでもなく、ひたすらに人脈を頼りにするものであるから、人脈の形成途中である若い人にとっては不利である。
「ガンバロー集会」は、決起集会・個人演説会のことを、仮にこう呼んでみた。「ガンバロー!!」という掛け声が特徴的だからである。こうした集会は、今まで挙げたものの中では一番「政治」に近いかもしれない。集会の中では政策を訴えることも稀ではないからだ。しかし多くの「ガンバロー集会」は、「今回の選挙は厳しい戦いだ。一丸となって頑張ろう!」という掛け声のために行われる。候補者の側としては、そもそも集会に出ている時点で出席者を支持者だとみなしているから(だいたい正しい)、その場にいる人に政策を訴えることは必要ではないと思っている。「ガンバロー集会」の目的は、政策を訴えるためではなく、支持者を高揚させ、一体感を抱かせることだ。
これらの旧来型手法は全体として、後援会を中心とした支持者集団を強固にし、そこを起点として露出を増やす活動だと言える。その中では、政策を訴えるとか、現在の政治・行政を批判するといったことは、かえって支持を失う可能性がある行為として忌避される。
今回の鹿児島県議選で、原発の是非や馬毛島のような、政治的な問題について候補者がほぼ沈黙しているのもそのためだ。以前、元SPEEDのメンバーで自民党から参議院議員に立候補した今井絵理子さんが、選挙活動中に記者から「憲法や経済の話は?」と問われ、「今は選挙中なのでごめんなさい」と言ったのは象徴的だ。これは自民党の事情も大きいのだが、野党も含め、有権者の判断が分かれるような問題はできれば触れないでおこうとする傾向はある。
結局のところ、今の選挙は「政治」から遠ざかってしまっているのだ。選挙が政治的であることを避けようとしている、と言い換えてもいい。
私は先ほど「政治への関心については、若い人を含め、少なくともここ30年では今が一番高い」と書いた。政治的な関心が高い若い人を見ていると、一昔前の「人付き合いがマメで少し声が大きなオジサン」などよりずっと真面目に政治を考えている。しかしそういう人にとって、選挙は少々馬鹿馬鹿しく感じられる。政治的な主張をするでもなく、社会の向かうべき道を示すでもなく、支持者との一体感の中で露出競走をするのが今の選挙運動だと。
もちろん彼らとて、いかに選挙が気乗りしないものに感じられようとも、いざとなれば選挙に出るには違いない。そして現実には、多くの人に動いてもらわなければならない選挙運動には、主義主張以前の部分に「政治」があり、はたから見るほど無意味ではないのだ。
しかしいざ彼らが立候補しようと思っても、彼らの考える「政治的な選挙運動」には、まだ多くの人がついてきていないのも現実だ。
例えば、インターネットを使った政治的主張、候補者同士の政策討論会、「ガンバロー!」ではない個人演説会、既存の政党の枠組みとは違う政治活動のやり方、後援会中心ではない選挙運動、といったことが彼らのやりたいことだろうが、実際にそれをやっても、不特定多数の支持が集まるのかどうか、今のところちょっとわからない。やはり「どぶ板」が強い可能性は高い。
ところで、選挙が「政治」から遠ざかったといっても、それは何も今に始まったことではない。少なくとも戦後はそんな感じが続いてきた。
だが、この20年ほどで、政治家に求められる役割はかつてとは違ってきた。かつての市町村議員・県議の役割は、上(国や県)から流れてくる予算の配分を行うことだった。特に高度経済成長期以降は、予算が有り余っている時期があり、そのお金を地域にうまく配分するのが「政治家」の役割だった。
そのために必要な資質が、マメな人付き合いや、分断をつくらないための曖昧な態度であったと言えるかもしれない。そして政治家本人よりも「後援会」の方に活動の本体があり、「神輿は軽い方がいい」と俗にいうとおり、個人の政治的主張よりも、お金の分配を求める地域の総意を代弁することが「政治家」に期待されていた。
もちろん、例えばダム建設予定地となって反対運動が起こったような場所では、こういうわけにはいかず、利害関係の対立を解消する、本来の意味での政治が繰り広げられた。しかし日本の大部分の地方では、そのような先鋭的な政治的対立はおこらず、上から流れてくるお金を大過なく分配しているだけで、それなりに発展してきたのである。
だが周知のとおり、そういうフェーズは過去のものとなった。今の日本は、政治的な問題に向き合わずにはいられない。これからの政治家は、お金を分配するのではなく、負担を分配するという、ややこしい仕事をしなくてはならない。
だから、真面目に政治を考えている若者に選挙に出てもらう他ない。そのために私たちができることは何だろうか?
少なくとも今回の県議選では、少しでも「政治」を語っている候補者に一票を入れることだろう。「政治」から遠ざかった選挙に、もう一度「政治」を取り戻さなくてはならない。
どこかの新聞に書いてあった。今は政治への関心は高いが、不信もまた根深いと。政治への不信があるからこそ、選挙では政治が避けられる。だがいつまでも政治を避けて通っていては、日本社会が変わっていくことはできない。
選挙がもっとまじめに「政治」に向き合うものとなれば、きっと多くの若い人が立候補するのではないかと、私は期待している。