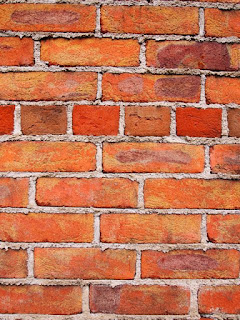鹿児島の枕崎市に、「
紅茶碑」というのがある。また、インド アッサムから導入した紅茶の原木もある。
曰く「この地に於いて我が国で初めて紅茶栽培が成功した。当時、枕崎町長今給黎誠吾氏は昭和6年印度アッサム種の栽培に着目してこの地に育て…」とのこと。ともかく枕崎は「日本国産紅茶発祥の地」を誇っているのであるが、これは事実だろうか?
私はこれに違和感を感じ、いろいろと調べてみたが、結論を先に言えばこれは事実ではない。残念なことに、
枕崎は国産紅茶発祥の地ではないのだ。では、国産紅茶の歴史において枕崎はどのように位置づけられるのだろうか? 非常にマニアックになるが、国産紅茶の歴史を繙き、枕崎における紅茶生産の持つ意味を探ってみたい。
日本紅茶の歴史は、殖産興業に邁進していた明治政府が「紅茶産業が有望では?」と目をつけたことに始まる。明治政府は、静岡に移住し茶栽培に取り組んでいた旧幕臣の
多田元吉を役人に取り立て、中国、ついでインドに派遣し栽培・製造方法を習得させる。中国式の製造法はうまくいかなかったが、インド式の製造法で成功し、ここに日本紅茶の生産が開始する。
多田がインドから帰国したのが1877(明治10)年。同年、高知県安丸村に試験場を設けて自生茶を原料として紅茶が作られた。
本当の日本紅茶発祥の地は、この高知県安丸村であると言うべきである。ただし、この紅茶はあくまで日本在来の緑茶の樹を使い、製法のみインド式紅茶にしたわけだから本格的な紅茶生産の開始ではない(緑茶の茶葉を紅茶に転用しただけ)。
ちなみに、多田元吉は「
近代日本茶業の父」などと呼ばれ、日本の紅茶・緑茶産業の基礎をつくった人物である。多田はアッサムから持ち帰った紅茶の種子を自身の農場である
静岡県丸子(まりこ)で栽培するとともに、各地に播種した。
紅茶用茶樹の栽培に初めて成功したのはこの静岡県丸子であり、「紅茶碑」にいう「この地に於いて我が国で初めて紅茶栽培が成功した」というのは事実ではない。これは「紅茶碑」の昭和6年に先立つこと
50年以上も前の話である。
それからの
日本紅茶産業の歴史は波瀾万丈で非常に面白い。紅茶は緑茶と違いグローバル商材であるため、世界情勢に大きな影響を受け、その歴史はまさに世界(主に米国)に翻弄された歴史であった。
まず、多田帰国の翌年である1878年には政府は各地に伝習所(研修施設)を作り、技術の向上に努め、そのおかげで1883年に米国への販路が開けたところが近代紅茶産業の幕開けとなる。ちなみに、それまでは政府は三井物産に委託してロンドンへ紅茶を販売するなどしており、このおかげで三井物産は大もうけし、これは後の
日東紅茶へと繋がっていく。
実は、米国は紅茶よりも遙かに多い量の緑茶も日本から輸入していたのだが、1899年、米国はスペインとの戦費調達のため
茶に高額な輸入税をかけ、これが日本の緑茶・紅茶業界に打撃を与えた。これは米西戦争後すぐに撤廃されたが、続いて1911年、米国は「着色茶輸入禁止令」を制定。どうも
この頃の日本紅茶は着色料で色つけしていたらしく、これも日本の紅茶業界に衝撃を与えた。明治後半は、米国の政策により茶業界が翻弄された時代といえる。
このように重要顧客である米国への輸出が不安定だった中、1914年に第一次世界大戦が開戦、これにより日本紅茶業界は
空前の好況を迎える。これは、イギリスがインド・セイロンからの紅茶輸送船を戦争に徴用して、イギリスからの米国向け紅茶輸出が激減したためであった。しかしこの期に乗じて日本は木茎混入品など
低劣な紅茶を大量に輸出。これで米国消費者の不信を買い、流通が正常に戻った戦後は対米輸出はむしろ低迷することになる。折しも1920年、米国は「禁酒法」を制定。インドやセイロン、ジャワなど紅茶産地はこれを好機と見て米国で紅茶の大キャンペーンを開始するが、これに乗り遅れた日本紅茶の存在感はさらに希薄になっていく。
空前の好況の後の低迷、これが大正期の日本茶業だった。
1919年、
政府は国立茶業試験場を設立し、それまで不十分だった紅茶用の茶樹の育種に取り組み始める。紅茶の価格は国際情勢(というより米国の情勢)に大きく左右され、その品質を高めようというインセンティブが少なかったためか、明治後期に行われていた茶の指定試験(国費により各地の試験場で行われる試験)がこの頃は中止されていたのだった。国立茶業試験場の設立を契機として1929(昭和4)年に指定試験を再開。全国各地で紅茶の指定試験が行われたが、知覧(※1)と枕崎(※2)でもこれが行われた。昭和初期は、紅茶の品質向上が目指された時代だった。
そうした中で1933年、
突如として日本の紅茶産業に空前絶後の好況が訪れる。世界恐慌で世界的に紅茶の需要が減り、在庫が激増、価格が半分ほどにまでに下落。これを受けてインド、セイロン、ジャワという紅茶の中心産地が5年間の輸出制限協定を締結し、世界的に紅茶の流通が一気に減少したのだった。そこで日本紅茶への注目が集まったというわけで、
輸出量は1年でなんと20倍以上に増え、イギリスまでもが相当量の日本紅茶を買い付けたといわれる。輸出制限の最終年である1937(昭和12)年には、日本紅茶は史上最高の輸出を記録。しかし、これが日本紅茶産業の最後の仇花であった。
全国各地で行われていた紅茶の試験は、この好況の中でも徐々に廃され、
1940年度には鹿児島に集約された。その理由は明確でないが、価格の浮沈が激しいだけでなく、国民所得(賃金)の増加によって世界的な競争力を失いつつあった紅茶への関心が薄れ、
日本の茶業界が緑茶に収斂していった結果のようである。つまり、国内の誰もが紅茶を見捨てていく中で、鹿児島だけが細々と紅茶研究を続けていく(いかされる)ことになった。しかも、太平洋戦争によって紅茶用茶樹の品種改良は戦前にはあまり成果をあげられなかった。
戦後、高度経済成長によって国産紅茶は国際競争力を失い、国内市場でも緑茶が支配的になる中、
1963(昭和38)年3月、枕崎に九州農業試験場枕崎支場が設立され、ここが紅茶栽培奨励と紅茶用品種の開発に邁進することとなる。しかしこれは、紅茶の試験場としては
遅すぎる出発だったと言わざるをえない。というのも、同年2月、農林省が「国産紅茶の奨励はもう行わない」ことを決定しているのである。ちなみに、知覧に存在していた農事試験場茶業分場も枕崎支場に統合され、
この枕崎支場は国内唯一にして最後の紅茶試験場であった。
なお、枕崎では昭和初期に紅茶の試験地(試験場ではない)が設置されたことから、その栽培もその頃から行われていた。日東紅茶も枕崎に直営の茶園と工場を経営していたし、昭和40年代では県内の紅茶生産量の約半分が枕崎産であった。しかし、枕崎支場が設置された時期には輸出用の紅茶は競争力を完全に失っており、枕崎の生産は国内向けだった。ところが1971年の紅茶輸入自由化で国内消費の命脈も絶たれ、同年紅茶の集荷は中止。
高知県安丸村で始まった日本近代紅茶産業の歴史は、ここに枕崎でその幕を下ろしたのである。
つまり、枕崎は「日本国産紅茶発祥の地」というより、「
日本国産紅茶終焉の地」なのだ。これでは余りにネガティブな表現だと思われるだろうが、実はこの紅茶奨励にあたった県の職員が、「今になってみれば『何んであのようなボッチな計画を立てたのだろう。』」と当時を苦々しく述懐している。そして自分の仕事は「
紅茶産業の終戦処理」だったとまで述べた上、「20数年間にわたり多額の投資をして、紅茶奨励に失敗した過去を反省し、ご迷惑をかけた生産者にお詫び申し上げ、紅茶産業奨励の思い出とする次第です」と結んでいる(※3)。どうも、枕崎の紅茶産業は、既に斜陽化していたものを引き受けさせられた形であり、輝かしい過去といえる過去がないようなのである。
しかし、しかしである。先日紹介したように、現在の枕崎では「
姫ふうき」という絶品の紅茶が作られている。そしてこの「姫ふうき」を生み出している「べにふうき」という紅茶用の品種は、多田元吉がアッサムから持ち帰った紅茶の種子を品種改良することで、ようやく1995年になって
遅咲きの枕崎支場において生み出されたものなのである。私は、昭和40年代に行われていた紅茶用品種の研究が、細々と続けられてきたことに驚愕した次第である。しかも、この「べにふうき」は
日本紅茶開発史の到達点とも言うべき優れた品種なのであるが、それだけではない。この品種に含有される
メチル化カテキンという物質が抗アレルギー作用を有していることが近年明らかになり、花粉症対策などとしてその緑茶が次々と製品化されている。
よく、「
鹿児島は周回遅れのトップランナー」と言われる。 この「べにふうき」開発までの長い歴史を見ても、そう感じるのは私だけではないだろう。一度終焉を迎えた日本紅茶が最近各地で復活の兆しを見せているが、その最高峰に枕崎の「姫ふうき」があるのは面白い。残念ながら枕崎にある紅茶の原木と「べにふうき」に系統関係はないが、紆余曲折を経ながらも受け継がれた国産紅茶の歴史が、今後、枕崎でまた新たな展開を見せることを期待している。
※1 正確には、鹿児島県立農事試験場知覧茶業分場
※2 正確には、鹿児島県立農事試験場知覧茶業分場枕崎紅茶試験地
※3 参考文献に挙げた『紅茶百年史』p511 「紅茶産業奨励の思い出」(鹿児島県園芸課 池田高雄)より引用
【参考文献】
『紅茶百年史』1977年、 全日本紅茶振興会