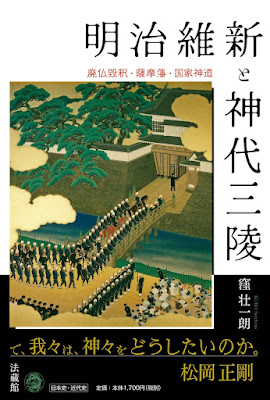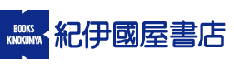(「「南島牌」とヤマト政権の南島政策」からのつづき)
 |
| 図1 万之瀬川河口周辺の主な遺跡(筆者作成) |
これまで文献によって鑑真が秋目に来た意味を考察してきた。
おさらいすると、まず『続日本紀』や『唐大和上東征伝』の記述に基づき、鑑真一行が秋目に来たのは漂着ではなく正常な航路によるものだったと結論づけた(その5)。
次に、鑑真一行が秋目に来着した直後に修理された「南島牌」について考察し、「南島牌」を735年に設置した「高橋連牛養(たかはしのむらじ・うしかい)」は古代阿多郡の豪族だったのではないかという仮説を提示した(その6)。
今回はこれに考古学的知見を加えて、鑑真が秋目に来た意味を歴史に位置づけてみたい。
「その6」でも述べたように、阿多郡は南九州における海上交通の要衝であった。
そのことが解明されるきっかけとなったのは、「持躰松(もったいまつ)遺跡」の発見である。ここは1993年に河川改修工事に伴って発見され、博多・大宰府以外では例を見ないほど多種多様な輸入陶磁器と、東海地方や近畿・瀬戸内地方のものと見られる国産陶器、カムィヤキ(徳之島の焼き物)等が出土した。このことから万之瀬川河口で中世に一大貿易が行われていたことが明らかになったのである。さらに、隣接する「渡畑遺跡」「芝原遺跡」が調査され、特に「芝原遺跡」では「持躰松遺跡」を超える17,000点もの厖大な輸入陶磁器・国内産陶器が発掘された(ただし、持躰松で一通り考察が行われていたので、それほど話題にならなかった)。 しかもコンテナ的な要素を持つ大型の甕・壺が大量に出土したのは、九州では博多以外で万之瀬川河口だけという。
また、中岳という近くの低山の山裾に「中岳山麓窯跡群」という窯跡があり、ここが2000年代に入ってから発掘調査された。ここは9世紀以降に100基を超える須恵器の窯があったというとんでもない場所である。なぜこれほどまでに大量の須恵器を製造する必要があったのかというと、地元で使っていたのではなく交易に使っていたからにほかならない。その証拠に、琉球諸島でも中岳山麓窯製の須恵器(焼き物の成分分析による)が出土している。
しかし、これらの遺跡の出土品のピークは中世であり、特に11世紀から13世紀の話である。では古代以前はどうだったのか。
これについては有名な「高橋貝塚」という遺跡がある。玉手神社という神社の裏手にある貝塚だ。この遺跡からはゴホウラ貝などの南海産(奄美諸島以南に棲息する)の貝殻とその加工品が見つかった。ゴホウラ貝というのは平たい貝で、この真ん中に穴を空けることで貝輪(腕輪など)になった。「高橋貝塚」の時代は弥生時代前期から中期である。
つまり、弥生時代の阿多の人は、ゴホウラ貝を奄美以南から仕入れていた。この貝交易を詳細に研究した木下尚子氏はこの交易を「南海貝交易」と名付け、その交易ルートを「貝の道」と表現している。その研究によれば、阿多の人々は沖縄から貝を仕入れて加工し西北九州(博多など)に輸出していたという。もともと、ゴホウラ貝の貝輪は弥生時代の北部九州で流行していたから、この需要を見込んでの交易だったのである。ところが、やがて沖縄で貝を加工することが行われるようになって中継交易としての阿多はスキップされるようになり、弥生時代中期には阿多での貝交易は廃絶した、というのが木下氏の見立てである。
また、こうした交易の傍証として、「中津野遺跡」で国内最古級の弥生時代前期の準構造船の舷側板が出土した。準構造船というのは、丸木舟に部材を付け加えて大きくした船のことである。阿多は、弥生時代前期に丸木舟以上の船を作り、さらには南島との交易を行っていた地域なのである。
この他にも、この地域には膨大な遺跡が見つかっていて、遺跡の発掘報告書をめくるだけで大変だ。これほど遺跡が集積している地域は鹿児島県内でも珍しく、河川改修や道路開通に伴う発掘調査は地域の風物詩である。周囲はほとんど田んぼで開発がされていないのにこの密度で遺跡が出てくるのは驚異的だ(遺跡は開発によって発見されるからだ)。しかも先史時代から近世にかけて遺跡が重層的になっていて、交易が主体となっているのがこの地域の著しい特徴である。
その中心は、いうまでもなく万之瀬川だ。万之瀬川河口には、先史時代から港が置かれたことがこれまでの発掘調査から明瞭である。物流の中核であったと見られる「芝原遺跡」は、現在の河口からは5kmほど遡った川が大きく蛇行したところにある。このあたりが万之瀬川の港だった。
ところで、どうして海ではなく川を遡ったところに港を作ったのかというと、これは船のメンテナンスと関係がある。
船はずっと海に浮かべているとフジツボなどが船底にびっしりついてしまい、水の抵抗が増してうまく進めなくなる。そこで定期的にフジツボなどを除去する必要があるが、大きな船だと陸揚げするのは大変だし、そもそもフジツボなどが着いた時点で船が傷む。ところが川に船を入港させれば、真水によって海棲動物が死ぬのでその除去の必要がない。これが、海棲動物の付着を防ぐ船底塗料がなかった近世以前において、港が川に設けられた一因である。もちろん、外海に面した場所では、海が荒れた時に施設や物品が損傷してしまうという単純な理由もある。
以上を踏まえれば、鑑真一行が「阿多郡秋妻屋(あきめや)浦」を目指した事情がより明らかになる。つまり、彼らの本当の目的地は万之瀬川河口の港だった可能性が高い。しかし河口の港は、潮が満ちていくタイミングでしか入港できないという弱点がある(もちろん入港に適した風向きも限られる)。そのため、入港の方向も条件も異なる秋目がその予備的な港だったのではなかろうか。鑑真一行は航行のタイミング・風向きなどの事情により、万之瀬川河口への入港を諦めたのだろう。これが、鑑真が秋目を目指した理由であると私は考える。
これで結論が出たようだが、実はまだ話は終わらない。
下の「表1 万之瀬川河口付近の主な遺跡」をじっと見ているとあることに気付かないだろうか。弥生中期までと9世紀以降は万之瀬川河口での交易は盛んなのに、古墳時代については交易が低調なのだ。中世において物流の中心であったと考えられる「芝原遺跡」において、古墳時代の遺構は大量に発見されているのにその時代の交易を示すものがほとんど見つかっていないのは象徴的だ。この表は周辺遺跡を網羅してはいないものの、主要な遺跡は掲載しているからその傾向は明らかだ。つまり、ちょうど鑑真が秋目に来た頃、万之瀬川河口での海上交易は低迷していた。この事情を考えてみないことには、「鑑真一行は海上交易が盛んだった万之瀬川河口の港を目指したのだ」という単純な結論に留まってしまう。古墳時代の万之瀬川河口はどんな場所だったのか。
| 遺跡名 | 時代 | 主な時代 | 注目点 | 参考文献 |
|---|---|---|---|---|
| 栫ノ原遺跡 | 縄文時代草創期 | 縄文時代草創期 | 鹿児島県内では上野原遺跡に次ぐ最古の定住跡。 | |
| 高橋貝塚 | 弥生 | 弥生時代前期 | ゴホウラ貝の交易拠点があったことを窺わせ、沖縄諸島と西北九州とを中継したと考えられる。弥生時代中期以降は貝交易が途絶えた。 | 木下尚子「弥生貝交易の中継地―鹿児島県高橋貝塚のゴホウラ分析から」国立歴史民俗博物館研究報告第237集(2022) 『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(229)「高橋貝塚2」>(2025) |
| 下小路遺跡 | 弥生時代中期 | 弥生時代中期 | 九州南部には分布しない「甕棺墓」に埋葬されていた人物が、ゴホウラ貝装身具を身につけていた。 | |
| 中津野遺跡 | 旧石器時代~近世 | 縄文〜弥生時代 | 縄文時代から中近世までの土器・農具・住居跡等が多数出土した。弥生時代前期から稲作が行われていた。日本最古級の弥生時代前期の舷側板が出土した。 | 『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』「中津野遺跡」「中津野遺跡 2」「中津野遺跡 3」(2022) |
| 上水流遺跡 | 縄文時代中期~近世 | 縄文 | 大規模かつ長期間にわたる集落跡。縄文時代晩期の南島系土器が本土で初めて発見された。縄文時代に南島とのつながりがあったと見られる。 |
『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』「上水流遺跡 1」「上水流遺跡 2」「上水流遺跡 3」(2009)「上水流遺跡 4」(2010) |
| 奥山古墳 | 古墳時代 | 古墳時代 | 4世紀の古墳。板石積石棺墓。天草地域からの石材・工法と考えられる。万之瀬川流域で唯一の古墳。 | 橋本達也他『薩摩加世田 奥山古墳の研究』鹿児島大学総合研究博物館研究報告(2009) |
| 白糸原遺跡 | 縄文時代~中世 | 古墳時代・中世 | 古墳時代の大量の高坏が出土。中世末から近世にかけての土坑が24基検出。中世の土壙墓には廃材と見られる夜光貝がまとまって出土。九州での出土例は枕崎「松尾野遺跡」と本例のみ。 | 『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(86) 「白糸原遺跡」(2004) |
| 中岳山麓窯跡群 | 古代 | 平安時代 | 9世紀中ごろ以降の窯跡が集積している。100基を超える須恵器窯があったと考えられている。交易に用いる壺・甕の製造を担ったと考えられ、成分分析によれば琉球諸島にも中岳山麓窯製の須恵器が出土している。 | 鹿児島大学埋蔵文化財調査センター『中岳山麓窯跡群の研究』(2015) |
| 小中原遺跡 | 縄文時代・奈良~平安時代・鎌倉時代 | 平安時代 | 平安時代(9世紀)の掘立柱遺構が多数。「阿多」の文字が刻まれた土師器が出土した。阿多郡衙の可能性がある。9世紀の火葬人骨も出土。 | 『鹿児島県埋蔵文化財調査報告書』(57) 「小中原遺跡」(1991) |
| 持躰松遺跡 | 縄文時代後期~近世 | 中世 | 多種多様な輸入陶磁器と、東海地方や近畿・瀬戸内地方の国産陶器、カムィヤキ等が出土。大型の掘立柱建物跡があり特殊な施設の可能性。 12世紀中頃~13世紀前半の白磁・青磁がピーク(この時期、大宰府の機能が衰退していることと関連が予見される)。近世にはほぼ耕地化。 |
『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(120) 「持躰松遺跡」 (2007) |
| 渡畑遺跡 | 縄文時代中期~近世 | 中世 | 縄文時代から中世にかけて生活跡が数多く残る。貿易拠点というより居住地が中心か。大量の成川式土器が出土。古墳時代に集落の最盛期を迎えた。ヘラ書き土器・墨書き土器が出土。 11世紀後半~12世紀がピーク。13世紀以降衰退。近世には景徳鎮製の椀が出土。これはヨーロッパからの注文品であった可能性が高いが、なぜ本遺跡にあるのか不明。中岳山麓窯産と思われる須恵器も出土している。 |
『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(151)「渡畑遺跡」『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(159)「渡畑遺跡2」(2010) |
| 芝原遺跡 | 縄文時代中期~近世 | 中世 | 弥生時代には破鏡が出土。古墳時代には大量の土器。中・北部九州地域から搬入されたと考えられる土器があり、交易が予想される。古代には多量の土師器や須恵器が出土。 中世の輸入陶磁器や国内産陶器、合計17000点が出土しその量は周辺遺跡に比べ突出している。青磁・白磁等の輸入陶磁器も約7500点に上る。11世紀後半から12世紀がピーク。コンテナ的な要素を持つ大型甕・壺が大量に出土。中世全期を通じて、万之瀬川下流域の中心的役割を果たした場所であり物流の中心。中国瓦と畿内産瓦器が出土。中世後期からは国内産陶磁器がメインに。中岳山麓窯産と思われる須恵器も出土している。 |
『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』「芝原遺跡」(2010)、「芝原遺跡 2」(2011)「芝原遺跡 3」「芝原遺跡 4」(2013) |
| 小園遺跡 | 縄文時代〜中世 | 中世 | 11世紀後半から13世紀の貿易陶磁、須恵器・常滑焼・畿内産和泉型瓦器椀・南島産のカムィヤキ・滑石製仏具等が出土。有力者の居館跡または宗教的拠点の可能性。 |
古墳時代では、古墳の築造がヤマト政権における秩序を表していたから、まずはこれを見てみるのが一番だ。南九州の墓制・古墳はどうなっていたかというと、これが面白い(図2(※1))。
 |
| 図2 隼人の墓制と高塚古墳 |
なんとなんと、万之瀬川流域を含む薩摩半島中部は、見事なまでの空白地帯になっているのである。古代南九州の人は畿内型の古墳(図では「高塚古墳」と表現)をなかなか受け入れず、「地下式横穴墓」とか「地下式板石積石墓」というような独自の墓を作っていた。そんな中でも大隅半島ではやや早く古墳を受け入れ、たくさんの古墳が残っていることはよく知られる通りである。
しかし薩摩半島中部は「地下式横穴墓」のような古代南九州の墓制すらも不在で、大がかりな墓自体が作られなかったようなのだ。
万之瀬川流域には遺体を海に流すような特殊な墓制があったのかもしれないが、このことから古墳時代の万之瀬川流域について少なくとも2つの事が言える。第1に、この地域に大きな権力を持った指導者のいる社会はなかった。第2に、他地域との人の交流が大規模には行われていなかった。
もし、この地域で活発に人の交流が行われていれば、他の地域でこぞって古墳が作られているなか、墓で威信を示すことが行われていてもよさそうなものだ。それがないということは、社会が内向き・独自路線になっていたことが明らかである。なお、例外として万之瀬川河口近くに「奥山古墳」という古墳が一つだけある。これは天草の方から石材・工法が移入していると分析されている。土着の墓制ではなく、ヨソ者的な墓なのである。
また、社会が内向き・独自路線になっていたことの証左として「成川(なりかわ)式土器」も挙げられる。成川式土器とは、指宿の山川にある「成川遺跡」を標式遺跡とし、弥生時代終末期〜7・8世紀まで南九州全域で作られた土器である。これは長く弥生土器と思われていた地域色の強い独自の土器だが、こういう独自の土器がつくられた背景には、他地域との接触の少なさが一因とされる。先述の万之瀬川流域の遺跡でも古墳時代の層から成川式土器が大量に出土している。
古代南九州の人々、いわゆる隼人は、「まつろわぬ民」として表象されてきた。古墳の事情を見るかぎりそれは正しい。彼らは明らかに畿内的な秩序を受け入れていない。こういう敵対的な「異民族」とは、国家的な交易が安定的に行われたとは到底思えないのである。ともかく、考古学の知見からは、古墳時代の万之瀬川河口で交易が盛んだったとは言いづらい。
ここで改めて南島と南九州との関わりについて考えてみよう。
8世紀初頭という、南九州の人々がいまだ「まつろわぬ民」だった時期、南島人が朝貢するにあたって南島人は南九州を経由しただろうか。700年に起きた「覓国使剽劫事件」では覓国使が南九州で脅迫されているので、南島航路は南九州を経由していた。しかし、「隼人の大乱」の最中である720年に南島人232人が来朝して授位されているが、この時に彼らは南九州を経由しただろうか。そんなわけはないと私は思う。
そのことを考える上で重要なのが種子島・屋久島である。特に種子島はヤマト政権が一貫して重視していた地域である。ヤマト政権の南島政策は種・屋久からスタートした。史実かどうか不明瞭だが、『日本書紀』によれば早くも629年に田部連(たべのむらじ)某という人物が「掖玖(やく)」に遣わされている。そして679年には多禰嶋に使いが派遣され、681年に地図を提出させたという。この遣多禰嶋使は史実と思われ、ヤマト政権の南島政策が始まったことを示す。翌682年には多禰人・掖玖人・阿麻弥(アマミ)人に禄が与えられた。朝廷は早くから南島に大きな関心を寄せていたのである。ちなみに同年に「阿多と大隅の隼人が朝庭(みかど)に相撲する」という記事があるが、これが隼人の確実な初見記事である(※2)。ヤマト政権は隼人に先だって種子島との関係構築を図っているのである。
種子島の南部にある「広田遺跡」は当時の種子島の存在感を窺わせるものだ。ここは海岸に面した場所にある弥生時代後期から7世紀にかけての墓地遺跡で、157体の人骨、44,000点以上の貝製品が出土した。この遺跡では美しく加工されたゴホウラ貝の貝輪が大量に出土している。種子島にもゴホウラ貝は棲息していないから、これは交易によるものであることが明らかだ(※3)。弥生時代後期から7世紀という、ちょうど万之瀬川河口での交易が低迷していた時期に、種子島では南島交易が盛んに行われていたのである。ヤマト政権が南九州をすっとばして種子島に行くのも無理はない。
そして種子島からは、南九州を経由せずに瀬戸内・紀伊半島などにいく日本海流に乗って進む航路があったと思われる。 実際、鑑真一行のうち第3船は屋久島から出航したものの、漂流して紀伊半島の牟漏埼に着いているが、これは日本海流に乗れば紀伊半島まで直行できることを示している。安全性はともかく、この方が南島ー畿内の距離は近い。種子島こそが古墳時代の南島航路の中心だったので、種子島から瀬戸内・紀伊半島へ進む九州東回りルートがヤマト政権の公式航路となってもおかしくなかった。
だが、そうならなかった理由は明らかだろう。大宰府の存在である。
ヤマト政権が南島政策に本格的に乗り出した700年代は、大宰府が行政庁として発展していく時期にあたっていた。
そもそも大宰府は、白村江の戦いの敗戦後(663年)、朝鮮半島からの圧迫に備えるために軍事拠点として設けられた(それまでも「筑紫大宰」はあるが場所と役割が違う)。『続日本紀』の大宰府関係記事を確認してみると、7世紀末から8世紀頭には軍事関係記事ばかりである。ところが朝鮮半島との緊張状態が緩和されると、次第に西海道(九州)を所掌する行政官庁となっていった。
それを示す最初の記事は702年の「大宰府に所部の国の掾以下と郡司等の人事の選考を任せることを許した」というものである。ここで「所部の国」は明示されていないが、ともかく大宰府は「国」を所轄し、中級官人以下の人事が任されたのである。その後大宰府は天候不順による困窮をたびたび報告して「所部の国」の税の減免を訴えており、行政庁としての実体があったことが窺える。また706年には「所部の九国・三嶋が日照りや大風で作物に被害がでている」と報告しており、三嶋=壱岐・対馬・種子島なので、種子島まで所管していたことが明らかになる。
ところが、ヤマト政権の南島政策には不思議なほど大宰府の存在感がない。707年に「大宰府に使いをやり南島人に位階や下賜を与えた」という記事が一つあるだけで、これも使いの指示によって行われているので大宰府の主体性は窺えない。そしてその後の度重なる南島人の来朝や授位には大宰府が関与した記録がないのである(末尾の表2参照)。とすると、ヤマト政権の南島政策は直轄事業であり、大宰府が所轄していたのはあくまで種子島までだったと考えるのが自然である。その前提で南島人が畿内へ行く時の航路を考えると、わざわざ南九州ー大宰府を経由する必要はなく、やはり種子島から日本海流に乗って九州東回りルートを取る方が自然なのだ。
しかし「南島経営を南九州人に委託した」ことでヤマト政権の南島政策が終わりを告げたとすれば、南島の管轄は大宰府に移行したと考えられる。大宰府は南九州(薩摩・大隅)を所轄しているのだからそれが自然のなりゆきというものだろう。
ここでもう一度、735年に「南島牌」を設置したことを述べる「大宰大弐の従四位下小野朝臣老が、高橋連牛養を南島に派遣して、牌を立てさせた」という記事を見てみると、「南島牌」を「大宰府が」立てさせたということの意味が重大に思える。これは、それまで南島政策に関与していなかった大宰府が、主体的に南島経営に乗り出したことを示しているように思えてならない。そして大宰府が「南島牌」を設置する以上、南島から本土にゆく航路は九州東回りルートではありえない。南島からの船は大宰府にいく必要があるのだから、九州を西回りするルートでなくてはならないのである。そこで交易の拠点として息を吹き返すのが万之瀬川河口なのである。
そして、8世紀半ばにおいて九州西回りルートが確立していたことを示すのが、鑑真一行が秋目を目指して航行し、秋目に来着してからたった6日間で大宰府に到着している、という事実なのだ。鑑真の秋目来航は、「8世紀に南島からの航路が九州西回りルートへ変更された」ことを明証するパズルの1ピースなのである。
実際、九州東回りルートのおかげで繁栄していた種子島は9世紀には全く振るわなくなる。多褹国は824年に大隅国に編入されるが、この時の大宰大弐の上奏文(『本朝文粋』所収)が面白い。曰く、種子島は「損失ばかりで利益がない」とか「利益のない土地を守るために、有用な物資や人材を損なうことは、政治の根本に照らしても道理に合わない」などといい、「この島を(独立した行政単位から)停止し、辺境の弊害を省かれますように」と結ぶのである。かつて南島交易で栄えた種子島が、9世紀には「辺境の弊害(邊弊)」とまで言われているのである。
これに代わって殷賑を極めるのが万之瀬川河口であることはいうまでもない。9世紀に「中岳山麓古窯群」が興隆し、万之瀬川流域の遺跡では9世紀以降に交易が繁栄していることはそれを明証する。一方、南島の側で交易の拠点となったのが喜界島である。喜界島の「城久(ぐすく)遺跡群」は9〜15世紀の遺跡群で青磁などの輸入陶磁器を含む大量の陶磁器が出土しており、特に9〜10世紀には北部九州と繋がりが窺われる。9世紀以降の南島交易は明らかに大宰府の力を背景にしていた。
そう考えると、古代から中世に万之瀬川河口で交易が盛んに行われたのは、それが九州西回りルートにあたっていたからで、大宰府のおかげであるといっても過言ではない。そもそも交易は仕入れ先と売り先の両方が揃って初めて成立する。大宰府・博多という売り先があったからこそ万之瀬川河口の交易が興隆したのは明らかだ。その上大宰府は公的な後ろ盾でもある。「金峯山由来記」の「高橋殿」の伝説で、阿多郡の繁栄を築いたのが「勅使従三位兼太宰大弐蔵人頭高橋卿」という大宰府の高官だとしたのは現実を鋭く反映していたと思う。
この「高橋卿」について、知覧の歴史家・江平望さんは阿多忠景(あた・ただかげ)の「姿が投影されているようにみられる」としている(※4)。阿多忠景とは、薩摩平氏の棟梁で、大宰府と関係を持って交易に関与したと見られ、阿多郡司から「一国惣領」にまでのし上がった人物である。しかし彼は12世紀の人物だ。忠景の時代の阿多郡=万之瀬川河口はすでに大宰府との深い関係があったように思われる。私には、忠景が阿多郡と大宰府を繋いだのではなくて、もともとあった万之瀬川河口と大宰府の関係を忠景が利用したように思われるのである。
1138年、阿多忠景は金峰山中腹の観音寺に所領を寄進しているが、観音寺といえば大宰府が7世紀後半から造営した「観世音寺」が想起される。金峰山の観音寺は、近隣に「小薗遺跡」があることから交易のネットワークに関わる存在なのではと考えられているが、元来は大宰府による万之瀬川河口での貿易管理の出先機関だったのではないだろうか。この時代には末寺末社が荘園の現地管理に利用されていたのである。忠景はそこに所領を寄進することで大宰府との繋がりを強固にしたと考える方が筋が通る。
ちなみに『三国名勝図会』では、この観音寺(金峯山観音寺金蔵院)についてこう述べている。
推古天皇二年、日羅、金峯山権現を崇るや、當寺を阿多浦之名に建て、護持の精舎とし、自刻の十一面観音を安置す。(中略)保延四年、十一月、阿多郡司平忠景、阿多牟田上浦を寄附す。(後略)
保延4年は1138年であり、これは史実に正確だ(※5)。このように『三国名勝図会』の編者には阿多忠景について正確な知識があった。「金峯山由来記」に登場する「高橋卿」が阿多忠景であると考えられるならそう書いたはずだ。「高橋卿」は阿多忠景よりもずっと前の、万之瀬川河口交易を創始した人物なのである。
なお前回述べたように、中世では阿多郡は薩摩・大隅国において唯一の大宰府領であったが、これが大宰府に寄進された事情は詳らかでない。万之瀬川河口が9世紀という早い段階で交易で賑わうことを踏まえると、「荘園」という仕組みが確立する以前に、万之瀬川河口は大宰府の強い影響下にあったとするのが自然だ。事実、大宰府に属する軍事貴族が阿多忠景以前に盛んに南九州に進出している(※6)。
そう考えると、やはり阿多郡=万之瀬川河口の繁栄の始祖と呼べるのは、8世紀に大宰府の指示で「南島牌」を立てた「高橋連牛養」であるように思えてならないのである。
ところで、前回の記事を書いた後、「高橋連牛養が外から来た人物であるという可能性も捨てない方がいいのでは」というコメントが複数の人からあった。確かに「金峯山由来記」では「高橋連牛養」は大宰府から来た官人で、その居住地「高江崎」は彼の一族にちなんで「高橋」と呼ばれるようになったとしている。前回の記事では単純化して「高橋連牛養」を「南九州の豪族」だと書いたが、彼は「他所から来て南九州に土着した豪族」であったとした方が伝説に合致する。なにより「連(むらじ)」はヤマト政権に早い時期に帰順した畿内の豪族に与えられた姓(かばね)だから、薩摩国の豪族が称するのは不自然だ。
というわけで「高橋連牛養」の出身地について考えあぐねていたところ、X(Twitter)で「古墳時代史解題」さんから「越智氏の一族の可能性がある。この高橋は伊予国越智郡高橋郷の高橋ではないか」という趣旨のコメントをいただいた(今でも愛媛県今治市高橋として地名が残る)。越智氏といえば古代伊予国の豪族で、伊予国一宮であり式内社(しかも名神大社)であった大山祇神社と深い関係がある(『延喜式神名帳』の表記では「大山積神」)。これは瀬戸内海の大三島という島に建立されており、武具を中心とする多数の国宝を有していることで知られる。
大山祇神(おおやまつみのかみ)といえば、天孫降臨の神話で、天降りしてきたニニギノミコトが出会って結婚するコノハナサクヤ姫の父親が大山祇神である。そしてコノハナサクヤ姫のまたの名が「神吾田津姫(かむあたつひめ)」すなわち「阿多の姫神」なのである。というより『日本書紀』でも『古事記』でも、この姫神の名は「アタツヒメ」が基本で別名がコノハナサクヤ(木花咲耶)姫である。(※7)。 『日本書紀』は720年に完成しているが、これは「南島牌」が設置されるたった15年前だ。この神話は、大山祇神を媒介にして瀬戸内と阿多の人々に何らかのつながりがあったことを伝えている。
そして古墳時代の瀬戸内海は畿内と北部九州を結ぶ海上交通ルートであり、特に今治市が面する来島(くるしま)海峡は海上交通の要衝であった。中世では村上水軍など海賊が活躍している。今治市の高橋は、今治平野に注ぐ蒼社川(そうじゃがわ)の北側にある低標高地域で、阿多の高橋と自然条件がたいへんよく似ている。こういう自然環境におり海上交通との縁が深かった越智氏の一族なら、「南島牌」を立てることができたかもしれない。伊予国越智郡高橋郷にいた越智氏の分流に「高橋連」を名乗った家系があり、その一人「高橋連牛養」が大宰府の意向で南島を旅してから阿多に居着き、そこから阿多郡の高橋が名付けられたと考えると伝説と整合的だ。ちなみに今治市には野間神社(これも式内社・名神大社)もあり、笠沙町の野間岳にある野間神社と関係があるようにも思う。「持躰松遺跡」からは吉備系土器と見られる土師器が出土しており、北部九州を経由しない畿内・瀬戸内ルートがあったことが推測されている。中世以降も瀬戸内海と万之瀬川流域には関係があったのは間違いない。
いずれにせよ、万之瀬川河口における古代の交易が大宰府との関係で興隆したものであることは文献・考古学・伝説の全てが一致して物語っており、「高橋卿」にしろ「高橋連牛養」にしろ、そういう人物が古代に大宰府から遣わされたということは信じてもよい。
もう一度冒頭の「図1 万之瀬川河口付近の主な遺跡」の図を見てもらうと、中世以降の遺跡が万之瀬川の北側ばかりなのに気付くだろう。実は中世において、万之瀬川の北側は大宰府領だったが、万之瀬川の南側は島津領なのである(※8)。自然条件はほとんど違わないのに、万之瀬川の北側ばかりに交易の痕跡が色濃いのは、交易において大宰府がいかに大きな存在であったかを示唆している。島津氏の側から言えば、川の対岸では交易で莫大な富が動いているのが苦々しかったに違いない。そして正確な時期は不明ながら、阿多郡も島津庄に吸収され、島津氏も万之瀬川河口での貿易を手がけるようになるのである。
これまで、長々と考察を続けてきたが、それは『続日本紀』の二つの記事をどう読み解くかということににかかっていた。最後に原文で掲げよう。
<天平勝宝六年正月>壬子、(中略)入唐副使従四位上大伴宿禰古麻呂来帰。唐僧鑑真・法進等八人、随而帰朝。
<天平勝宝六年二月>丙戌、勅大宰府、去天平七年、故大弐従四位下小野朝臣老、遣高橋連牛養於南嶋樹牌。而其牌経年、今既朽壊。宜依旧修樹、毎牌、顕着嶋名并泊船処、有水処、及去就国行程、遥見嶋名、令漂著之船知所帰向。
たったこれだけの簡単な記述だが、二つの記事を有機的に連関させて読み解くことで古代の海上交通についていろいろと推測した。改めてまとめると、鑑真が秋目に来航したのは、単に高僧が来朝した第一歩であるばかりでなく、(1)南島航路が九州西回りルートとなったことと、(2)その航路が大宰府の管轄下にあったことを示し、(3)ひいては万之瀬川河口の交易の開始(中興)を暗示する徴証なのだ、ということが二つの記事から導けるのである。
ただし肝心の秋目が当時どんな場所であったかは、文献でも考古学でも全く不明というほかない。私の知る限り秋目は一度も埋蔵文化財の調査が行われていないようだ。秋目の発掘がなされれば、さらに面白い事実が解明されるのではないかと思う。どんどん過疎化し開発の見込みがない秋目では発掘調査が行われる可能性は低いが、将来ひょんなことから(崖崩れとかで)発掘が行われることを期待したい。
(終わり)
※1 出典は熊田亮介「古代国家と蝦夷・隼人」(『岩波講座 日本通史 第4巻』1994)
※2 『日本書紀』には、これ以前にも隼人の記載はいくつかあるが「蝦夷・隼人」とセットで書かれていることから後世の作為とされる。
※3 広田遺跡では、ゴホウラ貝の腕輪などが使用されているので、交易といっても最終消費地の性格もある。
※4 江平望「阿多忠景について」(『古代文化』第55巻第3号(2003))
※5 阿多忠景の寄進は、『二階堂文庫』保延四年十一月十五日「薩摩国阿多郡司平忠景解案』で跡づけられる(※4による)。『三国名勝図会』の編者はこの文書を利用したのかもしれない。
※6 野口実『列島を翔ける平安武士—九州・京都・東国』(2017)
※7 『日本書紀』本文では「鹿葦津姫(かしつひめ)<亦の名は神吾田津姫。亦の名は木花咲耶姫>」とある。第一の一書には登場せず。第二の一書では「神吾田津姫、亦の名は木花咲耶姫」。第三の一書では「神吾田津姫」。第四の一書には登場せず。第五の一書では「吾田鹿葦津姫」。『古事記』では「神阿多都比賣、亦の名は木花之佐久夜毘賣」。
※8 正確には、中世初期においては万之瀬川のすぐ南にある益山荘は弥勒寺(宇佐神宮の別当寺)の荘園であった。
【参考文献】
文中および表中で挙げたものの他に、次の文献を参照した。
- 『古代文化』55巻2-3号(特輯 11~15世紀における南九州の歴史的展開―万之瀬川下流域に見る交易・支配・宗教―)(2003)所収の次の論文
- 永山修一「『11~15世紀における南九州の歴史的展開』に寄せて」
- 柳原敏明「平安末~鎌倉期の万之瀬川下流域―研究の成果と課題―」
- 大庭康時「博多遺跡群の発掘調査と持躰松遺跡」
- 市村高男「11~15世紀の万之瀬川河口の性格と持躰松遺跡―津湊泊・海運の視点を中心とした考察―」
- 宮下貴浩「山岳寺院と港湾都市の一類型―小薗遺跡と観音寺の調査を中心として―」
- 中村和美・栗林文夫「持躰松遺跡(2次調査以降)・芝原遺跡・渡畑遺跡について」
- 山本信夫「12世紀前後陶磁器から見た持躰松遺跡の評価―金峰町出土の焼き物から追及する南海地域の貿易・流通―」
- 江平 望「阿多忠景について」(再掲)
- 倉住靖彦『大宰府(教育社歴史新書<日本史25>)』 (1979)
- 中村明蔵『隼人の古代史』(2001)
- 鹿児島大学総合研究博物館編『成川式土器ってなんだ?—鹿大キャンパスの遺跡から出土する土器—』(2015)
- 喜界町教育委員会『城久遺跡群—総括報告書—』(2015)
| 和暦 | 西暦 | 事項 |
|---|---|---|
| 文武2年 | 698 | 大宰府に大野・基肄・鞠智の3城を修繕させた。 |
| 文武3年 | 699 | 大宰府に三野・稲積の2城を修繕させた。 |
| 大宝2年 | 702 | 歌斐国から献げられた梓弓500張が大宰府に納入された。 |
| 大宝2年 | 702 | 大宰府に所部の国の掾以下と郡司等の人事の選考を任せることを許した。 |
| 大宝3年 | 703 | 天候不順により京畿および大宰府管内諸国の調を半減し、庸を免除した。 |
| 大宝3年 | 703 | 大宰府の史生を10人増員した。 |
| 大宝3年 | 703 | 大宰府の「軍功(勲位)があって位階がないものも昇叙の対象とすべき」という申請を許可した。 |
| 慶雲元年 | 704 | 信濃国から献げられた弓1400張が大宰府に納入された。 |
| 慶雲元年 | 704 | 大宰府から「昨秋の台風で作物に被害が出た」と報告があった。 |
| 慶雲2年 | 705 | 大宰府に飛駅(ひやく)の鈴8口、伝符10枚を与えた。 |
| 慶雲3年 | 706 | 諸国の飢饉に際して7条の対策が定められた。うち第4条に「大宰府所部の国はすべて庸の収めを免除する」とした。 |
| 慶雲3年 | 706 | 大宰府から「所部の九国・三嶋が日照りや大風で作物に被害がでている」と報告があったことを受けて使いに見聞させ、調役を軽減した |
| 慶雲7年 | 707 | 大宰府に使いをやり南島人に位階や下賜を与えた。 ※735年以前において大宰府が南島政策に関与した唯一の記事。 |
| 和銅元年 | 708 | 大宰府帥・大弐(ほか略)らに傔杖(護衛)を与えた。 |
| 和銅2年 | 709 | 「筑紫の観世音寺は、天智天皇が発願されたが未だに完成しないので、大宰府はこれを考慮して人員を増員し速やかに完成させるべきである」との詔があった。 |
| 和銅2年 | 709 | 「大宰帥以下の官人につける事力(労働者)を半減する。ただし薩摩・多褹の国司と国師の僧は減じない」との命令があった。 |
| 和銅3年 | 710 | 大宰府から銅銭が献上された。 |
| 霊亀元年 | 715 | (新羅使の)金元静が帰国するため、大宰府に綿5450斤と船一艘を与えるよう指示した |
| 霊亀元年 | 715 | 大宰府の官人の家口(けく)(家族?)には課役を免除する制度とした。 |
| 霊亀2年 | 716 | 大宰府の佰姓に錫を売買する「鋳銭の悪党」がいるため、私蔵を禁じ見つかれば没収することを命じた。 |
| 霊亀2年 | 716 | 大宰府に弓5374張を納入した。 |
| 霊亀2年 | 716 | 大宰府が「帥以下につけられる事力(労働者)が半減され代わりに綿が給付されているが、労働力が足りず困窮しているので、綿の給付を辞めて労働者をつけてほしい」というのでこれを許した。 |
| 養老2年 | 718 | 三関と大宰・陸奥の国司の傔杖に白丁を取ることを禁じた。 |
| 養老2年 | 718 | 大宰所部の国の庸を諸国と同じくし、先に庸の減免を行ったのを旧に復した。 |
| 養老2年 | 718 | 大宰府から「遣唐使従四位下多治比真人が帰国した」と報告があった。 |
| 養老3年 | 719 | 大宰府に大型船2艘、独底船(小型の船か)10艘を納入した。 |
| 養老4年 | 720 | 大宰府が白鳩を奉った。 |
| 養老4年 | 720 | 大宰府が「隼人が反乱を起こした。大隅国守陽侯史麻呂が殺された」と報告があった。 |
| 養老5年 | 721 | 七道按察使および大宰府に寺を併合して減らすように命令が下った。 |
| 養老5年 | 721 | 新羅貢調使の大使一吉飡金乾安、副使の薩飡金弼らが筑紫に来朝したが、太上天皇の死去のため帰国させた。 |
| 養老6年 | 722 | 「大宰府管内の大隅・薩摩・多褹・壱伎・対馬らの司(役所)に欠員があれば、大宰府の官人を選んで権(かり)に任命してよい」とはじめて制定した。(隼人征討の直後) |
| 養老7年 | 723 | 大宰府から「日向・大隅・薩摩の三国は隼人征討のために軍役が多く困窮しているので、3年間課役を免除してほしい」との申請がありこれを許した。 |
| 神亀3年 | 726 | 太政官は、新任の国司に給付する経費について規定し、大宰府およびその管内の国については特例を定めた。 |
| 天平元年 | 729 | 大宰府に調の綿11万斤を納めさせた。(大宰府貢綿の開始) |
| 天平2年 | 730 | 大宰府から「大隅・薩摩では班田を実施していないが、班田をあえて行うと訴えが多く起こると思われるので、このまま実施せず自主的な耕作にまかせる」との報告があった。 |
| 天平3年 | 731 | 大宰府に壱伎・対馬の医師を補任させた。 |
| 天平4年 | 732 | 新羅使の奈麻金長孫らを大宰府に召喚した。 |
| 天平6年 | 734 | 大宰府から「新羅貢調使の級伐准飡らが来泊した」との報告があった。 |
| 天平7年 | 735 | 大宰府では疫病による死者が多数出ているため、神祇に奉幣し大宰府の大寺と管内諸国の諸寺で金剛般若経を読誦するとともに、救恤のため使節を発遣して、長門国からの諸国では斎戒し道饗祭を祀らせた。 |
| 天平7年 | 735 | 大宰府から「管内の諸国では疫瘡が流行しているので今年の調を停止してほしい」との申請がありこれを許した。 |